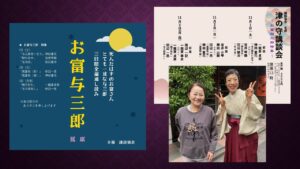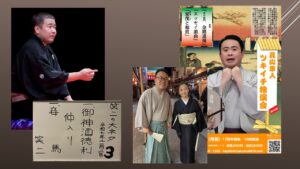津の守講談会「お富与三郎」連続口演 一龍斎貞寿「親子別れ」田辺一邑「与三郎殺し」

津の守講談会三日目に行きました。中入り後は「お富与三郎」連続口演の最終日である。
「三方ヶ原軍記」神田はるまき/「一心太助 旗本との喧嘩」田辺凌々/「曽我物語 紋づくし」神田おりびあ/「西遊記 芭蕉扇」田辺一記/「萩原タケ」一龍斎春水/中入り/「お富与三郎 親子別れ」一龍斎貞寿/「お富与三郎 与三郎殺し」田辺一邑
貞寿先生の「親子別れ」。佐渡に遠島になった与三郎だが、人足として朝から夜まで泥まみれになって働き詰めの日々で身も心もボロボロに。「お富に会いたい」の一心で、仲間三人で結託して島抜けを敢行する。嵐で船は粉微塵になり、一人は海に投げ出される。残りの二人で高崎まで行ったが、相方は病死、与三郎は独りきりで江戸へ出る。
日本橋横山町の実家、伊豆屋の前で様子を窺うと、中から数人の僧侶が出てきた。その後、番頭が棟梁の弥七を見送りに出た。番頭が引っ込んだところで、与三郎は弥七に声を掛ける。驚く弥七。何かあったのかと訊くと、与三郎の母の百箇日の法要だったという。母親は「ご新造は若旦那のことを心配し、瘦せ細ってしまい、床に伏した。心残りは与三郎のこと。あんな良い子が悪事に手を染め、死んでも死にきれない。一目会いたい」と言っていたという。
大旦那は「与三郎は佐渡島の厳しさに堪えかね、とても生きていられないだろう。冥途へ逝けば、与三郎に会える。私は養子を貰って身代を継がせ、出家して菩提を弔う。だから、安心して先に逝っておくれ。私もほどなく追いかける」と言うと、女将さんは程なくして亡くなったという。親不孝というのは酷いものだ、なんであんなことをしたのかと与三郎に詰問する。
与三郎は佐渡島での過酷な労働が辛く、また会いたい女もいる、両親にも会いたいという想いが募り、命からがら島抜けしてきたと話す。弥七は「悪党におなりになりましたなあ」と言った後、「よろしかったら、大旦那に一目会ったらいかがですか」と提案する。しかし、与三郎は伊豆屋の看板に傷をつけてしまうから、それはできないという。幸い、弥七に会うことができた、「心の底から詫びていた」と伝えてくれと頼む。
母親が眠っている深川浄真寺の墓にお詫びに行ってから、「会いたい女」に会って、その後でお上にお恐れながらと自訴するつもりだと言う。すると、弥七はお富は赦免されて、品川の観音の久次という博奕打ちに引き取られたという噂を教える。「一目会いたい。お富の酌で酒を飲み、ニッコリと笑ってもらったら、思い残すことはない」と言い、番所に自訴して、お仕置きを受けるつもりだ。
弥七が言う。自訴して、鈴ヶ森で磔になったら、そのことが大旦那の耳に入り、さぞ悲しむだろう。どこか遠くへ逃げてください。甲州の身延山でご出家なさい。菩提を弔うことこそ、親孝行ですよ。ここに三十両あります。命だけは助かりますように。
与三郎は「親父のことは頼んだ」と言って去る。弥七は後ろ姿に両の手を合わせ、伊豆屋へ引き返す。大旦那に今、若旦那に会ったと伝え、私たちの知っている若旦那じゃなかったと言って、一部始終を語る。すると、大旦那は「なぜ、私に会わせてくれなかったのか」と責める。店に迷惑はかけられない、このことが知れたら、土地も建物も召し上げられてしまうと遠慮したのだと説明すると、大旦那は「真の悪党になったとて、倅であることに変わりはない。屋敷がどうなろうと構わない。なぜ、声を掛けてくれなかった」と涙した。
一邑先生の「与三郎殺し」。お富は観音の久次と夫婦同様の暮らしをしている。久次は夜中眠れずに、お富に酒を用意させ、二人で酌み交わしながら、「不思議な縁だ。与三郎が見たら、悔しがるだろう」と話し、お富も「今が一番幸せだ」と言う。そこへ戸を叩く音がする。「与三郎でございます。お富に一目会いたくて…」。
びっくり仰天のお富と久次。「実は島抜けをして…」と一部始終を久次に話すと、奥からお富が出て来る。何で今更と心では思ったが、「よくぞご無事で…あんまり嬉しくて…」と嬉し泣きをする。久次は気を利かせ、「俺は明日から四、五日、横須賀へ出掛けなくちゃいけない」と言って、「役所に訴える野暮はしない。つもる話もあるでしょう。ゆっくりなさい」。そう言って、洋箪笥にある五十両を渡す。
二人きりになったお富と与三郎。つもる話をしながら、酒を酌み交わすが、与三郎は疲れが出たのだろう、そのうちに寝入ってしまった。お富は考える。島抜けまでしてくるとは。今は安穏な暮らしをしているのに。困りものだ。一日寝た与三郎が起き出し、また飲み直す。与三郎がお富に絡む。「あの久次といい仲になっているんだろう」。これに対し、お富は「あの人は女嫌い。そんなことはない」。また与三郎はゴロッと寝てしまう。床に入らないと風邪をひくという言葉も聞かず、眠っている。起きない。
お富は段々と与三郎がふてぶてしい悪党に見えてきた。気持ちが醒めたのだ。「もう、嫌だ。与三さん、お前との縁はこれまで。今が幸せ。私の前から消えておくれ。どうせ磔になる身なら、私の手であの世に逝かせてやろう。それが本望だろう?」。寝顔を見つめ、意を決して、家の締まりをする。
細引きを柱と与三郎の首に巻いて、思い切り引っ張る。「堪忍しておくれ。この幸せを手離したくないんだ。私のことを思うんだったら、死んでおくれ」。呆気なく、与三郎は死んだ。死骸を葛籠に仕舞い、蓋をしたとき、表で戸を叩く音がする。「六でございます」。久次の子分のさざえがらの六蔵だ。葛籠は次の間に隠す。
六蔵は親分の遣いで来たという。五十両を渡したが、足りないだろうからと、もう五十両を持ってきたのだ。ここでお富はあることを思いつく。「飲んでおいきよ」と六蔵を家に上げ、色仕掛けで迫る。「お前みたいに優しい人を亭主に持ったら幸せだよ」と心にもないことを言って、膝をつねる。そして、「私を連れて逃げておくれ。久次には世話になって有難かったが、愛想が尽きた。六さん、夫婦になっておくれ」と言って、得意の流し目をする。もう六蔵はイチコロだ。
「今だよ。五十両と五十両で百両ある。下総銚子、越後新潟、いっそ蝦夷函館にでも渡ろうか。ついちゃあ、私の葛籠を持っておくれでないかい?」。重いと嫌がる六蔵に対し、強引に葛籠を背負わせ、家を出て歩を進める。万年溜め(ゴミ捨て場のようなもの)が目に入ると、突然「やっぱり、こんな重いものは足手まといだ」と言って、「ここへ打っ棄っておこう」と二人で放り込む。
一安心したお富。今度は古井戸が目に入った。「中を覗いてごらん。星が映って綺麗だよ…あれ?あそこに小判が…」「どこですか?」「よく覗いてごらん」。井戸に身を乗り出した六蔵を突き落とす。そして、大きな石をいくつも投げ込み、落命させてしまった。おそるべし、悪女。
だが、天網恢恢疎にして漏らさず。やがて、お富は召し捕られ、市中引き回しの上、鈴ヶ森で磔になったという…。「お富与三郎」読み終わり。壮絶なドラマであった。