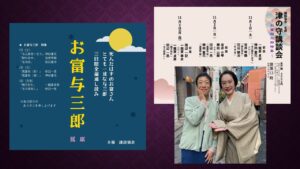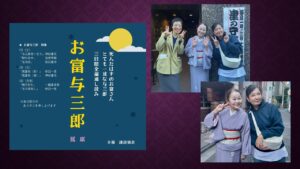津の守講談会「お富与三郎」連続口演 田辺一邑~神田菫花「茣蓙松」リレー

津の守講談会二日目に行きました。昨日に引き続き、中入り後は「お富与三郎」の連続口演である。
「三方ヶ原軍記」神田はるまき/「千葉周作 幼年時代」宝井優星/「木村又蔵鎧の着逃げ」一龍斎貞介/「怪人二十面相 黄金塔」宝井小琴/「大岡政談 五貫裁き」/中入り/「お富与三郎 茣蓙松」(前)田辺一邑/「お富与三郎 茣蓙松」(後)神田菫花
一邑先生の「茣蓙松」前編。与三郎とお富は玄冶店で夫婦として暮らすが、仕事をするわけではないから、生活費に困った。手っ取り早く稼ぐ手段はないか。お富はある日、日本橋通一丁目の白木屋で白縮緬を一反、買い求めた。その足で、今度は大伝馬町の大丸屋へ行く。白縮緬の反物を見せてほしいと言って、出してもらうと、袂に入れてあった白木屋で買った白縮緬一反を一度出して、再び袂に戻した。そして、「気に入ったものがないので帰ります」と店を出ようとすると、店の者が「ご冗談はやめてください。品物は置いて帰ってください」と止める。
ここがお富の腕の見せ所だ。私が品を盗んだとでも…恥をかかすつもりか。裸になってみせましょう。それで品が出たなら、番屋へ届けてください。もし出なかったら、容赦しませんよ。果たして、一反の白縮緬の反物が出てきたが…。この店の品ではないことくらい判るでしょう。白木屋で買ったものです。受け取りだってある。同じ白縮緬でも、品が違うことは明らかだ。
番頭の卯兵衛が出て来て、平身低頭、詫びる。「申し訳ございません。ご勘弁を」「裸にされて、恥をかかされて、はいそうですかと引き下がれるものか。この始末、どうつけてくれるんだい」。お富は店先で寝っ転がって、騒ぐ。番頭は店の暖簾がある。十両を出して、「これで勘弁してください」。お富は「金でカタがつく私じゃない!」。すったもんだの挙句、三十両という金を懐に入れることができた。
そんな騙りをあちこちの店でしたが、ネタが尽きた。別の手を考えなくては。お富と与三郎が酒を酌み交わしながら、策を練っている。すると、にわか雨。軒先に雨宿りのつもりだろう、六十くらいの男が立った。立派な身なりである。お富は与三郎に耳打ちをして、奥の間に引っ込んでもらう。そして、「そこの方、どうぞ中へ」と声を掛ける。「私は雷が大嫌い。先年、主人を亡くして一人なもので心細いんです」。男は「お言葉に甘えて」、通されるままに二階へ上がる。
お召し物が濡れている、乾かしましょう、風邪を召すといけないと言って、着物を脱がし、女物の浴衣を着せる。そして、酒と肴を運んでくる。「ちょうど一人でやろうと思っていたんです。酒は一人より二人の方がいいです」と甘い言葉を投げ、「旦那はどちら?」と訊く。「芝田町の松屋喜兵衛です」。通称茣蓙松。畳表の問屋の大店だ。いいカモだとお富は思う。
「私は男運がないんです。三年前に亭主と一緒になったんですが、昨年亡くなりました。なかなか良い縁がないんです。どこかに良い方を世話してくれる方はいないかしら。私みたいな年増のおかめじゃ駄目ですよね」。これに対し、茣蓙松は「とんでもない。もし私で良ければ、相談に乗りますよ」。そこに落雷。お富が旦那の膝にしがみつく。
そこへ良いタイミングで与三郎が現れる。「立派な亭主がありながら、こんな爺さんと!」と、出刃包丁をふりあげる。「ご勘弁ください。何かの間違いです」と言う茣蓙松だが、お富は会ったばかりの男をさも以前からの仲のように言う。茣蓙松は「なんでもします。命ばかりはお助けを」。その言葉を聞いて、与三郎は「いくら出すんだ」、茣蓙松が「間男は七両二分という相場がありますが、二分でご勘弁を」「ふざけるな」「では相場の七両二分で…」「だめだ」「一体、いくらなら」「百両出しな」。
お富も「旦那、仕方ありませんよ。旦那だって、少しの間、いい思いをしたんだから、金を払った方が身のためですよ」。与三郎は「しょうがない。五十両で勘弁してやる」。茣蓙松は「生憎、持ち合わせがない。明日、必ず届けます」と言うと、「じゃあ、証文を書いてくれ。もし届けなかったら、店に乗り込み、居座るぞ」。茣蓙松は紙入れに八両二分あったので、それを前金として受け取り、残りの四十一両二分を届けてもらうことに。だが、証文は「五十両と書け」。茣蓙松は証文に爪印を押して、この場を去る。
茣蓙松は考えた。これで五十両で許してもらえないかもしれない。度々無心に来られたら始末が悪い。自分の地所で家主をしている伊之助は肚が座っている。伊之助に頼んで仲介してもらおうと考えた。
菫花先生の「茣蓙松」後編。茣蓙松の隠居は早速、伊之助に相談に行く。一部始終を話し、明日の昼に玄冶店に行って後腐れがないように話をつけ、証文を取ってきてほしいと頼む。伊之助は「相対間男(あいたいまおとこ)」であることを承知して、これを引き受ける。前金に払った八両二分は厄落としと諦めて、新たに五十両用意するように言う。さらに、遣い賃として一両を貰うことになった。相手は玄冶店のお富という女と傷だらけの男だという情報だけで、伊之助は翌日に出掛ける。
伊之助がお富と与三郎を訪ねると、お富はいい女だということ、男はどこかで見たことがあるなと思った。伊之助が「金は持ってきたんだろうな」と言う与三郎に対し、切りだす。「あー、思い出しました。日本橋横山町の伊豆屋の若旦那、与三郎さんでは?…よく覚えています。すっかり立派になられて。元は貸本屋をしていて、伊豆屋さんには懇意にしてもらいました。旦那も女将さんも情けに厚い方でした。ご両親が目に入れても痛くない可愛がりようだった与三郎さんが、こんな姿になって…」。涙をこぼす。
さらに続ける。「こんな悪いことをしているとご両親が知ったら…お縄にかかったら、さぞお嘆きになるでしょう。これも何かの縁。お店にお帰りになりませんか?ここにいるお綺麗な方と一緒にお店に帰りませんか?」「できるのか?」「伊豆屋と懇意にしている者が大勢おります。そうなさってはいかがですか?悪いことは言いません。お天道様が見ています。お縄にかかったら、大変です。私は奉行に訴えて、酷い目に遭わせようと思っていました。でも、相手が与三郎さんと判ったら、そんなこともできない。私に花を持たせてくれませんか?茣蓙松の隠居はああ見えて金が自由にならない身の上なんです。何とか工面した、この十両を納めてくれませんか。これが精一杯なんです。どうか、ご勘弁を。不承知なら、奉行に相談します。これで、お許しを…」。
あれだけ強気だった与三郎が両親のことを言われ、弱気になったのか、「しょうがないね」。やきもきしていたお富が堪りかね、声を掛けようとする前に、伊之助が大きな声で「ありがとうございます!」。その勢いで、これ以上何も言わないという一筆を証文に認めさせてしまう。「内金が八両二分ですから、差っ引き、おまけして二両」と言って、二両だけ渡して「それではこれで失礼します」。伊之助は去って行った。お富が言う。「与三さん、一体何なの?」「よく喋る奴だった」。お人好しの与三郎にすっかり呆れたお富は「甘い!ああ、また考えなくちゃ」。
半月後。お富のところに小間物屋がやって来た。櫛を買い求める。お茶でも…と誘い、「何か近頃面白い話はないか」と訊くと、小間物屋は「四十九両儲けた話」をする。「私の伯父さんなんですがね、相対間男の掛け合いに行ったそうです。それで一度顔を見たことがあるだけの男に、知り合いでも何でもないのに、あることないことでっちあげて、示談金五十両を二両に負けさせたそうです」。お富が何と言う名前かと訊くと、「伊之助の伯父さんです。あんな馬鹿がいるんだねと笑っていました」。
お富と与三郎は気が済まない。乗り込もう!と芝田町の長屋に行くが、伊之助には軽くあしらわれてしまった。そこで松屋の店先に座り込み、「隠居に会わせろ」と脅すが、常廻り同心に店の者が通報し、二人はお縄にかかってしまった。奉行の与田豊前守の裁きで、お富は永牢(無期懲役)、与三郎は佐渡島に遠島になった…。