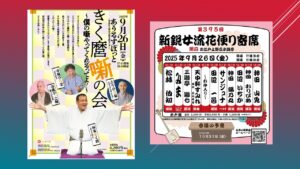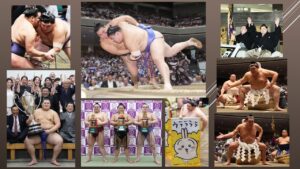黒談春 立川談春「三軒長屋」、そして田辺いちか いざ真打へ!「玉川上水の由来」

「黒談春~立川談春独演会」に行きました。「小猿七之助」と「三軒長屋」の二席。
「小猿七之助」は巧者が演じると情景が浮かぶ。滝野屋のお滝は惚れている七之助と二人になりたくて、ご法度である一人船頭一人芸者の禁を破った。七之助が助けた身投げの男、田島屋の幸吉から理由を訊くと、イカサマ博奕で店の金30両を取られたという。そのイカサマ博奕の男は深川相川町の網打ちの七蔵。七之助の父親だ。七之助が十四歳のとき、盗んだ金に佐竹様の刻印がしてあって七蔵はお縄になりそうになったが、七之助が「蜆を採っていたときに拾った」とデマカセを言って、父親の身代りになってやった。だが、七蔵は相変わらず改心していない。それでも、父親を守ってやりたいと思う息子の気持ち…。
一旦は助けてやった幸吉の背中を押して、川へ突き落とす。その現場を目撃したお滝には死んでもらうしかないと、匕首を突きつける七之助。しかし、お滝は抵抗しない。「惚れた男に殺されたら幸せ」とまで言う。その勢いでお滝は一人船頭一人芸者という選択をした理由を告白する。「同じ苦労をするなら、惚れた男としたい…」。お滝が七之助を口説きにかかるところで終わる。神田伯龍の講談に惚れこみ、談志が落語にしただけあって、“美”を感じる高座である。
「三軒長屋」。江戸前の登場人物たちをイキイキと活写するのが、この落語の肝だと思う。鳶頭の政五郎の女房の姐御肌、小股が切れ上がったいい女で、勝気なところが良い。隣に住む伊勢勘の大旦那の妾に自分の亭主が「どぶっつぁらい」扱いされたことに憤るところ、同じ女としての対抗心のようなものを感じる。
鳶頭の子分たちが、その妾の女中のことを囃し立てるのも面白い。「背比べなら横からこい」「走るな、転がれ」、挙句には「化け物」扱い。同様に伊勢勘がやって来ると、「薬缶が飛ぶ!」と叫ぶ。喧嘩はしないという約束で二階を借りたのに、三年前の暮れの二十七日に居候をさせて助けてやった、そして正月の獅子舞を手伝わせたらドジを連発した、と詳細に辰公が八公の弱味を言い立てるものだから、八公が刺身の皿を投げつけて、辰公が出刃包丁を持ち出して、「さあ殺せ!」と大騒ぎになるところも、江戸っ子連中の気質がよく出ていて愉快だ。
伊勢勘が「この長屋は自分の家質(かじち)に入っている。もう少しで抵当流れする。そうしたら、鳶頭の家は庭にして、楠木先生の道場は離れにする」と言って妾と女中をなだめるが、それが逆に鳶頭チーム(特に姐御肌の女房)の対抗心に火を点ける形になるのが楽しい。そして、鳶頭と楠木先生の採った秘策「お互い引越し作戦」で伊勢勘にギャフンと言わせる最終盤。何が言いたい落語なのかと問われれば、特に何もない。だから、演じ手が少ない噺なのかもしれないが、こういう登場人物がワイワイと沢山出て来て、それを演じ分け、なお且つ楽しく笑わせてくれる。力量が問われる噺を談春師匠は「疲れるんだ、この落語」と言いながら、すっかり観客の心を掴んでいる。すごい。
「田辺いちか いざ真打へ!」に行きました。「三方目出鯛」「木村長門守重成の最期」「玉川上水の由来」の三席。開口一番は神田おりびあさんで「小松菜の由来」だった。
「玉川上水の由来」。按摩の松の市が先代に言われたという「真っつぐな道を歩いていたら、神様も仏様も見捨てることはない」という言葉を、玉川庄右衛門・清右衛門兄弟に言い残していったところがとても印象的だった。
神田上水だけでは江戸の町の水を賄うことはできなくなり、十里ばかり離れた羽村の地から武蔵野台地を通って水路を引くという構想に対し、百姓である庄右衛門・清右衛門兄弟が提出した図面が一番優れていると採用され、その職務を任された。
だが、何せ初めて行う工事。経験がないために目論見は様々な手違いを生み、思うように進まない。幕府から下げ渡された金は底を尽き、三度の追加資金、それに兄弟の田畑や山といった私財を売り払っても完成に至らなかった。そればかりか、世間は幕府からの調達金は全部自分たち兄弟の懐に入れ、人足にはろくに賃金を払わないと批判に晒される。この誤解は辛いだろう。水路は幡ヶ谷の不動の森まで来ている、九分通り出来た、あと300両あれば出来上がるのだが…。
庄右衛門が呼んだ按摩の松の市がこの事実を訊き、世間の噂と乖離していることを気の毒に思う。そして、今度は自分の身の上を聞いてくれと言う。三歳か四歳の頃、薬缶の煮え湯を頭からかぶってしまい、こんなただれた顔になってしまった、そして両目も潰れてしまった。親は見捨て、松の市という按摩の師匠が拾ってくれて親代わりとして育ててくれた。師匠はいつも「真っつぐな道を歩けば、神仏は見捨てない」と口癖のように言っていた。だが、自分が十歳のときに流行り病で亡くなった。
世間は按摩などに治療をしたり、薬をやったりするのは後回しという考えだ。だけど、俺たちだって人間だ。人間らしい扱いをしてもらいたい。松の市の名前を継いで、按摩を続けた。納め金を払えば、按摩も位をもらい、人間扱いされると聞いた。検校になるには千両、座頭になるには三百両必要だ。毎日暮らしを切り詰めて、コツコツと働き、金を貯めた。女房を貰わないかと誘われたが、金がかかると断った。そして、ようやく三百両が貯まった。来春には幕府に願い出るつもりだ。
そこへ金策に走っていた弟の清右衛門が帰ってくる。「みんな、門前払いで駄目だった。もう、腹を切って詫びるしかない」。人足頭の吉五郎が「明日中に賃金を払わないとお前らをぶち殺す。掘ってきた水路も埋めちまう」と言っているという。庄右衛門は松の市に療治代として1両を渡す。相場は20文のところ、「座頭になる前祝いだ」。松の市は「旦那、真っつぐな道をお行きなさい。短気なことはおやめください」と言って去って行った。
兄弟は人足たちが集結している幡ヶ谷へ。吉五郎が「金はできたのか」と訊く。「できなかった」と土下座する兄弟、「打つなり、蹴るなり、殺すなり、好きなようにしてくれ。だが、心血を注いだ水路だけは埋めないでくれ」と嘆願する。そこに、「兄弟への届け物」を受け取ったと一人の人足がやって来る。ズシリと重みのある金包み。化け物のような按摩が持ってきたという。二十五両の切り餅が6個ある。三百両に按摩の笛が添えてあった。「松の市さんだ!」。だが、もう姿は見えなかった。「一旦はありがたく受け取り、必ず後日にお返ししよう」。
三百両のお蔭で、工事は捗る。12月14日、完成。羽村からの水は四谷大木戸までの十里あまり、およそ43キロの水路を通って、江戸市中に流れ込んだ。庄右衛門・清右衛門兄弟は玉川の苗字を与えられ、侍になった。「検校になってもらいたい」。血眼になって松の市を探したが、その姿を見ることはできなかった。玉川上水は私財を投げうった兄弟の手柄でできたものではない。「真っつぐな道を行け」。そこに一人の按摩の教えと資金援助があって初めて完成を見たのだ。素敵な人情譚である。