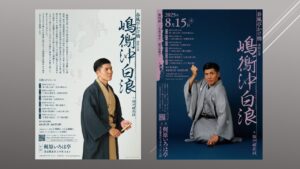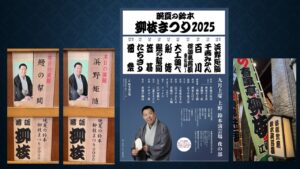浪曲定席木馬亭 港家小ゆき「伊能忠敬 晩学の星」玉川奈々福「天保水滸伝 亡霊剣法」木村勝千代「天保六花撰 三千歳廓抜け」港家小柳丸「神田祭 勇みの吉五郎ご恩返し」

木馬亭の日本浪曲協会九月定席五日目に行きました。
「恋と武士」富士琴哉・水乃金魚/「織田家仕官」天中軒かおり・沢村理緒/「伊能忠敬 晩学の星」港家小ゆき・佐藤一貴/「天保水滸伝 亡霊剣法」玉川奈々福・広沢美舟/中入り/「四代小団次 白州見得」天中軒景友・広沢美舟/「杉原千畝」神田伊織/「竹久夢二の女」澤順子・佐藤貴美江/「中山安兵衛婿入り」天中軒雲月・広沢美舟
小ゆきさんの「伊能忠敬」、とても良かった。下総国佐原で隠居をして江戸に出てきた五十歳の忠敬、幕府天文方である三十一歳の高橋至時に入門したときの並々ならぬ熱意。正確な暦を作りたい、そのために地球の大きさを知りたい。浅草と深川の間を歩数を数えながら歩き、北極星の見える角度の誤差から地理を類推することを日課とした忠敬は「推歩先生」と渾名された。
高橋が堀田摂津守からロシアに対する国防のために「蝦夷地の測量」を命じられたとき、即座に忠敬を適任者として推薦したのも当然だろう。忠敬ほどの学問への執着心、そして測量技術を持った人間はいなかったからだ。忠敬は期待に応え、江戸から蝦夷地まで180日をかけて歩いて測量し、その膨大なデータを基に地図を作った。
この正確な地図を摂津守と高橋は松平伊豆守に謁見し、見てもらう。「見事だ。この地図に測量した人物の人となりが描かれている」と賞賛。そして、日本全国の地図を作製するように命じたという。忠敬、このとき五十五歳。世の為、人の為、果てない大地に向かう国家の大事業を担った。その成果は日本が開国したときに、世界が絶賛したという。まさに「晩学の星」。素敵な高座だった。
奈々福先生の「亡霊剣法」。平手造酒が笹川繁蔵と出会い、その用心棒となり、大利根河原の決闘で活躍し、敵の闇討ちで果てるまでを、恋女房だった島乃の亡霊という視点から描いているのが興味深い。
平手は大事な恋女房の島乃を他人に騙されて斬っちまった。以来、島乃の亡霊が平手の背後につきまとっている。繁蔵は平手の後妻になった取手宿の旅籠の女中頭のお信に150両を渡して、用心棒にした。だが、平手を引き取るということは、つきまとう島乃の亡霊もセットで引き取るということだった。
飯岡助五郎一家300に対し、笹川繫蔵一家は100足らずの勢力しかいない。それでも互角に戦えたのは平手につきまとう亡霊のお陰だったのか…。飯岡の用心棒、成田の甚蔵に闇討ちされて平手は最期を遂げた。きっと島乃の亡霊も、そのときに初めて成仏したに違いない。
伊織さんの「杉原千畝」。第二次世界大戦でソ連がポーランドに侵攻し、リトアニアに多くのユダヤ人難民が押し寄せた。ソ連がポーランドを併合すると決まったとき、多くのユダヤ人難民がリトアニアの日本領事館にやってきて、日本を通過するビザの発給を求めた。だが、日本外務省の答えは「拒否せよ」。
だが、領事官だった杉原はこれを見棄てることが出来なかった。日本外務省の訓令に違反して、独断でビザを発給する。その数、2000。だが、その杉原の独断によって多くのユダヤ人の命が救われた。その恩をユダヤ人たちは終戦後も決して忘れることがなかった。杉原千畝の名前は世界中のユダヤ人に知れ渡った。だが、終戦後に帰国した杉原を外務省は訓令違反として解雇した。
1985年にイスラエルの外務大臣が来日したとき、パーティーに杉原は招待され、「諸国民の中の正義の人」という称号を与えられた。出席していた中曽根首相も、安倍外相も杉原を知らなかった。やがて、日本にも杉原千畝の功績が知られるようになる。86年、杉原は86歳で逝去。日本政府が公式に謝罪したのは2000年のことである。この読み物が素晴らしいのは終戦後の日本政府の無理解を指摘し、もし杉原が外務省に引き続き勤務していたら、もっと大きな功績を残したに違いないと批判しているところだ。
雲月先生の「安兵衛婿入り」。最後の雲月バラシ。堀部弥兵衛金丸が両手をついて安兵衛に対し、頭を下げて「たった一人の娘。嫌かもしれないが、どうか婿になってやってくれ」と涙を零して頼む。これに対し、安兵衛が「それほどまでに買ってくれているのか」と感激し、中山の姓を捨てて堀部の婿に入ることを承知するところ。これぞ、浪花節である。
木馬亭の日本浪曲協会九月定席千秋楽に行きました。
「神田松」東家一陽・東家美/「文七元結」富士実子・沢村道世/「紀文戻り船」真山隼人・沢村さくら/「天保六花撰 三千歳廓抜け」木村勝千代・沢村まみ/中入り/「紺屋高尾」国本はる乃・沢村道世/「大田南畝」田辺鶴遊/「神田祭 勇みの吉五郎ご恩返し」港家小柳丸・佐藤貴美江/「夕立勘五郎 吉原高窓太夫との出逢い」東家一太郎・東家美
勝千代さんの「三千歳廓抜け」。河内山の策略で三千歳を大口楼から足抜けさせることに成功するが、片岡直次郎が行った風呂屋で大口楼の寝ずの番だった三次が直次郎に嫌疑をかける。直次郎と三千歳の定紋が比翼に彫られた腕守りを証拠に番所に訴えるが…。「痩せても枯れても天下の御家人」という直次郎の度胸、そして「そんなものが証拠になるか」というハッタリをかます河内山の貫禄が上をいった。
早く夫婦になりたいと急く直次郎と三千歳に対し、狂言作者である河内山の冷静がキラリと光る。三千歳を一旦、どこか金持ちの妾にあてこもうという作戦。そこで三千歳は日本橋の廻船問屋、森田屋清蔵の名を挙げる。「忘れないでね、直さん」と言いながら、三千歳は日本橋へと向かう。これで首尾よく事が進むと思ったが…この森田屋の裏の顔が海賊という悪党だったとは!というところで、ちょうど時間となりました。惜しい切れ場だ。
はる乃さんの「紺屋高尾」。高尾が久蔵に「今度はいつ来てくんなます?」と訊いて、嘘をつき通せない久蔵の純情が良い。三年前、花魁道中で「こんな綺麗な人はいない」と一目惚れしたこと、自分は上総の大尽の若旦那ではなく紺屋の職人であること、十五両なんて金はそう簡単に拵えることができないこと。そして一つのお願いをする。この広い江戸のどこかで会ったら、ニッコリ笑って、「久さん、元気?」と言ってほしい。
これを聞いて、高尾は久蔵に惹かれる。遊女は客に惚れたと言い、客は来もせで、また来ると言う。嘘と嘘の色里で恥も構わず身分までよく打ち明けてくれました。あなたのような正直を捨ておいて他の男にいくわけがない。女冥利に尽きる。わちきも人の子。あなたの正直に初回惚れしました。そう言って、夫婦になったときに役立ててほしいと三十両を久蔵に渡す。嘘で固めた吉原のファンタジーである。
小柳丸先生の「勇みの吉五郎ご恩返し」。神田白金町の絹問屋、萬屋の主人の五郎兵衛が吉原の三笠屋勘兵衛で働いている娘のお花を神田祭のために身請けしなければならず、百両が必要となった。質屋の井筒屋惣兵衛に相談したが、相手にされない。その話を聞いた大工の吉五郎は五郎兵衛を助けたいと思う。なぜなら、先代の萬屋五左衛門に恩義があるからだ。
吉五郎は女房のお蔦に相談すると、意見が一致した。今持っている長屋二十五軒と家財道具、大工道具一切を井筒屋に売り払い、百両を拵えて三笠屋勘兵衛のところに行って事情を話す。勘兵衛は理解のある人物で、五十両でお花を手離した。吉五郎、お蔦、お花を乗せた駕籠三挺が萬屋五郎兵衛宅へ到着。五郎兵衛は目に涙を浮かべて喜んだ。そして、お花は神田祭の山車を曳き、その美貌は江戸中の評判となる。
この姿を見た井筒屋惣兵衛の息子、惣三郎は「お花を嫁に貰いたい」と言い出す。惣兵衛は吉五郎に相談するが、「きっぱりと断る」と当然言う。惣兵衛は反省し、「私が悪かった。心を入れ替える」と頭を下げる。そこで、吉五郎は井筒屋の身代二十万両の一割の二万両を萬屋に譲渡することを条件にして、井筒屋惣三郎とお花が夫婦になることを認めた。そして、吉五郎夫婦が仲人になり、婚礼。傾いていた萬屋の経営は立ち直り、再興なったという…。素敵な読み物だった。