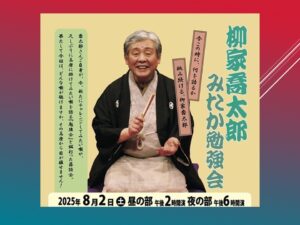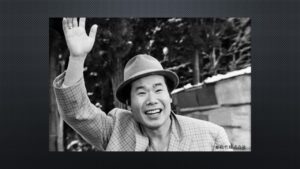よせによせ

NHK総合テレビで「よせによせ」を観ました。パイロット番組として今年1月放送の第1回に続く第2弾だ。
浅草にある木馬亭での収録。進行は前回と同じ桂二葉さんと春風亭一花さん、そしてゲストは世界的指揮者である佐渡裕さんだった。佐渡さんは高校生の頃に桂枝雀師匠にはまり、海外に行くときも常に枝雀師匠の落語のテープを持って聴いていたという。
佐渡さんは言う。枝雀師匠は古典でありながら、チャレンジ精神旺盛で、常に改革をしていて、「座布団からはみ出す」高座が魅力だ、と。佐渡さんの指揮はクラシック音楽でありながら、無意識に指揮台を飛び跳ねるようなところがあり、「共通しているのかもしれない」。二葉さんが我々も古典落語という決まったベースがあっても、「自由にやりたい」と思っているところがあり、それでアドリブが自然に出てくることもあると共通点を見つけているのが興味深かった。
昭和53年に桂米朝師匠(当時52歳)が枝雀について語っているインタビュー映像が紹介された。いわく、感覚が独特なんですな、江戸から現代に移動してきたような、これは誰にも真似することができないことです。同じ年のインタビューで枝雀師匠(当時38歳)は「落語を漫画化する、誇張をして、繰り返しを増やす」と自分のテクニックについて語っている。
そして、昭和56年放送の「花の落語家独演会」の「池田の猪買い」の高座が紹介された。猟師が猪を狙うのに、脇で喜六がごちゃごちゃ言って集中力を削ぐという一番の笑いどころだ。この噺は二葉さんも演じるが、喜六の「飛び抜けてアホ」なところが肝要。アホだけど愛しいキャラクターが良い。あと、普通は扇子を鉄砲に見立てて演じる、実際に二葉さんもそうだが、枝雀師匠は手拭いを使って表現していた。この発見も面白い。
二葉さんが高座で「つる」を演じた。鶴の名前の由来を甚兵衛さんから聞いて、甚兵衛さんが「今のは嘘や」と言うのも聞かず、「つるの因縁」をどこかで披露したいという男の純粋さが見事だ。仕事をしている徳やんのところに行って、「日本のアホが来た」と言われながらも、「昔は鶴とは言わなんだ」と甚兵衛さん仕込みの「つるの因縁」を得意げに喋る男が可愛い。甚兵衛さんのことを「生き字引」でなく「生き地獄」というのも笑える。
この他、高座で披露したのは二組。漫才のヤーレンズはパン屋「パンデミック」で店主クロワさんが“パンシュルジュ”としてお客さんにピッタリのパンを薦めるというネタ。シュールな展開が可笑しい。
もう一人はバイオリン漫談の福岡詩二先生、御年九十一歳。バイオリンを弾いているうちに、どんどんバイオリンが壊れていく。そのうちに弓も切れてしまう。葱を取り出し、「カーネギーホール」の洒落。ナンセンス極まりない笑いが愉しい。
最後は前回もあった「勝手に吹き替え劇場」。今回も昭和35年放送の西部劇「ボナンザ―殺し屋兄弟―」の一部から。春風亭与いちさんの「機種変更」が面白かった。安心サポートパックを説明する女性がはまっている。桂三実さんの「文化祭の出し物」、どこのクラスもタピオカ屋を出店したいというのが可笑しい。立川かしめさんの「なぞかけ戦争」は、牢屋に入っている二人の男がスパイと小説家というオチが効いていた。
この「よせによせ」、いつかはレギュラー番組になるのだろうか。今は朝5時の放送だけど、プライムタイムで是非放送してほしい。NHKの豊富なアーカイブス映像を利用した、一捻りも二捻りもした従来にはない演芸番組に注目である。