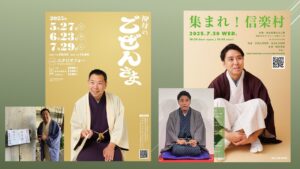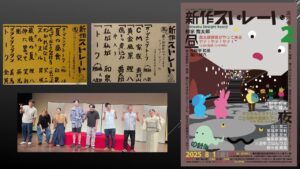SWAクリエイティブツアー、そして つる子の赤坂の夜は更けて 林家つる子「しじみ売り」

SWAクリエイティブツアーに行きました。
今回は「蔵出し」ということで、各々がSWA以外で新作ネタおろししたが、その後あまり演じていない作品を口演した。
三遊亭白鳥「カバライ菌大活躍」
上野動物園で人気者のカバやライオンなどに来園者が祝儀を切ってしまう病気が流行し、それはカバライ菌(過払い金?)が蔓延したためというのが、いかにも白鳥師匠らしい発想だ。人気のないツチブタやカラスバトに悪霊が乗り移り、そのカバライ菌を退治できるという…。
高利貸しの消費者金融に困っているヤスダさんを、ニコニコローンのチョビヒゲの吉田から救うため、飼育員のタナカさんが悪霊を連れて来て、吉田とインディアンポーカーで対決し、見事に悪徳金融を退散させたという。いつもながらの荒唐無稽な白鳥ワールドの高座だった。
柳家喬太郎「鶏もつ煮込み」
今流行っているというコンセプトカフェを土台にしているのが良い。早い話が落語に特化した昔の椀や、ウルトラマン好きが集まった怪獣酒場みたいなものだろうという解釈も喬太郎師匠らしい。居酒屋を開業しては破綻し、また開業しては破綻する主人公に、友人が「何度も女性にふられる寅さんみたい。だったら、男はつらいよをコンセプトにした居酒屋を開店したら」とアドバイス。
御前様、タコ社長、さくら…次々と関連するメニューを繰り出す主人公が愉しい。一番笑ったのは、デザートメニューの黒砂糖。「さとうかじろう(佐藤峨次郎)」って!主人公がずっと思い続けていたマドンナ的存在のメグミに告白しようと考えていた主人公だったが…。やっぱり、寅さんはふられ役がお似合いだ。
春風亭昇太「子供になりたい」
妻というのは子どもが生まれるとそれに夢中で、夫を蔑ろにしてしまう。料理の味付けひとつとっても、カレーライスが甘口になってしまい、夫は憤懣やるかたない。そこで、学校の教師である夫は「これからは自分が子どもになってやる!バブー!」と宣言。
生徒に対しても、「勉強をしたい人は自分で勉強しなさい」「スポーツが得意な人はそれを一生懸命やればいい」を貫き通した結果、生徒に自主性が生まれたというのが面白い。修学旅行の夜、教師たちが集まっての飲み会で、「好きだった昔のアイドル」を言い合うところ、こんな風に教育現場が平和を取り戻せればいいのにと思った。
林家彦いち「いけぬぇ」
何でも合理化で、市町村合併も進み、限界集落はどのように生き残るか。村民たちが真剣に“ゆるキャラ”や“グルメ”について話し合っているんだけど、どうにも現実離れしてしまうところが、逆に愛しい。村民全員の賛同を得られると、「がっぽん、はい!」と掛け声がかかるところも面白い。
取材に来ていた新聞記者が違和感を持って耳を疑うが、村の衆たちはお構いなしに村議会が進行する。猫又の妖怪が現れる件、生贄ならぬ「いけぬぇ」を提供することを大真面目に話し合っているのが、この限界集落の魅力であり、そこは否定してはいけないのだと思う。
「つる子の赤坂の夜は更けて~林家つる子独演会」に行きました。「井戸の茶碗」と「しじみ売り」の二席。
「しじみ売り」は鼠小僧次郎吉ではない型。真打昇進披露の末廣亭初日に掛けたのを聴いて以来だ。口入屋稼業の稲葉屋清五郎の子分の留吉が、蜆売りの長吉を下駄泥棒と間違えたのが発端だ。
清五郎は詫びに蜆をそっくり、二朱で買ってやる。そして、前に流れる川に放して来いと言う。「きょうはおふくろの命日だ。放生会と洒落こもう」。そして、長吉に茶と巻寿司、稲荷寿司を出してやる。すると、長吉は「病気で寝ているおっかさんに食べさせたいから、包んでくれないか」と頼む。聞けば、長吉は十歳。目が見えなくなってしまった母親と暮らしを立てるために、蜆を売っているという。これを聞いた清五郎は「医者に診せろ」と言って、二朱のほかに小判三枚を渡す。
ところが、長吉は「二朱は受け取るが、小判は断る」と言う。「小判が憎いんだ。小判に恨みがあるんだ」。事情を知りたくなった清五郎は話をしてくれと頼むが、長吉は「こんな話は人様にするもんじゃない」と断る。だが、熱心に聞かせてくれと言うので、「湿っぽくなるが」と言いながら話し始めた。
姉が深川で芸者をしていた。田原町の下駄問屋の若旦那が惚れたが、入れあげて勘当になってしまった。二人で小間物屋を始めたが、筋の良くない借金を拵えてしまい、姉は吉原に身売りしようとした。それを聞いた若旦那は「すまない。俺が悪い。死んでお詫びをする」と言うと、姉は「水くさい。私もお伴して死にます」。
去年の二の酉の晩。二人が吾妻橋から身投げしようとするところを、「馬鹿な真似はよせ!」とある旦那が止め、事情を訊くと、20両が入った財布を渡して、「命だけは粗末にするな」と言って去って行った。名前は教えてくれなかった。
その20両で借金を返して、仲良く暮らすようになったが、いいことは続かない。近所の質屋に泥棒が入り、若旦那も「あの20両はどうした?」と問い詰められた。「見ず知らずの人から貰った」と言うだけで、あの旦那に迷惑がかかったらいけないと人相なども言わなかった。だから、若旦那と姉ちゃんは番所から戻っていない。おっかさんは泣き腫らして、目が見えなくなった。
清五郎が「だったら、尚更この三両は受け取れ。誰から貰ったかと訊かれたら、稲葉屋清五郎からと言え。これからも困ったことがあったら、相談に来い。蜆は毎日買ってやる」。これを聞いた長吉は「親方、いい人ですね」と泣く。
清五郎は言う。「冬っていうのは辛いよな。寒くて厳しくて嫌になる。だけど、冬だってそう長くは続かない。必ず春が来る。お前の家にも春の便りが来る。困ったときは必ず来いよ」。長吉は恩に感じて、ペコリと頭を下げ、いつまでも清五郎の方を見つめながら、帰って行った。
留吉が「身投げを助けた男、名前くらい名乗ればいいのに」と言うと、清五郎は「俺はこれから番所に行くよ。20両をやったのは俺なんだ。二の酉の晩、良いことをしてやった、人の命を助けてやったと思っていたが、天狗の鼻をへし折られたよ」。
良かれと思ってした善行が、回り回って迷惑をかけていたとは…。口入稼業の清五郎は実は大泥棒。貧しい者に施しをする、いわゆる義賊だったのだろう。それが鼠小僧かどうかは、この噺では明らかにしていない。ただ、その人情味溢れるつる子師匠の人物造型に痺れた。