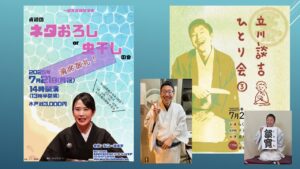桂米朝 なにわ落語青春噺
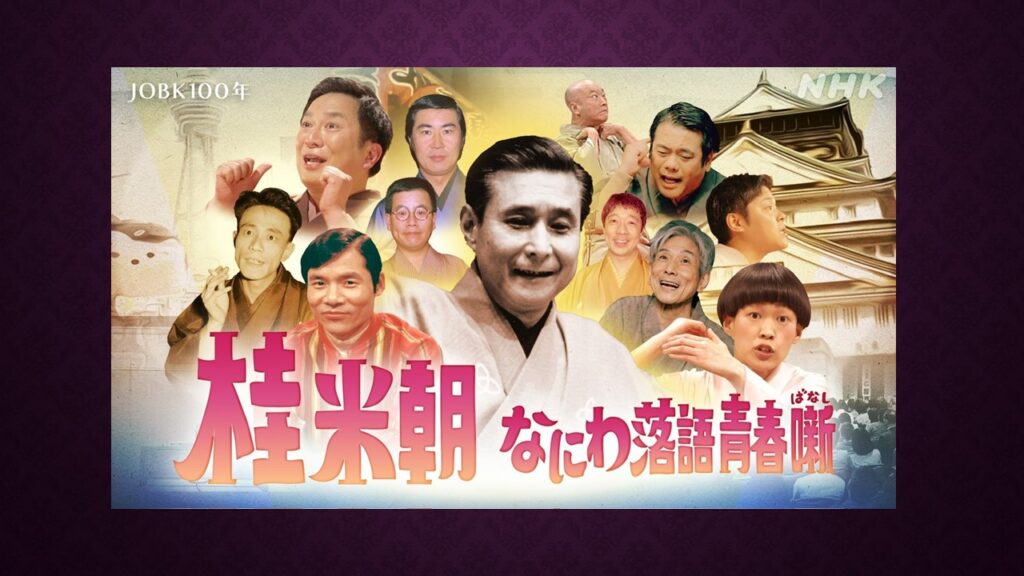
NHKプラスで「JOBK100年 桂米朝 なにわ落語青春噺」を観ました。
桂米朝が生まれたのが大正14年(1925年)、NHK大阪放送局が設立された年である。つまり、米朝師匠とBKは同い年。そんな偶然もあって、この記念番組が制作されて、関西ローカルで放送された。全国放送ではないために、NHKプラスで観たけれど、上方落語のレジェンドであり、人間国宝にもなった米朝師匠の足跡を辿る番組、全国放送されても良かったのになあと思う。(8月2日深夜に総合テレビで全国放送されるそうです)
後に米朝となる中川清少年はラジオで落語を聴くのが楽しみだった。昭和6年にNHK大阪がアンケート調査したところ、人気の番組は①大阪落語②浪花節③ニュース④喜劇⑤野球中継だったという。大阪落語の中でも一番人気は初代桂春団治。清は自宅にあった落語全集を貪り読んだ。
落語を知って私は子ども心に改めて大工さんや植木屋さんの仕事を畏敬の念をもって見直した記憶があります。権威や肩書きや財産などで人間の価値が決まるものではないということなんかは落語で知らず知らずに感得していったのです。
やがて、太平洋戦争がはじまる。清も19歳で召集され、姫路連隊に配属になったが、腎臓炎で陸軍病院に入院。そのときに綴った日記に当時のことが記されている。「ついにたちぎれ線香を一席やってしまう」。入院患者の前で、「くしゃみ講釈」や「蛸芝居」など実に36演目を披露したという。この入院は神様の思し召しだったのかもしれない。
21歳で四代目桂米團治に入門。昭和58年放送の「訪問インタビュー」でこう語っている。笑いの芸でこれぐらい洗練された結構なものはないっていうんですな。落語というものに対する姿勢のようなものを教わった。
終戦後は漫才が人気だった。落語を味わう空気がなく、落語家の中には漫才に転向したり、廃業したりする人もいたという。そして、五代目笑福亭松鶴、二代目桂春団治、そして師匠の米團治も米朝が入門して4年で亡くなってしまう。新聞は「大阪落語は一巻の終わり、滅んだ」と書いた。
そんな米朝にとって大切な存在だったのが、六代目松鶴だ。昭和58年放送の「この人 笑福亭松鶴ショー」で弟子の仁鶴と共演し、「貧乏という地獄を知って初めて芸がわかる」と話している。「らくだ」を得意とする、コテコテの大阪人だ。
そんな松鶴に対し、米朝はスマートだ。深い教養に裏打ちされた芸。昭和57年の「軒づけ」の高座が紹介されたが、5ツの浄瑠璃を見事に演じ分けている。小唄や能狂言に通じ、歌舞伎の舞台にも立ったことがある。
米朝と光鶴(後の松鶴)はライバルとして芸論を戦わせた。松鶴に言わせれば、米朝の落語は「わかりやすくしすぎ。味がない。学校の授業みたいに頭でっかちだ」。米朝は松鶴に対し、「声だけでかくて、客に伝わらない」。それぞれの芸風の違いがわかって興味深い。
当時10人の噺家しかいなかったが、落語復興に奮闘した。米朝は失われていく噺の掘り起こしを熱心にやった。噺を知っている人のところへ出向き、聞き書きをして、足らない部分は自分の創作で補った。その数は40以上。一方、松鶴は落語ができる場所探しに奔走した。漫才に「悔しかったら客を入れてみなはれ」と言われ、キャバレーで立ちの落語をやったが、誰も聞いてくれない。
NHK大阪が動いた。「その灯を消すな」とBK上方落語の会を主催したのだ。必死に集客したが、130の客席を埋めるのは容易ではなかったという。時代は高度経済成長。上方落語協会を設立した。米朝はメディアに積極的に出演し、週6本のレギュラーを持った。売れっ子司会者となると、次第に落語会に客が来るようになった。
昭和45年の大阪万博の2年後、念願の寄席ができる。キリスト教の教会の礼拝堂を借りることができたのだ。名前は島之内寄席。大入り満員となった。戦後のどん底から20年。ようやく芽が出てきたのだ。第一回では松鶴と米朝が口上に並び、今後の支援をお願いした。その14年後の昭和61年、松鶴が病で床に伏した。見舞いに行った米朝に、松鶴は「今後の上方落語はお前に頼むで」と言ったという。
米朝は十八番の「地獄八景亡者戯」を磨いた。昭和42年に東京で初の独演会を開く。「地獄~」には三途の川が汚染されている等の時事ネタを入れた。ちょうど公害対策基本法が制定された時期だ。場所は紀伊國屋ホール。永六輔、小沢昭一、立川談志、安藤鶴夫などがこぞって観に来た。プロデューサーを務めた矢野誠一は「これで全国区になった」と喜んだそうだ。
昭和57年に放送された「なにわの落語家歳末噺」では上方落語のスターが総出演、司会は桂文珍と笑福亭鶴光だ。番組の中で米朝はこう語っている。
芸人になるのは大きな賭けやと思うんです。うまいこといったらよろしいけど、うまいこといかなんだら噺家のなりそこないは釘一本よう打ちまへんな。どないもこないもしょーもないような者なんですね。うまいこといけばよろしいけど、いかなんだらクズみたいなもんですな。
含蓄のある言葉である。京都祇園の安井金毘羅宮で二カ月に一度、桂米朝落語研究会が今も開かれている。59年前に米朝がはじめた勉強会だ。平成14年放送の「NHKスペシャル 桂米朝 最後の大舞台」の映像が紹介された。今は亡き吉朝やざこばの若き姿も映っている。今、この勉強会は弟子の米二が引き継ぎ、主宰している。米二の弟子の二葉が語っている。
落語って、すごい平和な世界。今、やっぱり誰かが失敗したら、みんな責めるでしょ。でも、それを許せるというのかな。しゃーないやっちゃな、アホなやっちゃなっていう、そういう人ばっかり出てくるんです。すごい寛大な世界で、それが落語のすごくいいところやなって思いますわ。
NHK上方落語の会は今も継続されて開催され、来月の会で453回。1400人のBKホールは毎回満員だという。上方落語協会が作った寄席、天満天神繫昌亭の舞台の後ろには、米朝が書いた「楽」という一文字が掲げられている。
上方落語のレジェンド、桂米朝によって切り拓かれた上方落語の文化は確実に実っている。その功績の素晴らしさを再認識した。