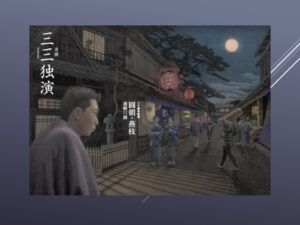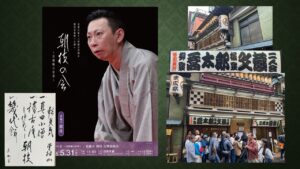講談協会定席 神田あおい「波の伊八」、松柳亭鶴枝真打昇進襲名披露公演「甲府ぃ」

上野広小路亭の講談協会定席に行きました。
「塩原多助一代記」田辺一記/「村井長庵 乞食伊勢屋」宝井琴凌/「怪人二十面相 黄金塔」宝井琴星/中入り/「波の伊八」神田あおい/「江戸のスーパー名君 保科正之」一龍斎貞弥
あおい先生の「波の伊八」が良かった。彫り物師の島村丈右衛門定亮に、安房国の名主の息子だった大助が入門した。入門以前から彫り物をしていて、父親がその才能を見抜いて、定亮に息子の彫った馬などを見せていた。父親が亡くなり、その三回忌を機に入門したのだった。4人の兄弟子がいたが、定亮は大助の腕を認め、名を伊八と改めさせる。
時代は徳川家治の時代、田沼意次が政治の実権を握っていた。師匠の定亮は寺社の欄間など彫り、「仏法者を育てる」ということに熱心だった。しかし、伊八はこの考え方に反発を覚えた。「仏の信仰は庶民のためにある」と考え、自ずと師匠とは違うやり方で彫るようになる。
兄弟子の定兼が「伊八の彫る龍は親方と違うやり方だ」と定亮に苦言を呈した。だが、定亮は伊八の才能を認めており、伸び伸びと育てたいと考えた。遠方からの仕事が舞い込むと、定亮は伊八を呼び、自分の代わりに彫ってくれと頼む。「お前の思う龍を彫れ」。事実上の一本立ちをさせた形だ。そのときに伊八が彫った欄間は今でも杉並の妙法寺にあるそうだ。
独立した伊八の許へ、兄弟子の長次郎が訪ねて来た。親方の娘おかよが寝込んでしまったという。定兼兄さんが親方に「娘さんと結婚したい」と申し出た縁談が元だという。伊八とおかよは幼い頃から好きあっていた。それを他の兄弟子たちも知っているのだ。「お前は親方と違う彫り方をする。そんな奴には娘はやれない。お前は元の彫り方の戻すことはできるか?」。伊八の答えは「できない」だった。「だったら、おかよさんは諦めろ」と言って、長次郎は去った。
おかよは意を決して、父親の定亮に「私には心に決めた人がいる」と言った。それは定兼ではなく、伊八であることは定亮も判っている。「俺のやり方と違う伊八とお前が夫婦になることは世間が許さない」。定亮はきっぱりと言った。おかよは夜になって家を抜け出して嵐の中、伊八の許へ身を寄せた。
翌日、伊八は師匠定亮を訪ね、「おかよさんを私にください」と頭を下げる。定亮は「もらってくれ。だが、お前は俺を裏切った。この家の敷居を二度と跨ぐんじゃないぞ。それがけじめというものだ。おかよを大事にしてやってくれ」。晴れて伊八とおかよは夫婦になった。
伊八は浦賀に仕事に行ったとき、勝川春朗という絵師と出会う。「富士山が綺麗だ。この時と天地と天気が入り混じった美しい瞬間を表現したい」という言葉に感銘を受けた。以後、伊八は一心不乱に彫り物に打ち込み、名人となった。
中井大和守から幕府のお抱え彫り物師にならないかという誘いを受けた。だが、伊八はこれを断る。「人から褒められたくて彫るようでは、良い彫り物はできない。それでは大和守様の顔に泥を塗ることになります」と言って、頑固を貫いた。真の名人とは何か。伊八は行元寺から毎日馬に乗って海を見に出かけ、波を見た。時と天地と天気が入り混じった美しい瞬間を目に焼き付けた。そして出来たのが「波と宝珠」である。この彫り物は葛飾北斎の富嶽三十六景に影響を与えたと言われる。この葛飾北斎こそ、若き日の勝川春朗である。とても良い名人伝を聴いた。
柳亭市童改め松柳亭鶴枝真打昇進襲名披露公演に行きました。
「高砂や」柳亭小燕枝/「道灌」桂宮治/「加賀の千代」春風亭一之輔/「五目講釈」柳家三三/中入り/口上/「七段目」柳亭市馬/「甲府ぃ」松柳亭鶴枝
口上の司会は兄弟子の小燕枝師匠。師匠市馬と会食していたら、「あいつ(鶴枝)、昔はしくじってばかりだったが、いい噺家になったな。俺に似ているんだ」と言っているのを聞いて感動した、と。市馬一門を背負ってほしいと期待していたのが印象的だった。
宮治師匠。研精会で初めて当時の市童さんの高座を観て、「こういうのが落語なんだ…自分はこのままじゃいけない」と思ったそう。そして、市馬師匠の「首提灯」を観て、「芸というのはこうやって継承されていくのか」と合点がいったそうだ。師匠伸治から自分への継承とはまるで違うと比較してしまったと笑いを取った。それはそれで違って良いと思いますけどね。
一之輔師匠。鶴枝は柳家の本寸法の芸。でも、これから先はもっと間口を広げても良いのではないかとアドレス。市馬師匠が高座で歌ったり、三三師匠が古典に入れ事を沢山するようになったりしたように、芸は色々な人の影響を受けて変わっていくものだ、と。かく言う自分もそうだった。周囲の人はそれを見守り、「芸が荒れた」なんて言わないでほしい、寄り道こそ大切だと説いた。御意。
三三師匠。鶴枝が弟子になったとき、「やっと、これという弟子が来たよ」と言うので「良かったですね」と返したら、「歌が好きなんだよ」(笑)。市馬師匠が「三十石」を掛けるとき、袖に鶴枝がいると舟唄を歌う役を任せるようになった。高座の市馬師匠が実に嬉しそうな表情で、鶴枝は師匠孝行だなあと思うと語った。
市馬師匠。談志師匠いわく、囃されたら踊れ。「私より歌うようになりました」と言って、ある昭和歌謡(曲名不詳)の前奏を市馬師匠が口ずさむと、鶴枝師匠は間髪を入れず、高らかに歌い出した。流石である。以前は体格の割りに線が細かったが、この頃は逞しくなったと褒め、「(大の里を横綱にした)二所ノ関親方の気持ちが判る」と笑わせた。
鶴枝師匠の「甲府ぃ」。実直で愛嬌があり、親切で働き者の善吉のキャラクターが鶴枝師匠にとても良く似合っている。両親を亡くし、育ての親になってくれた伯父伯母夫婦に報いるために、江戸で一人前に出世しようと身延山に願掛けして甲府から江戸へ出てきた心意気。仲見世で巾着切りに遭い、おからを食べようとしたことが縁で、豆腐屋夫婦に気に入られ、飯を食わせてもらうばかりか、この店で働けと優しい言葉を掛けてくれるのも、善吉の人徳だろう。
天秤を担いでの荷商い、「豆腐、胡麻入り、がんもどき」の売り声も、鶴枝師匠の良い喉で聴くととても澄んで聴こえる。町のおかみさんたちの人気者になるのもよく判る。だから、三年経って、娘のお花の婿に迎えたいと豆腐屋夫婦が思うのも自然だし、お花自身も顔を赤らめるほど善吉に惚れているというのも、むべなるかな。
この縁談を善吉に持ち掛けるとき、女房が「でも善公が何と言うか」と言うのに対し、そそっかしい親父は「何かお花に不満でもあるのか。三年前の恩を忘れたか」と一人で興奮しているのが可笑しい。善吉は素直に喜び、「恩返しもできないうちに、婿に迎えたいなんて、ありがたいことです。甲府の伯父や伯母もさぞ喜んでくれるかと思います。こちらこそ、よろしくお願い致します」。この謙虚さこそ、この噺の真髄だろう。
祝言を挙げてからも、善吉は働きすぎではないかと気遣う豆腐屋の優しさも良いし、少しは休めという言葉に反応して、善吉が「お暇をもらって、伯父伯母に顔を見て報告したい。また、身延山へ願解きに行きたい」と願い出る了見が素敵だと思う。実直な善吉と鶴枝師匠を重ね合わせた高座だった。