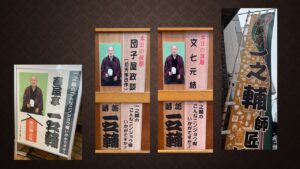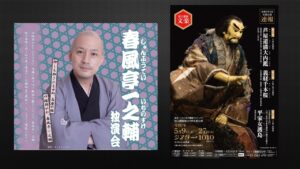兜町かるた亭 天中軒かおり「心の故郷」富士綾那「太刀山と清香」、そして文楽「義経千本桜」
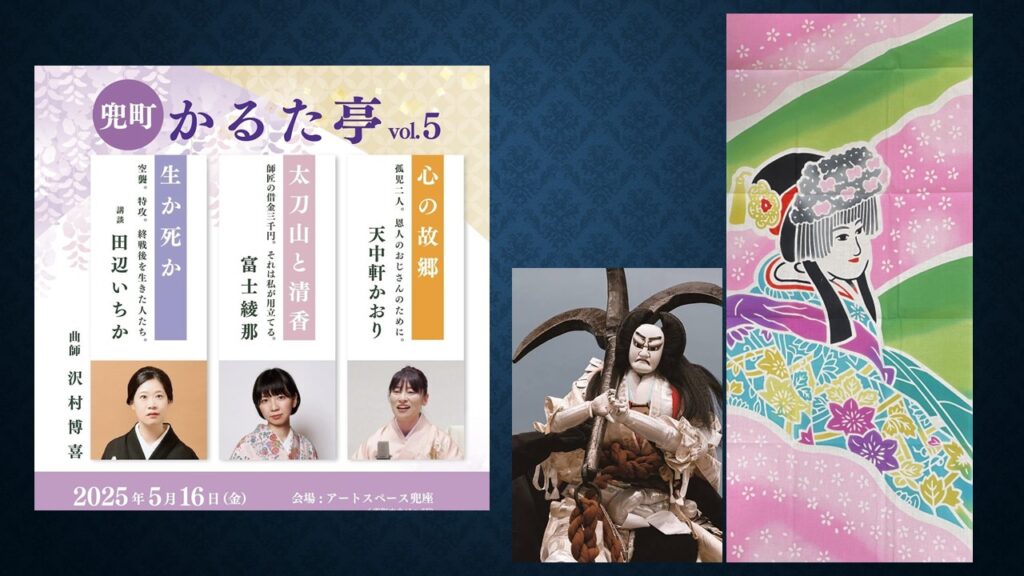
兜町かるた亭に行きました。
「心の故郷」天中軒かおり・沢村博喜/「太刀山と清香」富士綾那・沢村博喜/中入り/「生か死か」田辺いちか
かおりさんの「心の故郷」。木馬亭定席ではかおりさんが前座のために前半または後半しか聴けなかったが、今回フルバージョンで聴けて嬉しかった。当代の雲月先生のために書かれた作品だが、もう雲月先生はお演りにならないそうで、かおりさんに稽古をつけて、「(この作品の)後継者が出来て良かった」と喜んだそうだ。
正一と丑松は孤児院で一緒だったが、院長が悪徳で虐待を受けたために、院を飛び出し、鉄道自殺を図ろうとした。それを小間使いをしていた音蔵が見つけ、命を救い、一緒に孤児院を出た。だが、音蔵は持病の神経痛のために寝込んでしまい、三人は貧乏暮らし。正一と丑松は鍋焼きうどんの屋台を引いて商売を始めたが稼ぎはほんの一握りだ。正一は新聞に自動車事故に遭って500円の賠償金を貰った人がいるという記事を見つけ、本当に自動車に突っ込んだ。
自動車を運転していた酒井哲也が正一を病院に連れて行き、かすり傷程度であることで胸を撫で下ろす。そして、優しい酒井氏に対し、正一は正直に告白する。「許してください。金のために悪いと知りつつ飛び込んだ」。音蔵の神経痛を治す湯治代を捻出するためだったと言う正一に酒井は心打たれる。
音蔵は酒井の計らいで入院した。そのとき、音蔵は酒井に正一と丑松のことを話す。二人は自分の身寄り頼りでもなんでもないが、孤児院院長から救出するために引き取ったこと。だが、自分に稼ぎがないばっかりに二人を不幸のどん底に落としてしまったこと。それが気がかりで夜も眠れない。あつかましいお願いかもしれないが、あの二人を引き受けてくれないだろうか、と。
酒井は二つ返事で引き受けた。丑松は両親を早くに亡くしたことが判っているが、正一は停車場で捨て子として拾われた。手がかりはお守りで、そこには「大正10年7月6日 酒井正一 母朝子」と書かれていて、父のところは名前が消されていたという。「何か深い事情があったのでしょう」と音蔵が言うと、酒井が反応する。
「恥ずかしい話ですが、その父は私です」。10年前、朝子と別れ、今の妻である玲子を財産目当てで娶ったが、家庭は愛のない虚しさだけが残った。「許してください、音蔵さん」。音蔵は正一を呼び、「お前の本当のお父さんは酒井の旦那だよ」と告げた。そして、酒井は正一と丑松の二人を引き取り、養育。二人は幸せに育てられたという…。親子の情愛を感じる高座だった。
綾那さんの「太刀山と清香」。太刀山の師匠友綱は地方巡業で赤字を出し、高利貸しの赤川重助から2000円を借りた。それが利子を含めて2800円に膨らみ、弱っていた。赤川は「次の場所で太刀山が常陸山に負けてくれれば、借金は棒引きにする」と言う。友綱は太刀山に事情を話し、太刀山も承諾した。
だが、その裏では赤川と吉田五右衛門との間で、太刀山―常陸山の取組に1万2000円の賭けをしていたのだった。その事実を知った太刀山は悩む。自分を友綱部屋に入門させ、太刀山という四股名を付けた板垣御前に対し、申し訳が立たない。相撲道に反して八百長をすることはできないと考えたのだ。この話を聞いた柳橋の芸者、清香は「私に任せなさい」と太刀山に言う。
太刀山と友綱親方がいるところに、俥で清香が駆けつける。「ここに3500円あります。2800円は赤川に返済して、残りの700円は祝儀にしてください。私は男嫌いで名の知れる奴芸者、汚れた金ではありません。ある時払いの催促なし。必ず勝ってください」。太刀山は八百長相撲を取らなくて済んだと血の涙を流し、友綱も「出来た!金だ!」と喜んだ。
そして本場所。五日目まで得意の“四十五日”の鉄砲が冴えて全勝を走る太刀山、六日目の相手は常陸山。桟敷席は小切手を片手に勝負に行方を見守る赤川と吉田、そして柳橋の芸者が揃いの着物で総見だ。清香は絹のハンカチを振って応援する。呼び出し、勘太郎。行司は木村庄之助。さあ、勝負は?と盛り上がったところで、高座は終わった。八百長相撲を拒んだ太刀山の陰に芸者清香の功労があったという…。素敵な高座だ。
五月文楽第二部「義経千本桜」を観ました。
伏見稲荷の段/渡海屋・大物浦の段/道行初音旅
船問屋の渡海屋銀平は実は平知盛、女房おりうは実は典侍局、一人娘のお安は実は安徳天皇。知盛たちは船宿一家に身をやつし、帝を守り、義経を討つ機会を狙っていたというのがこの芝居の眼目だ。「銀平」は雨続きで足止めしていた義経一行に良い天気になると嘘をつき、荒天の海に義経を誘い出し、西海に滅んだ「知盛の怨霊」と見せかけて討つ計略だった。
だが、戦況は義経方優勢。知盛家来の入江丹蔵が味方の敗北を報せに戻り、自害する。覚悟を決めた典侍局は「波の下にこそ極楽浄土があり、帝の祖先も平家一族もそこにいる」と帝に入水を促す。局も一緒に行くと聞いて、帝は安心して辞世の句を詠み手を合わせた…。そのときに、それを制止したが義経だった。
深傷を負った知盛が長刀を杖に戻ってくる。義経に対峙しようとする知盛に、「私をこれまで守ってくれたのはお前だが、きょう命を救ってくれたのは義経だから、仇と思ってはいけない」と帝が諫める。典侍局は平家一族より帝が大事と自害。たった一人残された知盛は「帝は実は女の子なのだ」と秘密を明かす。父清盛が権勢欲によって、生まれてきた女の子を男宮と偽り、即位させたのだった。
天照大神を欺いた罰が平家一族に報いとなった。いわば天罰が下った、それゆえ平家一族が滅びるのは必定なのだ…そう知盛は解釈し、「大物浦で義経に戦いを挑んだのは知盛の幽霊だった」と伝えてくれと言い残し、帝を義経に託して渦巻く波間に消えた…。悲壮な最期が印象的である。