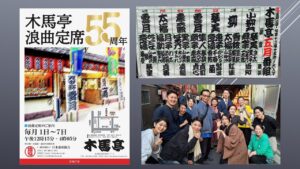擬古典落語の夕べ 立川談吉「だいだらぼっち」古今亭佑輔「鏡」春風亭いっ休「朝顔侍」立川談洲「うざん」春風亭昇羊「おたふく」

配信で「擬古典落語の夕べ」第8回を観ました。
「新婚旅行」鈴々舎美馬/「穴抜け」春風亭昇輔/「中江藤樹」林家彦三/「だいだらぼっち」立川談吉
美馬さん。江戸時代の庶民にも婚礼を挙げた記念に新婚旅行に行きたいという願望があったのではないかという発想は面白い。旅をするのは手形が必要だったが、湯治や寺社参拝が目的だったら許された。女房が薩摩や京都など候補地を挙げるが、亭主が色々と理由をつけて却下し、最終的に江ノ島に行こうということになる。女房が自分の希望を聞いて貰えないと、離縁状を書いてくれ、さもなければ鎌倉の東慶寺に行って離縁するという。また、亭主は一回だけ大山詣りに行ったことがあるというと、女房は「あなたと初めてのことがしたかったのに」と不機嫌になる。これらの要素が一つのストーリーに十分結実していないのが残念だった。
昇輔さん。脱獄王と呼ばれた“穴抜け権次”は自分の体内にあるノミやら金槌やらを肛門を通して自由に出し入れできるという技が肝の創作だ。牢屋の設計図を入手し、壁に穴を空けて用水路を経由して脱獄に成功する。もう一人の男が権次の肛門から体の中に入り、一緒に脱獄できるという発想も奇想天外。でも、それ以上の展開がないため、噺として成立していないのではないかと感じた。
彦三さん。近江聖人と呼ばれ、陽明学を広めた中江藤樹の伝記的要素を随談的に語る前半は落語としていかがなものかと感じた。後半のエピソード的な部分は興味深かった。加賀藩の飛脚が200両を紛失したために切腹して詫びようとしたとき、馬方が忘れ物だと言ってその200両を届けに来た。御礼をしたいと言う飛脚に、馬方は「当たり前のことをしたまで」と拒む。この様子を聞いていた若侍が感心すると、馬方は藤樹の私塾で「正直」の大切さを教えられたと語る。この若侍は後の熊沢蕃山だという…。中江藤樹当人は出てこないが、この後半をきちんと膨らませた方が良いのにと思った。
談吉さん。突出して優れた作品を披露してくれた。猟師の作兵衛の娘おさとと山の守り神のだいだらぼっちの心の交流を描く、ファンタジーな創作だ。きのこが群生している野山に金色に輝く椎茸を見つける。その椎茸を引き抜くと、出てきたのは尻に椎茸が尾のように生えている雄の鹿だった。この鹿を鉄砲で仕留めようと、断崖絶壁にまで追い詰めたが、椎茸がパラシュートのようになって川に落下し、鹿は小舟のように川を下っていってしまった。この情景描写だけでおとぎ話の世界に誘ってくれる。
おさとは崖から落下、気が付くと背後には巨人が立っていた。山の守り神のだいだらぼっちだ。彼がおさとの命を助けてくれた。感謝を示し、言葉を操れないだいだらぼっちと、おさとはコミュニケーションを取りたいと人間の言葉を教える。毎日通い、お互いに情が湧き、だいだらぼっちは日常会話を話せるようになった。
ある日、山が噴火した。村人は避難した。「おらたちの山が燃えている!」と嘆いていたとき、だいだらぼっちが現れ、手で川の水を掬い、山にかけ、噴火は収まった。「だいちゃん、ありがとう!」と、おさとが言う。すると、だいだらぼっちの手が溶岩のようになって、「お別れのときだ」と言う。「俺の役目がわかった。俺はこれから山になる…いつでも会える。来てくれるだろう?また山で会おう」。巨人は山に同化し、山は元通りになった。だいだらぼっちのいた場所の桜が満開となり、ふきのとうがいっぱい採れた。それを食べて、おさとの父の作兵衛は病が治ったという…。ファンタジックでロマンチックな創作落語だ。
配信で「擬古典落語の夕べ」第9回を観ました。
「妖怪根問」三遊亭ごはんつぶ/「鏡」古今亭佑輔/「長屋移籍」春風亭昇咲/「のこった」三遊亭青森
ごはんつぶさん。隠居が詳しく話す河童、輪入道などの妖怪目撃談を、それは見間違いだと論破する八五郎だったが…。ぬらりひょん、主人に成り替わって家に居つく妖怪の話を聞いた八五郎。実は今自分がいるのは自宅で、隠居が主人のように振る舞っていたが、主人は八五郎自身ではないか…ということに気づき、隠居はぬらりひょんだったのか?と思わせる考えオチ。もう一捻りほしいかも。
佑輔さん。素晴らしい。秀作である。醜い顔に生まれしまったおゆうは父親から暴力を受け、自分を産んだ母親を憎む。ある小間物屋に奉公に出たが、そこの夫婦が優しい人で、自分たちに子どもがいないから養子になってくれと言われ、これを受けて愛情いっぱいに育てられた。醜かった顔もいつしか養母に瓜二つの美しさに変わり、隣町の相模屋の若旦那との縁談を受ける。養母は形見に鏡を渡し、これは人の心を映すと教えられた。やがて、養母は亡くなる。
若旦那は「お前のことは昔から知っていた。こんなに美しい妻を迎えられて幸せだ。お前の幸せのためだったら何でもする」と言ってくれる。人を愛すること、そして人に愛されることの喜びを知ったと、鏡=養母に向かって報告をする。だが、女中のおこうがおゆうに対し冷たい態度を取るのが気掛かりだった。すると、使用人の権助から「若旦那とおこうはあやしい仲だ」と知らされる。おゆうは若旦那にそのことを問い詰めると全面的に否定した。
実は若旦那はおゆうが嫁ぐ以前に大旦那が亡くなって落ち込んでいたときに慰めてくれたことがあって、深い仲になったことが一時期あったのだ。おゆうがこの店に来て、おこうは嫉妬した。だが、おこうはそれ以上に悪い女だった。大旦那はおこうに殺されて死んだのだ。そして、若旦那の心も掴み、店を乗っ取ろうと企んでいたのだった。
おこうは悪党の佐平次に「おゆうを汚してくれ」と依頼し、50両を渡す。そして、若旦那が留守のときを狙って佐平次がおゆうを襲い、強姦した。おゆうは若旦那に申し訳ないと思い、離縁を申し出る。だが、若旦那は「綺麗な顔で男をたぶらかすお前が悪い」と言って、離縁を断る。おゆうはおこうの首を絞めて殺す夢を見た。そして、実際におこうは死んでいた。権助は「この店は呪われている」と恐れた。また、おゆうは若旦那に離縁を申し出るが、若旦那は「他に男でも出来たのか。あばずれ!」と言って、おゆうを殴った。
おゆうがいくら心を尽くしてもどうにもならない。鏡を見ると、そこには哀れな女が映っていた。そして、出刃包丁で若旦那の胸を突き刺し、返り血を浴びる夢を見た。鏡には満面の笑みを浮かべた化け物のような顔が映っていた…。佑輔さんが「寝子」に続く素晴らしい怪談を創作した。嬉しい。
昇咲さん。八五郎が江戸を飛び出して、メジャーのロサンゼルス長屋に移籍するという創作。スカウトから一緒にワールドシリーズ制覇を目指そうと誘われたという。メジャーリーグで活躍する大谷翔平に八五郎を重ねる発想だが、二刀流とか、選手補強とか、契約条件とか、専属通訳とか、単なる言葉遊びに過ぎず、噺として成立していないのが残念だった。
青森さん。入門して間もない力士が兄弟子に対し、「自分は横綱になる才能がないとわかった。そこまで頑張る覚悟も持てない」と言って、力士をやめる相談をしているところ。「まだ可能性があると言えるのは、本気を出して稽古していないからではないか」と詰め寄る台詞にちょっとだけ頷いた。小さな村から漁師の父親に勘当されて出てきた太郎左衛門重松後の兼次に現代っ子気質を思う。
この相談を陰で聞いていた親方が、実は太郎左衛門の父親がやって来て、「これは息子の飯代です」と金を置いていこうとしたが、「師匠と弟子は親子同様。飯代なんかいらない。きっと一人前の力士にします」と約束したと打ち明ける。そして、父親が「息子がやめるときに渡してくれ」と言って、その金を預かっているという。
「その父親のために白星を挙げようと思わないのか」という親方の言葉に何も感じず、太郎左衛門は金を受け取りやめてしまった。だが、博奕に手を出してスッカラカンになり、父親に泣きついたら見捨てられ、「親方、あなたは親同然なんですよね」と戻ってくるという…。起承転結がしっかり出来ている作品だと思った。
配信で「擬古典落語の夕べ」第10回を観ました。
「朝顔侍」春風亭いっ休/「正直もの」林家きよ彦/「うざん」立川談洲/「おたふく」春風亭昇羊
いっ休さん。きちんと江戸時代の風俗を研究して創作している姿に好感を持つ。徒士という江戸城警護が職務の下級武士の主人公が内職として朝顔栽培を始めた。珍しい色や形の朝顔ができると大金が得られる。10年かかって、七色の虹のような朝顔が育った。「これは100両はくだらない」と売るように催促する妻に対し、主人公は「可愛い。大事な我が子のようだ。手放したくない」と売るのを拒むというのが面白い。越後屋が100両、細川越中守が200両の値をつけるが売ることはなかった。一カ月して朝顔は萎れてしまった。「父は幸せであったぞ」という言葉が良い。
きよ彦さん。これも良く構成されている。正直者の源兵衛が女房お久の病を治すために、裏山に花を摘みに行くと、崖に滑り落ち、異世界に。ばあさんが出てきて、「村の名産」だという花をくれた。条件として「嘘をつかない」と言い添えて。その花を煎じて飲ませると、お久の病は治った。
異世界から村に帰るときに送り役を勤めてくれたお国という女のことを源兵衛は惚れてしまう。お国に会いたいと思い、村人に病人が出た、怪我人が出た、と小さな嘘を繰り返し、異世界に通っていた。すると、ばあさんが現れ、「約束は守りましたか?」と詰問する。そこには花嫁衣裳を来たお国がいた。思わず抱きしめるとお国は狐の姿になった。「これが私の本当の姿です」。あなたは私と一緒になると言っていた、あなたは小さな嘘を重ねたことで村は大変なことになっていると言う。源兵衛が村に帰ると村人は病人や怪我人だらけになっていたという…。幻想的な優れた創作だと思った。
談洲さん。談洲さんらしい数学的要素を取り入れたユーモアが素晴らしい。八兵衛が一カ月前から「日本一美味しい」と通っている鰻屋は55年の伝統を誇る秘伝のタレが看板だ。だが、主人が店を閉じるという。八兵衛は「そのタレを継がしてもらえないか」と頼む。すると、鰻屋は自分の「半生」を語り出すのが可笑しい。
開店したのは去年だという。天才肌の自分は鰻なんてどうにでもなると思って始めた。修業などしたことがない。天才肌だから。タレは9ツの店から買い取ったものを調合して作った。都合54年のタレに自分の1年を足して55年のタレ。その合算の仕方も、(10+9)÷2=9と1/2、それにXを足した。Xは未知数。55年の二乗とか、√55+Y+Sとか。私は天才肌だから。果たして、この鰻屋主人は平賀源内なのか?と思わせるサゲも良い。
昇羊さん。山本周五郎原作。擬古典の見本のような作品に仕上がっていた。腕の良い職人、貞次郎は酒が過ぎるのが難で、師匠が心配しているが、言う事を聞かない。おかみさんがおしずというおたふく顔だが心の優しい女性に貞次郎との縁談を持ち掛けると、おしずは大層喜んだ。
本所裏長屋で夫婦生活をするうちに、貞次郎は初めて「この女が好きだ」と初めて思うようになった。おしずが妹のおたかのところに行くと言って、風呂敷に包んだものをポロッと落とすと、それは貞次郎が以前に彫った帯留めだった。おたかにあげると言う。おしずが去った後、あれは小網町の鶴村の旦那に彫ったもの…おしずは鶴村に三味線を教えに行っていた。妾になっていたという噂も聞いたことがある…。妙な疑いを持つ。おしずの箪笥を開けて覗くと、他にも幾つもの鶴村の旦那に彫ったものが出てきた。やっぱり…。疑いは膨らむ。
おしずがいないときに、妹のおたかを呼び、真相を問う。確かにおしずは「鶴村の旦那のところに10年ほど世話になった」。年齢にすると二十歳から三十一、二の女盛りの頃だ。貞次郎は「子どもはいたのかい?」と訊く。おたかがなぜそんなことを訊くのかとばかり、「鶴村さんから貰ったものだと思ったのですか」「鶴村さんの女だったと思ったのですか」と言う。
違うのだ。姉さんは自分で御代を払って買ったんです。自分では頼めなかったから…姉さんは貞次郎さんのことがずっと以前から好きだったから…諦められないので、せめて貞次郎さんの拵えたものを身に付けたい…職人の魂が宿っているものを身に付けたら、傍にいる心持ちになれる、そう思って鶴村の旦那に頼んでいたのです。だから、貞次郎さんとの縁談が来たときは、信じられない気持ちで、泣いて喜んだんです。
貞次郎は「妙な勘繰りをして済まなかった。勘弁してくれ」と思ったという…。胸がキュンとなる素敵な高座だった。