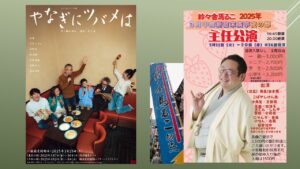こまつ座「フロイス―その死、書き残さず―」、そして古今亭佑輔の会「抜け雀」
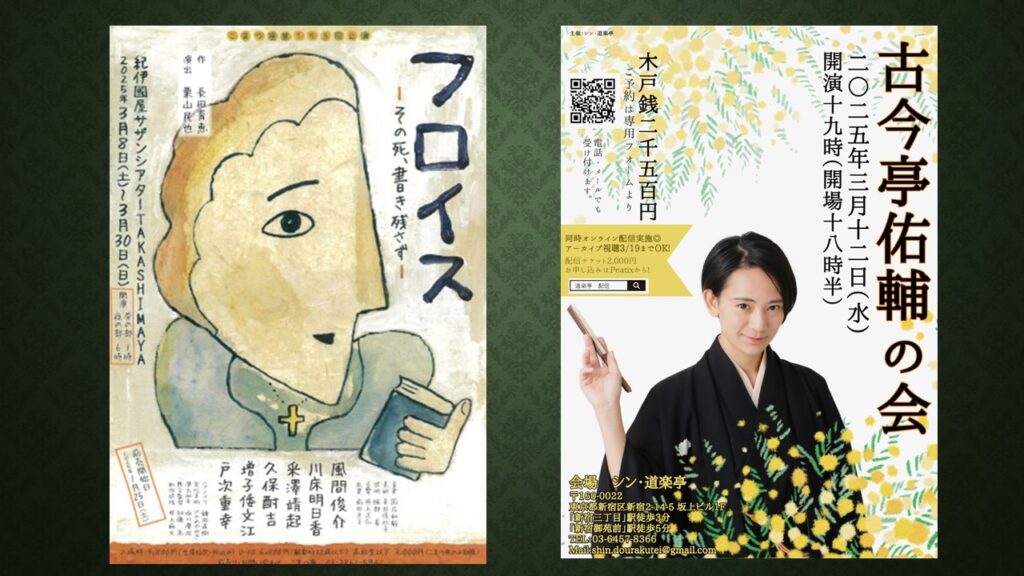
こまつ座公演「フロイス―その死、書き残さず―」を観ました。
井上ひさしは1983年にNHKのラジオドラマ「わが友フロイス」を書いた。リスボンで王室秘書庁の書記見習いをしていた13歳のフロイス少年が、イエズス会に入り、ゴアで司祭になるための勉強をし、31歳で日本にたどり着き、政治状況に翻弄されながら65歳で没するまでを、彼と様々な相手との往復書簡の形式で綴った作品だ。ルイス・フロイスを江守徹、その父アルバレス・フロイスを北村和夫、イエズス会神父オルガンティーノを小沢昭一といった錚々たる面々が演じている。
そして、そのフロイスを題材にした新作を井上ひさしに師事した長田育恵さんが執筆し、栗山民也さんが演出したのが今回のこまつ座公演である。
ルイス・フロイスとは何者か。それを知らないとこの芝居は理解できない。プログラムの中で「ルイス・フロイスの生涯」と題して、歴史学者の渡邊大門氏が書かれたものを基に整理する。
1563年にフロイスはイエズス会から日本に派遣され、肥前横瀬浦(長崎県西海市)に上陸。1568年に織田信長が足利義昭を室町幕府15代将軍にすべく上洛すると、その翌年にフロイスは信長と対面している。信長は大変に好奇心が強く、フロイスの話に熱心に耳を傾けたという。フロイスは布教の許可を得るため、信長の助力を求めた。信長は京都での布教を認め、以降もキリスト教を保護した。大友宗麟や小西行長などの大名をはじめ、一般庶民にもキリスト教の教義を説いた。
また、大きな仕事として「日本史」の執筆がある。ザビエルの来日以降の布教史を、群を抜いて優れた情報収集能力と観察眼で、1549年から1594年の間の事柄を記録し、全3巻にまとめている。「日本史」は戦国武将だけでなく、多くの出来事を書き留めたため、同時代の一級史料として高く評価されているそうだ。
ところが、1587年に天下人で関白の豊臣秀吉が伴天連追放令を発布したので、布教活動がやりにくくなった。1596年、秀吉はフランシスコ会員、イエズス会員、日本人信徒ら26人を捕らえ、翌年、長崎の西坂の丘の上で処刑した。そのことをフロイスが「日本二十六聖人殉教記」として書き記すと、長崎のコレジオでその生涯を閉じた。
今回の芝居はフロイスの布教、そして精力的な「日本史」の執筆が綴られていると同時に、猛烈なキリシタン弾圧によって殉教していった人々の思いが描かれていた。脚本の長田育恵さんはプログラムでこう書いている。
執筆しながら、物語さえあれば死んでいける日本人の宿痾や、二度とこの世に生まれたくないという戦国時代の辛さ、そんな日本人と接し、宗教上の使命との矛盾に苦しむフロイスの姿が浮かんできました。「神はいるのか」―その命題のもと、彼の心には、人間という存在へのどうしようもない愛情と生命の重さが刻印されていたでしょう。以上、抜粋。
ラジオドラマ放送から42年。ガザ地区などは宗教が民族のアイデンティティや暴力の理由になり、分断の要因になっていることは否定できない。今、宗教と人間を問うことの大切さについて思う。
「古今亭佑輔の会」に行きました。「桃太郎」「辰巳の辻占」「抜け雀」の三席。
「抜け雀」。小田原宿の相模屋に七日逗留し、「朝一升、昼一升、晩一升」の酒を飲んでいる男を相模屋女房がそのナリの様子から「ヒョロビリ」と呼んで、「5両の酒代を貰っておいで」と亭主に言いつけると、案の定男は一文無しだった…。「払いたいが、払えない」と堂々としていて、宿屋主人の方より威張っている様子がこの噺の肝だろう。
狩野派の絵師ということで、同じく一文無しだった経師屋が拵えた衝立に雀を五羽描く。一羽一両で五両というわけだ。その雀が雨戸を開けて、朝日を浴びると、衝立から飛び出し、向かいの屋根で餌を啄む。そして、しばらくすると衝立にピタリと戻る。ビックリした主人が女房に報告するが相手にしてもらえないのが、夫婦の力関係を表している。でも、確かに雀が抜け出ることが判り、“雀のお宿”として評判となって、どんどん客が押し寄せ、大久保加賀守がお忍びで訪ねてきて千両の値を付けるという大逆転劇。相模屋主人の感情表現をもっと豊かにすると、この噺の面白さが増すと思った。
そして、“ヒョロビリ”の父親がやって来て、「名人でもなんでもない。情けない。この絵にはぬかりがある。衝立から飛び出すほどの勢いがある雀、そのうちに疲れて死んでしまう」と指摘し、籠と止まり木を描いて、「まだまだ修行が足りないと伝えよ」と言い残し去っていくが、名人とは何かという名人論としても面白い部分だ。志ん朝師匠の言うところの「上手はいくらでもいるが、名人というのはなかなか出るものではない」という言葉に通じるものを感じる。そして、この衝立は大久保加賀守が二千両と値を上げる。
偉いのは、相模屋主人が千両になっても、二千両になっても、“ヒョロビリ”が「類焼は致し方ないが、俺が戻ってくるまで売ってはならない」と言っていた約束をきちんと守っていたことだ。最終的に“ヒョロビリ”が再び現れ、「正直な奴だな。お前にやるぞ」と言ってくれた。親切を旨として営業している相模屋さんが最後に報われるところが好きだ。