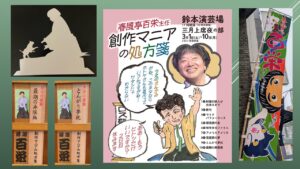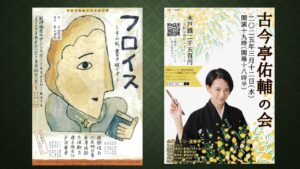劇団青年座「Lovely wife」、そして新作前線 立川談洲「かんたあびれ」

劇団青年座創立70周年記念公演「Lovely wife」を観ました。作・演出:根本宗子。
とても良い芝居だった。当たり前のことかもしれないが、それぞれの夫婦にそれぞれの形があり、100組の夫婦がいたら、100通りの幸せがあるのだということを教えてくれたような気がする。岩松了演じる売れっ子小説家・坂東晋太郎と結婚した、高畑淳子演じる編集者・秋江は晋太郎が次々と若い編集者と浮気をするのを見て見ぬふりをして、家事、子育て、そして出版社の仕事を頑張ってきた。晋太郎には晋太郎の生き方があり、秋江には秋江の信念があって、何とか離婚もせずに夫婦を続けてきたのは、他人には測ることの出来ない二人の間に流れる“何か”があったからではないかと僕は勝手に思った。
根本宗子さんはプログラムのインタビューの中でこう語っている。
「高畑淳子さんと岩松了さんの夫婦の話」ということは一番最初から決めていました。おふたりが夫婦だったら面白いと思いましたし、岩松さんはずっと夫婦や、家庭の物語を多く描いている作家さんだと私は思っているので、岩松さんにホンを書くなら夫婦の話にしたかった。でも、関係が良好な夫婦は思い浮かばなかったんです。自分の親もそうですけど、夫婦ってだんだん喧嘩もしなくなっていくじゃないですか。自分の台本の熱量はいつも高いので、書いたことのない「空気みたいになってる関係性」を描いてみたいなと。(以上、抜粋)
今回、岩松さんと高畑さんが演じている夫婦の形というのは決して特殊とか、稀とかということはなく、「どこかにいるかもしれない夫婦」の形のような気がした。そして、二人の間には過去に色々あったし、今も一筋縄ではいかない感情もある。だけど、それらを含めてお互いが分かりあえていれば、それは「幸せ」な形じゃないかと思った。
僕の父は92歳、母は88歳と存命で、お互いを慮って暮らしているのがよくわかる。今、老いた両親の手助けをしながら感じることは、60年以上夫婦をやってきて色々なことがあったけど、「今ここにある幸せ」を大事にしながら生きている素晴らしさだ。この二人にしかない唯一無二の夫婦の形なのだと思う。
35歳の根本宗子さんがインタビューで語っていることに激しく共感した。
上の世代をテーマにすることって、これから自分の年齢が上がっていけば書く機会があるでしょうけど、今は若い女の子が真ん中にいる話をお仕事としてもいただきやすいので、自分から見た親世代の人たちの気持ちを描くのは、これまでやったことがないことかもしれないです。私は50代、60代をまだ過ごしてないので、その世代の人たちが何を考えているか、リアルにはわからないじゃないですか。だからこそ、もも(晋太郎と秋江の娘)という存在を入れて、娘から見た上の世代の人たちがどんなふうに見えているかを、漫画みたいに見せたいと思っていて。舞台の美術も一筆書きみたいなセットにして、リアルとファンタジーのはざま、という感じの世界観にまとめられたらいいなと思っています。(以上、抜粋)
そうなのだ。親の世代の本当の気持ちは正確にはわからない。だけど、こんな風に考えているのかな、と察することはできる。それを根本さんはファンタジーと表現しているわけだが、そういう想像力を膨らませることが大切なのかな、と僕は思った。「思いやり」という言葉では簡単には済ませることのできない、何かを探って僕も生きていきたいと思った。
「新作前線」に行きました。
「マッチングアプリ」鈴々舎美馬/「かんたあびれ」立川談洲/中入り/「大罪」春風亭昇咲/「お菓子の伝言」柳家花いち
美馬さん、すっかり自信作に仕上げている。運命をまちわびている主人公に声を掛ける男たちのバリエーションが面白い。高校球児の涙に涙しているチアガールの動画を見るのが好きな男、大根の桂剝きをクラブで披露してくれるのを楽しみにしている軽いノリの男、スリーピースでイケメンなのにお互いノーパンで集合しようと約束した奇妙な性癖の男…。主人公が幻滅しているところに、現れた警察官が運命の男性かと思ったが…という構成も巧みだ。
談洲さん、創作のセンスが抜群だ。長屋にピアノがやって来ると聞いたが、ピアノとは何かを知らない者ばかり、「食い物?生き物?」と騒いでいると、与太郎だけが「ピアノの音は人の心を動かしてくれるんだ」と知っていて、「おいら、弾いてくる」。長崎にいたことがあり、ピアノを嗜むという与太郎の意外な一面が見えるのが良い。
大家と八五郎が店賃を払え、払えないで喧嘩になり、「くそったれ!」「しみったれ!」と言い合っている最中に与太郎のピアノ演奏の音が聞こえると、両者は「俺が間違っていた」「私の方こそ意地になっていた。払えるときに払えばいい」となり、血の繋がりはないが、長屋という絆で繋がった家族のようなものと心穏やかになるのが可笑しい。
「お茶を淹れてくれ、ばあさん」「わたしはばあさんじゃない。ちゃんと絹江という名前がある」「つべこべ言わずに茶を淹れろ」「わたしは飯盛り女じゃない」と夫婦の喧嘩が始まるが、与太郎のピアノの演奏が聞こえると、両者は「お絹ちゃん、一緒にいるのが当たり前と考えていた俺が悪かった」「いいんですよ、わかってくれれば、徳ちゃん」「今度ふたりでどこか温泉にでも出かけよう、お絹ちゃん」となり、和解する。とても癒されるピアノ演奏を絶妙なタイミングで挿入し、音楽の力ってすごいなあと観客に思わせる構成力、演出力に脱帽だ。
昇咲さんは落語会で守ってほしいマナーを喚起する創作。落語会の会場に向かう春風亭昇咲が道に迷って、江戸時代にタイムスリップしてしまう。すると、大悪党が処刑されるのを見ようと黒山の人だかり。その大悪党が犯した罪は落語会で携帯電話を鳴らしてしまったことだという…。その他にも過去には、演者の評価を点数に付けてメモする人、オチの前に先にオチを言っちゃう人、新作と判った瞬間に目を閉じて寝てしまう人などが処刑されたという。この後に新たな展開がほしいところだ。
花いち師匠は自分の好きなお菓子にこじつけた教訓みたいなものを並べたオムニバス。みきちゃんはタロウ君とユウジ君の二人から告白されて迷っているので、菓子屋のおばあちゃんがオレオで占えばいいという。真ん中から割って、クリームが多く付いている方を選びなさい。また、人生は柿ピーのようなものと言って、柿の種が7割、ピーナッツが3割入っているが、人生で辛いことが7割、楽しいことが3割、ピーナッツばかり食べていては駄目ですよ、と。
ジュン君には、たけのこの里ときのこの山を混ぜてしまって、どっちを掴むか、ドキドキしなさい。人生はこのときめきが大切だと教える。タケル君には、ヨックモックの空洞から夢という字を覗かせ、「よく見えない」と答えると「それが大人の視界」だと教え、だから子どもはそんなことはしないで夢を諦めないことが大事と教える。面白い発想だが、ストーリー性に欠けるのが惜しい。