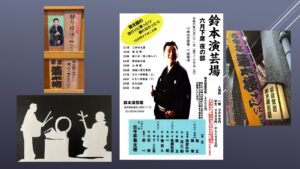立川談春独演会「妾馬」、そして田辺いちかの挑戦「黄泉から」
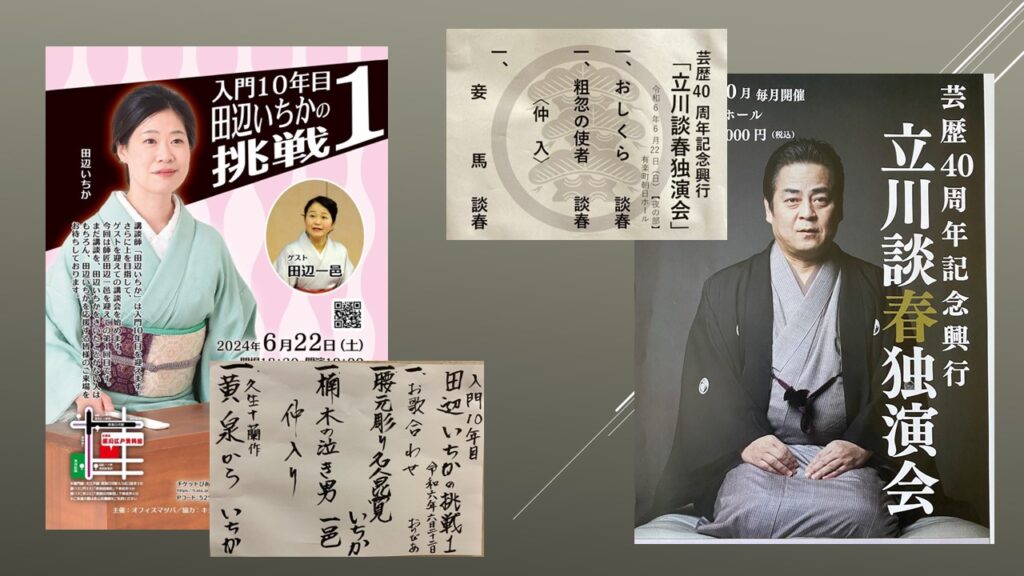
立川談春独演会に行きました。芸歴40周年の20回シリーズの第12回。「おしくら」「粗忽の使者」「妾馬」の三席だった。
「妾馬」。八五郎を大家が呼び出し、紋付を着させて、「妹のおつるが“お世取り”を産んだ」と聞かされて、八五郎は「おつるがフクロウを産んだので、肩に載せて親の因果が子に報い…と見世物小屋で口上を俺がやるんだ」という冒頭から笑い沢山の噺にしているのが良いなあ。褒美として50両は貰えるだろうと言われ、それじゃあ申し訳ないから佃煮屋の椎茸昆布を手土産に買うから200文貸してくれと頼むなど、身分の違いにあえて無頓着な八五郎が好きだ。
その紋服の晴れ姿を母親に見せて、おつるが男子出生したことを報告すれば親孝行になるし、喜ぶだろうと言われ、八五郎が自宅に戻ると母親は意外な反応。お前みたいな人間の出来損ないに嫁が来るのは諦めた、だから孫の顔も見られない、おつるは身分が違うから生涯会えない、せめてお前が孫の顔を見てきて、「幸せそうだった」と教えてくれればいいと泣きじゃくる。
八五郎は漢気のある奴だ。会わせてやるよ!殿様に話をしてやる。だいたい、この話はおかしいんだ。勝手におつるを召し抱えて、男の子が生まれたからって呼び出して。殿様は俺の舎弟だろ?本当だったら、向こうの方から手土産持って挨拶にくるのが筋じゃないのか!?身分制度の厳しい時代だったのだろうが、理屈で言えば、八五郎の言っていることの方が正しくないか。
八五郎が赤井御門守の屋敷を訪ね、酒や馳走で歓待され、すっかり酔っ払った八五郎は上機嫌だ。殿様の隣におつるを見つけ、「おつるか!つるっぺ!あんちゃんだよ!見せろ、お世取り!…目元はお前そっくりだ。口元は殿様似だな。器量がいいな。お産は辛くなかったか?」。
この後、八五郎が「言いたいことがある」と言ってはじまった弁舌が良い。お前は暫く苛められる。女は人の幸せが大嫌いなんだ。我慢しなくちゃいけない。頭を下げて、お陰様でございます、ありがとうございますと言っていろ。お前は悪くないけど、人というのはそういうものだ。実るほど…稲穂かな、だ。間に何かあるけど。ご老女のおばあちゃん、天狗になっているなと思ったら、遠慮なく注意してやってくれ。皆さん、よろしくお願い致します。
おつるが「あんちゃんが稲穂かなで生きていたら良かったのにね」と言うと…。人に可愛がられた方がいいのは判っている、若い頃はキャンキャン吠えて噛みついた、でも周りの大人がよくしてくれた、今度は俺が噛みつかれる番だ、人間が丸くなることができないんだ、人には嫌われない方がいいのはよく判っているんだけどね。八五郎には、八五郎の人生訓があるのだろう。
母親の話になる。おふくろは達者だよ。だけど、年取ったね。泣いてやんの。孫の顔が見られない、身分が違う…って。殿様、折り入ってお願いがあります。一目でいいから、おふくろにおつるやお世取りに会わせてやってくれませんか。こんな立派なところじゃなくていい、廊下ですれ違うだけでいい。喜ばしてやりたい。兄貴、ありがとうと言わせてみたい。オモクモクは要りませんから…。会わしてくれる?いい話だね!
三太夫や女中たちがこれを聞いて泣いている。湿っぽくなっちゃったね。あんちゃん、人情噺やっちゃった?じゃあ、陽気に唄でも歌うか!このガサツだけど、人情味ある八五郎の性格を殿様がすっかり気に入るのもよく判る。士分に取り立てるのもよく判る。でもって、この八五郎が後の「粗忽の使者」の地武太治部右衛門という…。談春師匠らしい演出が愉しい高座だった。
夜は清澄白河に移動して、「入門10年目 田辺いちかの挑戦1」に行きました。「腰元彫り名人昆寛」と「黄泉から」の二席。ゲストは師匠の田辺一邑先生で「太平記 楠木の泣き男」、開口一番は神田おりびあさんで「柳沢昇進録 お歌合わせ」だった。
「名人昆寛」。値は高く、仕事は遅く、注文中は催促なし。名人気質をよく表している“看板”だ。あるとき屋根職人の話し声「コン、カン、コン、カン。狐が鉦を鳴らしているみたいだ」が聞こえてきたのをヒントにして、町の子どもたちにたらふくご馳走して、王子稲荷で火消装束で行進させ、汐留で潮干狩りをさせ、その様子をスケッチして、それを参考に小柄に狐が遊ぶ姿の彫り物をしたというのが面白い。
紀州公の注文は金無垢の小柄だったので、銅に彫った細工に対して、尾張屋は見る目がなくて二分しか出さなかった。魂をこめて彫ったのにと昆寛は不思議に思うが、女房のおかじは「道楽で彫っているんじゃ駄目だ」と言うと、昆寛はおかじに三下り半を渡して追い出してしまう。昆寛が天才なのに対し、尾張屋やおかじは普通の価値観を持った常識人だったので、こういう悲劇が生まれてしまうのだろう。
だが、目利きの金兵衛さんがこの小柄の細工を見たら、恐ろしく感動して、「ここ10年で一番の名品だ。200両出す。いや、300両…500両」。ついには800両という値がついた。紀州公も大満足。尾張屋の気遣いで内助の功のおかじはすぐに復縁して、ハッピーエンドという…。名人というのは誤解されやすいが、物事を表面的でなく、奥底まで見抜くことが大切だと教えてくれる。
「黄泉から」は久生十蘭先生の短編小説をいちかさんが前座時代に講談にしたもので、何回か掛けて磨いてきた作品だとのこと。「10年目の挑戦」に相応しい、聴き応えのある読み物だった。
舞台は終戦直後だ。美術仲買人の魚返光太郎が新橋駅のホームで昔お世話になった老紳士、フランス文学の講師のルダンさんと再会する。手に花束を持っているので問うと、「お盆なので、墓参り」だという。「誰の墓参りか」を問うと、「この戦争で弟子が18人全員戦死した」。この戦争が終ったら、パンケエ(大宴会)をしよう!と約束していた。そのパンケエを新盆の今夜開くので、招待して歩いているのだ。
光太郎が「従妹のおけいも招くのですか?」と訊くと、「彼女は婦人軍属でニューギニアで戦死した。遺骨がまだ向こうにあるから、来られるかどうか」。「お前さんはおけいさんに8年間も手紙を出さなかったそうだな。彼女は君のことが好きだった。だが、子ども扱いされていると嘆いていた。雪の日に私のところへ来て、光太郎さんを諦めて、誰かと結婚してもらって、早く楽になりたいと言っていた。お嫁さんには自分の友人で良い人を推薦するとまで言っていた」。
光太郎が神田に出ると、ここも雑踏でにぎわっている。戦争で300万人が死んだというのに、このお盆で追悼する空気もない。光太郎はきょうの仕事を全てキャンセルし、自宅でおけいを追憶しようと考えた。祖母のおきぬは昔ながらの本式のお盆の支度をする人だったが、詳細を覚えていない。自己流ですることにして、甘口のリキュール、キャンディ、ショコラ、マロングラッセ等を用意し、本机の上に並べたが、どうもしっくりこない。おけいの写真を探したが、見当たらなかった。
俺に人間らしい優しさがあったなら、おけいをパリに呼び寄せて、そうしたらニューギニアに行くようなこともなかったろうし、自分の冷酷さのためにかけがいのないたった一人の肉親を失ってしまった…。おけいに最後に会ったのは、夏の宵。祖母がおけいのために遺した琴爪を受け取りに来たときだった。「きょう貰っておかないと、二度と手にできないかもしれない」と言っていたのを覚えている。
二十一、二の若い女性が訪ねてきた。品の良い見知らぬお嬢さんだった。「元銀座にいらした魚返さんですよね?今屋の伊草千代と申します…ニューギニアから戻ってきたもので、おけいさんの話が出来たらと思いまして」。千代が話し始める。
おけいさんと出会ったのは終戦の半年前でした。カイマナという地でした。雨季が明けると湿度が上がり、タイプライターの調子が悪くなって、軍の作戦文書を何度も打ち直さなければならなくて、命を削るような日々でした。宿舎に帰ると、皆は疲れているのに、おけいさんは習字をしたり、琴を弾いたりしていました。おけいさんが琴爪を持っていることを知った衛生兵が元琴師で、ジャングルの木を使って琴を作ってくれたのです。密林から琴の音色が響き渡り、美しかった。
その頃、おけいさんはもう容態が悪くて、雨に濡れて、喀血し、危篤になる危険な状態でした。私がお別れに彼女のベッドに行くと、彼女は「夢を見ていたの。面白かった。今、パリに行ってきたの。光太郎さんが煙草を吸いながら、石畳の道を歩いていたわ」。いつのことですか?と光太郎が千代に訊くと、「6月27日です」。
部隊長が「ご苦労だった。気の毒なことをした。最後に何か望みはありますか?」と訊いたら、おけいさんは「雪を見せて頂きたい」。部隊長が困った顔をすると、「冗談です。でも、内地を立つ前の晩に綺麗な雪が降っていたんです」と答えたんです。軍医長が部隊長に耳打ちをして、おけいさんを担架に乗せて、林の谷間の川に連れて行った。すると、空から真っ白な雪が舞い降りて、辺り一面が白く染まったんです。「見てごらん、雪だよ」。すると、おけいさんは「美しいこと…」と言って、眠るように息を引き取りました。この土地では雨季が明けると、沢へ幾億幾千万のカゲロウの大群が集まるんだそうです。それだったのです。
光太郎がどうしてこの家が判ったのか?と尋ねると、千代は道に迷ってしまい、知らないうちに偶然、「魚返」という表札を見つけたのだと説明し、はにかんだ。光太郎は「おけいが推薦する友人を連れてきたのではないか」と思った。
そして、近所のルダンさんの家の照明が点き、ピアノの音が鳴り、パンケエが始まったことが判ると、光太郎は「おけいもあそこに行くんだな」と思い、女中に提灯を用意させ、ルダン宅に向かった。後ろを振り返り、「ここは穴ぼこになっている。手を引いてやろう」。そう言って、光太郎は歩を進めた。
戦争という悲劇とちょっとした気持ちのすれ違いで光太郎とおけいは結ばれることはなかった。だが、おけいの魂はずっと光太郎の傍を離れないでいてほしい。そう願わずにはいられない、素敵な読み物だった。