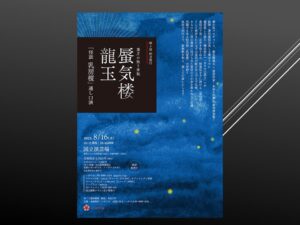玉川奈々福「瞼の母」、そして立川吉笑 真打トライアル vol.2

「奈々福・太福の浪曲浮かれナイト~清き流れの玉川姉弟会」に行きました。玉川太福先生は「任侠流れの豚次伝」第9話の「人生鳴門劇場」。玉川奈々福先生は長谷川伸先生の「瞼の母」をうなった。
「瞼の母」は名作だ。生き別れた母と息子がお互いを思う気持ちが十分にありながら、諸事情によって表向き喜べない、というか親子であることすら認められないことの切なさといったらない。
今は柳橋の料理屋「水熊」を切り盛りする女将であるおはま。そこに突然現れた江州番場宿の旅籠の息子だったと名乗る男が「私くらいの歳の男のお子さんを産んだ覚えはありませんか?忠太郎でござんす」と問われ…。息子とは5歳のときに別れた、9歳のときに亡くなったと聞いたと知らぬふりを通さなければいけない“母親”おはまの辛さに思いを馳せる。
この料理屋の身代欲しさに騙っているのではないか。私はあなたのようなヤクザ者を産んだ覚えはありません。目の前の男がお腹を痛めて産んだ実の息子と判っていても、新しい夫と再婚して可愛い娘もいるという現在の立場上、忠太郎の存在を受け入れることができない。心を鬼にするというのはこのことだろう。
その母の気持ちが判るだけに、忠太郎も最後には諦めて、立ち去る。旅をしながら探し求めていた実の母を、ようやく見つけることができたにも拘わらず、手も握ることすらできずに引き返さなければいけないのは、さぞかし無念だったろう。だが、母を恋しく思えばこそ、ここは息子として了見することが最大の親孝行と考えたのかもしれない。
母おはまと義理の妹お登勢が後を追いかけてきても、もう未練など残さずに、潔く去る男らしさに心が震える。上と下の瞼を合わせれば、昔のおっかさんの面影が浮かぶ。会いたくなったら、目を瞑ればいい。忠太郎の最後の言葉が印象的だった。
「立川吉笑 真打トライアル」vol.2に行きました。第1回の志の輔師匠に続き、第2回のゲストは春風亭昇太師匠。吉笑さんの師匠・談笑(当時は談生さん)の真打トライアルが19年前に銀座ガスホールで5回行われているが、そのときも志の輔師匠と昇太師匠はゲスト出演している。ちなみにそのときは、他に小朝師匠、鶴瓶師匠、そして最終回に談志師匠というラインナップだったそうだ。
「小人十九」立川吉笑/「マサコ」春風亭昇太/中入り/「イラサリマケー」立川談笑/「落語家」立川吉笑
今回のプログラムの「ご挨拶」で吉笑さんは、「12年半の落語家人生におけるターニングポイント」の一つとして、2017年春に結成したソーゾーシーの存在を挙げている。瀧川鯉八師匠、春風亭昇々師匠、玉川太福先生、そして吉笑さんの4人だ。こう書いている。
閉鎖的になりがちな立川流にいながら 前を向いてワクワクすることばかり考えられたのは いつも心地良い風が吹いているソーゾーシーのおかげだ。
いまだに「新作なんか落語じゃない」みたいなことが言われることがあるが、「僕たちが伸び伸びと活動できる」のは、新作落語の地平を切り拓いた圓丈師匠、そしてそれに続く「昇太師匠を含めたSWAの皆さん」が新作の土壌を作ってくれたおかげだと感謝の言葉を述べている。
今回、この真打トライアルのゲストに昇太師匠をお願いしたときのことを、吉笑さんはプログラムにこう書いている。
「ネタ下ろしの邪魔をしちゃいけない」と、これまで一度も伺ったことのなかったSWAの楽屋へ、今回のゲスト出演をお願いするために初めてお邪魔しました。そこでは、これだけの実績を残されている師匠方が「次はこんなことやってみない?」と前向きに未来の話ばかりをされていて、そのほとばしるモチベーションの高さに、まだまだトップランナーであり続けられるのだなぁと愕然としました。以上、抜粋。
今回、吉笑さんの「落語家」を初めて聴いた。近未来、落語は落語家というロボットの中に何人もの人間が入って操縦する演芸になるという見立てにハッとさせられた。特に手の動きを担当することになった新人が、なかなか羽織紐を解けなくて、羽織が脱げず、噺の本編に入れないところ、大いに笑った。そして、この噺を通して、落語という芸能は、いくら伝統芸能とか、古典芸能とか言っても、結局は今現在生きている人間の息遣いを伝えるものであって、それはロボットに替わり得るものではないことを示している。そこに吉笑さんの落語センスの素晴らしさが凝縮している気がした。
「ご挨拶」の最後に、吉笑さんはこう書き記している。
「これからの時代は僕たちに任せてください」と、そろそろ新作のバトンを受け取らなきゃと思うけど、いまだに創作を止めないSWAの背中は相変わらずずっと先にあって、それは悔しいことだけど、頼もしくもあったり。以上、抜粋。
そうなのだ。還暦を過ぎた噺家も、若手真打と言われる噺家も、そして二ツ目で意欲的に活動する噺家も、みーんな同じ走路を走っているランナーで、新しく生み出される新作落語に先輩も後輩もないんだ。その高座が面白いか否か、にベテランも若手もないのだ。皆が競い合って、聴き手である私たちを楽しませてほしいと願うばかりです。