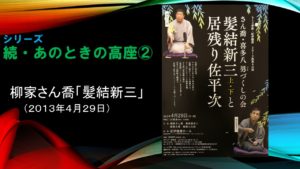【続・あのときの高座】③柳家喬太郎「横浜開港150周年記念落語」(2009年6月27日)
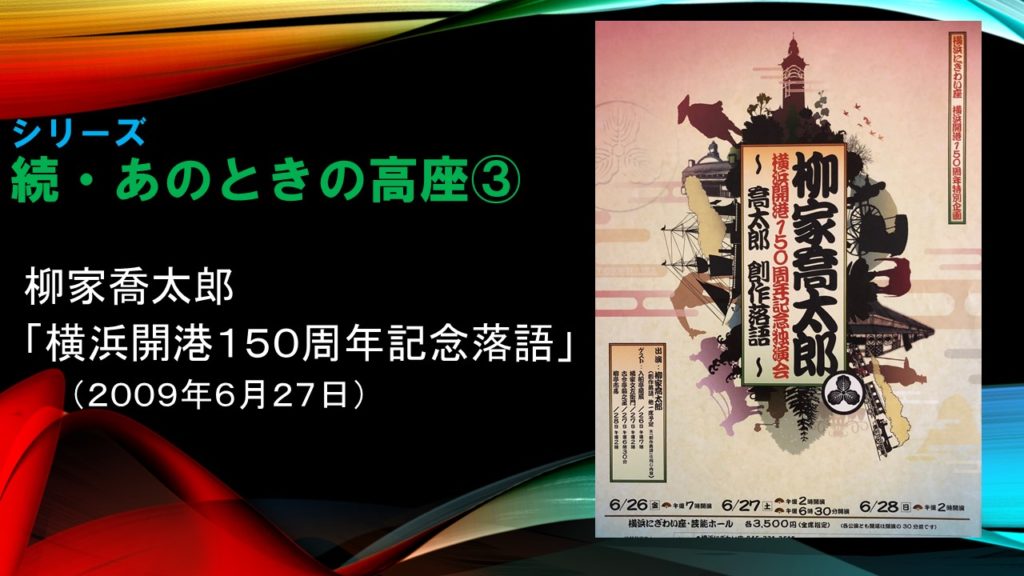
おとといから、過去に印象に残った高座をプレイバックしています。きょうは2009年6月27日。「横浜開港150周年記念 柳家喬太郎独演会」@横浜にぎわい座からです。なお、このときネタおろしされた創作落語は「横浜開港150周年記念落語」ということで、特別な演目名は発表されていませんでしたが、去年(2019年)の「きょんスズ30」で10年ぶりに演じられたときには、「純情日記 港崎(みよさき)編」となっていました。以下、当時の日記から。
喬太郎師匠は天才である。古典では、「牡丹燈籠」「文七元結」「おせつ徳三郎」といった本格的な噺を圧倒的な話芸で観客の心を奪うかと思うと、「綿医者」「橋の婚礼」「擬宝珠」、そして先日の「吉田御殿」のような誰も演り手のいない珍品を掘り起こし、見事なまでに蘇らせる。かと思えば、新作の分野でも、「一日署長」や「彫師マリリン」のような笑い沢山の噺で爆笑を取るかと思うと、「ハワイの雪」や「孫帰る」といったホロリとした作品で涙を誘うこともできる。実に守備範囲が広く、なおかつ、その芸ひとつひとつにぬかりがなく、深い。
そしてまた、ここに新たな伝説が生まれた。横浜開港150周年を記念して口演された創作落語である。なんでも、横浜にぎわい座が1年前に依頼したそうだが、喬太郎師匠はその期待に十分に応える噺をこしらえ、そして熱演した。開港当時に横浜にあった港崎(みよさき)遊郭を舞台にした悲恋物語をドラマチックに描きながら、一方で「純情日記横浜編」の主人公のその後を登場させて、その2つを上手に絡ませながら、展開する感動巨編。いやぁ、実に素晴らしい。喬太郎という噺家の才能に改めて、惚れ直した独演会だった。
柳家喬太郎「横浜開港150周年記念創作落語」
横浜で生糸輸出業で繁盛していた中居屋十兵衛は、桜田門外の変の大老殺しに絡んでいるのでは?という嫌疑をかけられ、行方不明になる。中居屋に奉公していた卯之吉は、職を失い、口入れ屋に行くが、中居屋にいたということで、「いつ火の粉が手前どもにかかるかわからない。他を当たってもらえますか?」と断られ、働き口が見つからなくて困っていた。そんな時、中居屋に出入りしていた店の娘であるお松に、道端でばったりと会う。なんでも、父親が借金を抱えて首が回らなくなり、三味線が弾けることを生かして、芸者になるのだという。「これで会えなくなりますね」と言う卯之吉に、お松は「お座敷に呼んでくれれば会えますよ」と明るく返す。「別に、女郎になったわけではないから・・・」とニコリと笑うお松の笑顔が可愛く見える。
舞台は変わって、現代の横浜。後輩のサラリーマン(34)が、先輩サラリーマン(46)に相談に乗ってほしいと頼んだ。二人は馬車道から横浜スタジアムを通って、横浜公園へ。「この銅像、知っているか?プラントンという外人だ。この公園を作った人だよ。昔、ここは廓だった。『岩亀楼(がんきろう)』なんて遊女屋があったんだ。色々な男と女が物語を紡いだ・・・」。
再び、舞台は明治の横浜。港崎(みよさき)遊郭は、外国人の接待をする場所になっていた。卯之吉の案内でやってきたイギリスのククレバーモンド商会の李王竜(リー・ワンロン)は、芸者となったお松、千代丸の三味線と歌に聞き惚れた。そして、千代丸を気に入った。「素晴らしい。美しい」。しかし、卯之吉はそのことを良く思っていなかった。「豚鉄」という、昔は講釈師だった鉄五郎がやっている豚屋で卯之吉はこぼす。「冗談じゃないよ。四足食っている人間が日本のことがわかるか?」。鉄五郎が諭す。「時代が変わったんだよ」。それでも、卯之吉は「嫌なときにでも、座敷でニコニコして、顔を作れる芸人」に不満を持っていた。すっかり千代丸を気に入った李は、「岡惚れしました」と言う。千代丸もまんざらでもない。そして、ある日、李は千代丸と二人きりになった時に、話があると言って切り出した。「私、本国の上海に帰ることになりました。一緒に来てはもらえませんか?あなたは、ラシャメン(異人専門相手の女郎)とは違います。立ち居振る舞い、目の輝き、すべてが美しい」。そして、口説き文句を放つ。「私と一緒に、長い人生の万里の長城を歩きませんか?・・・答え、待っています」。
舞台は現代に。後輩は、先輩に相談事を打ち明ける。「単身赴任が決まったんですよ。上海に。彼女は一緒に来てくれるかなぁ?」。二人は港の見える丘公園から外人墓地へと歩き、中華街へ繰り出すことに。「きょうは、お前の奢りだ!」。
再び、明治の横浜。卯之吉が千代丸となったお松と再会する。「何年ぶりかな?・・・チラリと聞いたよ。李さんが上海に帰るそうだね。一緒に行くのかい?芸人というのは、人を騙すのが商売なんじゃないのかい?」「行くかも知れないね。お前さんがグズグズ言うから!」「何を!お前なんか、ラシャメンじゃないか!」「聞きづてならないね。私は女郎じゃないよ。指一本だって触れさせない。李さんは他の異人さんとは違うんだ。ラシャメンを馬鹿にするんじゃない!あの人たちだって、仕方なくやっているんだよ!」「お松っあん、よ。考え直しなよ」「私は千代丸だよ。頭、冷やしなよ!」。本当は、お互いに思い合っている卯之吉とお松の言葉の行き違いが、運命の切なさを演出する。
李は特別に千代丸と話ができるように座敷を用意してもらい、二人きりになる。そして、思いがけない言葉を口にする。「答えは言わなくていいです。私は本国に帰ることになりました。あなたを連れてはいきません。あなたは日本の人、横浜の人。私は上海の人。故郷には思い出があります。山、川、海、親、兄弟、友達がいます。私の上海は、あなたの横浜。私はあなたに惚れています。しかし、あなたは私に惚れていない。あなたは、ここでいい人と一緒になった方がいいです」。そして、別れのプレゼントを渡す。「判子を作らせました。メノウという石でできた落款です。千代丸ではなく、かなで『まつ』と彫らせました。幸せになってください」。何という、紳士的な愛の告白と、素敵な別れの言葉。李の台詞に、切ない恋心が盛り込まれ、僕の胸を締め付けた。千代丸は「宝物にします」と言って、李にお酌した。
舞台は変わって、現代。先輩と後輩が中華料理屋で紹興酒で乾杯をする。「上海に単身赴任か。女ははぐらかすからな。待っているわ、と言いながら、待っていない女が山ほどいる」「男と女は難しいですね。彼女は31なんです。彼女は待っていてくれますか?」。本当の気持ちがわからないで悩む後輩である。
再び、明治の横浜。卯之吉がお松と会っている。「何で私に会いにきたんだよ!私はお松っちゃんでもなければ、千代丸でもないんだよ」。そうなのだ。お松は借金に困り、ついに女郎になったのだった。「男と寝る私を、笑いに来たのかい?」「会いたいから、来たんだよ」「一番会ってほしくない人じゃないか。こんな形で会いたくないよ。私はお前を好きだった。お前も私を好いている。上海なんかに行くわけないじゃないか!李さんはわかっていた」。さらに、お松は繰り返す。「お前さんだけには会ってほしくなかった。お前さんに金で買われるために、女郎なんかになったわけじゃないんだ」。卯之吉は申し訳なさそうに言う。「あの時、座敷に千代丸を呼びたかったよ。金を貯めて、お前のことを助けてやりたかった。でも、俺は、お前が女郎になるのを指をくわえて見ているだけだった」。そして、「女郎になったから、会えるんじゃないか。金出せば、会えるんだ」と言う卯之吉に、「やだよ、銭や金で会うなんて」とするお松。卯之吉は絞るような声で「俺はただ、お前に会いたくて・・・。俺の気持ちもわかってくれ」。
すると、お松が源氏名を「瀧川」にした訳を話す。「崇徳院さまの歌にあるだろう。『割れても末に逢わんとぞ思う』ってさ。一緒になれるようにって願いを込めたんだよ。それは李さんじゃない、お前さん、卯之吉さんのことだよ」。なんて、素敵な愛の告白だろう。「つらい夜だが、一晩一緒に過ごしてくれるか?」「つらいけど、初めての嬉しい夜になるよ」。その晩、二人はひとつになった。寝返りを打つお松に、卯之吉がふと目をやると、手にしっかりと守り袋を摑んでいる。中を見ると、李から渡された落款が。「なんで?涙いっぱいためて、話していたお前は、やっぱり嘘だったのか?こんなものを後生大事に持ちやがって!所詮、お前はラシャメンじゃないか。このアマ!」と卯之吉は言葉を吐き捨て、落款を懐に入れた。
そして、お松の首を絞めようとした時、「火事だぁ!」という叫び声が外からする。遊郭一帯は火の海だ。火元は「豚鉄」らしい。「飛び降りろ!」。三階から飛び降りたお松は、必死の思いで逃げて、海へ。異人たちが舟に乗せて助ける。だが、あまりの人数の多さに、舟がひっくり返り、辺り一面は地獄絵図のよう。そこに「千代丸さん、舟に乗りなさい」と、李が現れた。火の粉が飛ぶ中、李は千代丸を抱いて、助け出した。「ここまで来れば、安心です」「港崎は?」「火に飲まれています」。卯之吉の行方もわからなくなった。
で、現代の横浜。「なんて話があったらしいんだ」と先輩。「落款は?」「海へ落ちたままだよ」「卯之吉は?」「それっきり、わからない。死んだんだろう」。そして、先輩は言う。「どうアドバイスしても仕方のないことよ。所詮、男と女は良くわからない、ということだ。騙された奴がいれば、騙す奴がいる。気にするな」。と言った上で、「全部、作り話だよ!」。そのあと、「純情日記」を髣髴とする道中付けをやって、先輩は「俺の若い頃のデートコースだよ。あの頃は、死にたかった。でも、その後、あんなこと、こんなこと、色々あったさ。死ぬなんて、とんでもないことだ。前だけ見ろよ!」。そこに、突然風が吹いて、二人は波をかぶった。後輩のおでこに、なにやら直撃したものが。メノウの落款だ。「彼女、待っててくれますかね?」に、落款の文字が「まつ」で、サゲ。
素晴らしい創作落語である。開港当時の横浜の文化・風俗をたっぷりと描きこんだ背景に、展開されるドラマチックな悲恋の物語。それを、「純情日記」の主人公その後と上手に絡ませて、素敵なサゲにもっていく。恐るべし!喬太郎。横浜開港150周年記念にふさわしい素晴らしい高座だった。