【志ん朝七夜】⑦ 志ん朝が行く末を案じていた言葉の文化としての落語
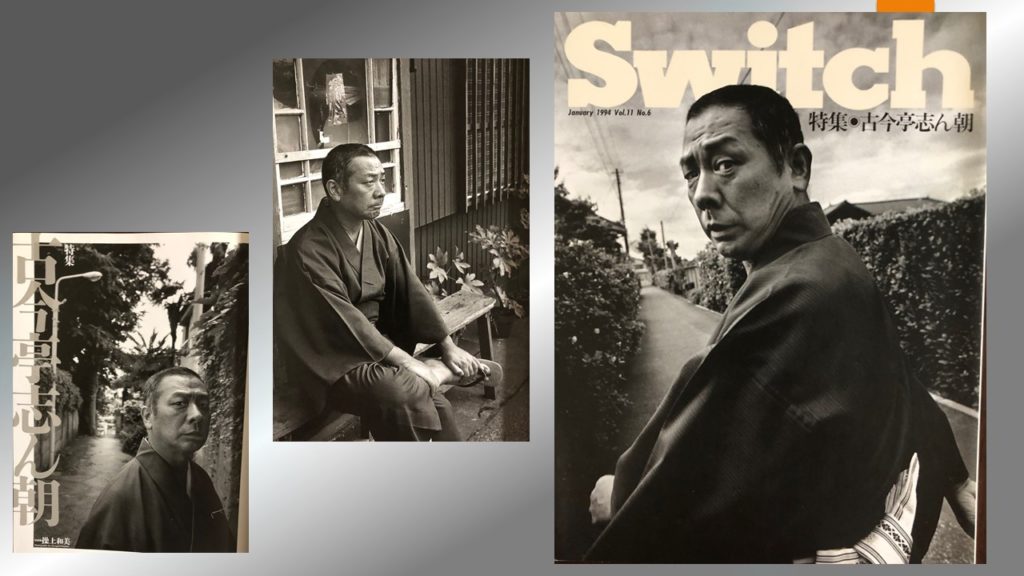
古今亭志ん朝師匠が十八番の「火焔太鼓」のサゲである「半鐘はいけないよ、おジャンになるから」というのは、この先通用しなくなるのではないか、という危惧を生前、というか、かなり以前からされていることはきのうのブログで少し触れた。志ん朝師匠は日本語について、それも時代とともに変わっていく日本語について非常に関心があったし、深く考えていた。それは古臭くなっていく言葉もそうであるが、コンプライアンスが喧しくなってきた現代における差別用語などについてもそうだ。広い意味で「志ん朝師匠と日本語」についての幾つかのインタビューを抜粋しながら、落語という言葉の文化の今後について考えていけたらと思う。
まずはNHK教育テレビ、93年8月27日放送「ことばは変わる」のインタビューの抜粋。(聞き手:松田輝雄アナウンサー)
そりゃあもうやりにくいですよ、「糠みそ」はもちろんわからないし、「敷居」はわかるが「鴨居」になるとわからない。歌舞伎は道具が出てきて目で見てわかるんですが、噺のほうは、言葉を言うだけですからね。こないだ若い人に「行燈って知ってる?」ってきいたら、「食べ物ですか」なんて言われちゃって。何だか天丼の親類なんかと間違えているらしいんですよ(笑)。そんな食べ物があっても不思議じゃないかな、なんてこっちが考えたりして。
今の人にこっち(落語)へ“入ってきて”もらおうと。例えば「糠みそ」っていう言葉にしても、知らないで聴いているうちにわかってくるんじゃないかと。親御さんにきいてみるとかして。ごく下世話な言い方ですが、もし私に、好きな女の子ができたとします。今はできてないんです(笑)。できてないから勉強しないんです。もしできたら、きっと勉強しますよ。今の言葉だとか、音楽なんかも。抵抗を感じながらも、気に入ってもらおうと、きっといろんなことを勉強すると思います。だから今の若い人たちもこっちのほうに、ちょっと興味をもってくれたら、落語を聴こうと思ってくれたら、言葉なんかもひとりでに勉強するんじゃないかと思います。こちらからあんまりお客様のほうへ寄ってちゃうと、私らの噺がなくなっちゃうんです。せっかく先人が遺してくれたものが。
結構若い人がお見えになるんですけど、やはりマニアの方が多くて、そのマニアの方が「落語って面白いよ」ってんで連れてきてくださる、そういう方が一回来て嫌になるか、「面白かった、また行きましょう」となるか、そこんとこですね。だからいつでも、使っている言葉は古くても、「噺は生きている」というふうにしておかないといけない。それと、落語の言葉は決して間違っている言葉ではなくて、かつてはこういう言葉が実際にあったし、使っていたんだと、こっちも自信をもってしゃべらないといけません。お客様に合わせて、合わせすぎると、ほんとに落語はなくなっちゃいますから。以上、抜粋。
落語は先人の残した財産であり、それを時代が変わったからといって、変えすぎると、壊れてしまう。だから、お客様に「こっち」へ入ってきてもらう努力が噺家には必要で、そのためには「噺が生きている」ことが肝要。まさに、この志ん朝師匠の考えを、2020年の現在進行形でそれぞれの噺家がそれぞれのやり方で実践しているからこそ、今の落語人気があるのだと思う。
時計をもう少し昔に戻してみよう。「週刊読売」79年11月25日号、国文学者で民俗学者の池田弥三郎さんとの対談からの抜粋。
志ん朝 あたしらこういう商売のせいか、すごく気になんですよ、最近の言葉の乱れが・・・。
池田 うーん、しかし、言葉ってのはどんどん変わっていくからね。
志ん朝 あたしらも、上の人に教わった通りにやってるつもりなんだけど、やっぱり、昔とは変わっちゃった新しい言葉を何気なく使っちゃうんですね。
池田 だけど、お客のことも考えてやらなくちゃね。ぼくは大正育ちだけど、その頃聞いた言葉で、いまはまったく消えちゃった言葉がたくさんあるもの。
志ん朝 そうでしょうね。
池田 たとえば「アバヨ」なんてのは、明治になって出来た言葉なんだろうけど、今の若い人なんか聞いたこともないだろうし。「ハイカラ」なんてのもそうだ。
志ん朝 うーん、そういやそうですね。
池田 だから噺でもね、少しは古い言葉と新しい言葉を差し替えないとね、お客に不親切ってことになるでしょ。
志ん朝 兼ね合いが難しいんですよ。極端に新しい言葉を使っても、違和感ばかりが目について、具合悪いんですよ。
池田 そういや、こないだテレビで、あなたの「火事息子」を聴きました。大変面白かったんだけど、一つだけ気になったことがある。おしまいのほうで、酒屋の旦那だったかが火事見舞いに行く。「いま通ったのはだれだい」「酒屋のお父さんだよ」って言ってた。お父さんはおかしやね(笑)。
志ん朝 えっ、本当ですか。うっかり口をすべらせたのかもしれないけど、お恥ずかしいですな(苦笑)。
池田 「お父さん」って言葉はね、明治33年に出来た言葉なんだ。
志ん朝 あ、そうですか。
池田 文部省が、初めて国定教科書を作ったとき、子供が父親や母親を呼ぶ呼称を統一する必要に迫られて、「お父さん」「お母さん」て言葉を作った。それまで庶民は「とうちゃん」「かあちゃん」とか「おとっつあん」「おっかさん」と千差万別だったからね。もっとも、学習院だけは、われわれは庶民じゃねえんだってのか「お父さま」「お母さま」を使っていたんだけどね(笑)。
(中略)
池田 明治・大正育ちの人間が「ハンケチ」で、昭和生まれが「ハンカチ」使うとね、ぼくらなんか、はっきり時代の差を感じるね。
志ん朝 なるほどね、やっぱり言葉っていうのは自然に変わっちゃうんですかね。
池田 それはどんどん変わりますから、変わるのが言葉の運命なんだね。
志ん朝 そうですねェ。噺のほうでも本当に困りますよ。「へっつい」なんて言葉がわからなくなっちゃったし、「火焔太鼓」のオチで「おじゃんになる」ってのも知らない人が多くなった。
池田 ああ「おじゃん」も、そうかね。「おじゃん」の「じゃん」は半鐘のジャンと鳴る音にかけてあるんだろ。
志ん朝 そうなんですけど、いまどき半鐘なんて見かけなくなったし、おじゃんになるなんて言葉を使わなくなりましたでしょ。
池田 しかし、それがわかんないと噺のオチになんない。やりにくいだろうな。
志ん朝 たとえば「ドキッとした」なんて言葉はいつからあるんですか。
池田 さあ・・・。「どぎつく」というのはかなり古くからあるし、そういう擬声語は古いんじゃないの。ドキンとするとか・・・。
志ん朝 「がっかり」ってのはどうです。こないだ、フッと使いたくなったんだけど、考えて躊躇してよしちゃいました。
池田 大丈夫ですよ。「り」のつく言葉は非常に古くからあるから。たとえば、「ほんのり」「ひんやり」「どっさり」・・・。
志ん朝 あ、そうですか、安心した。
池田 その「り」がいま「し」に変わりつつあんのね。「ぴったり」を「ぴったし」とか、「そのかわり」を「そんかし」とか・・・そういうのが最近の流行語みたいなんだね。
実に興味深い対談である。言葉というのは、時代とともに変わるのは当たり前。大正生まれの池田先生は落語の中にも臨機応変に、節度を考えつつ、取り入れた方がよいのではと考える。昭和生まれで噺家のプロである志ん朝師匠は、この言葉は取り入れていいものかどうか、言葉と格闘しながら、大袈裟に言えば、時代と格闘しながら、落語という伝承芸の牙城を守らなければならないと考える。攻撃は最大の防御という言葉もある。それはいまの噺家さんたちも同様の格闘をしているのではないか、と思う。
最後に、「家庭画報」96年11月号、中村江里子アナウンサーとの対談から抜粋。
中村 落語の世界で言ってはいけない言葉ってありますか。
志ん朝 ええ、放送禁止用語と同じですね。楽屋にネタ帳というのがあって、前座がつけていくんです。たとえば「寿限無」、志ん朝と書いて、次に上がる人に持ってって、この後よろしくお願いしますと。その日のネタをどんどん書いていくんです。だんだん深くなるにつれて、やるものが少なくなってくるんですよ。同じジャンルや形態はよける、酔っぱらいの噺が出たからよけようとか。オウム返しのものは出てるからとけようとかね。
中村 ネタが重ならないための工夫ですね。
志ん朝 そのネタ帳に小さな紙をこうパッとかけてね、足の不自由な人がおみえですとか、車いすの方がおみえですとか、ちゃんと書くんですよ。
中村 ウワーッ!そうなんですか。初めて聞きました。
志ん朝 それでそういう噺は避けるようにとか、そういうことで神経を使うんですよ。
中村 それは若い噺家のかたにも受け継がれてますか。
志ん朝 今の若い人はわりによく心得てて、言っちゃまずいことは、なんでもなくすっとよけられるみたいですよ。あたしらの年代のほうが、昔、何気なく使ってた言葉が放送禁止用語になっているから。
中村 ええ、そうなってますから。
志ん朝 困っちゃうことがあるんですよ。ただ、寄席の場合はね、それはいいではないかってとこがありましてね。あり盲目のかたとお話しする機会があって、そしたら、「いやあ、そういうお気遣いが一番、かえって困るんだ」と。気遣ってるのが手にとるようにわかるっていうんですよね。「それよりも普通にしゃべってくれたほうが、私たちは承知で聴きに来ているんだから、なんでもないんですよ」って。それで少し、安心しましてね。放送禁止用語もなかなかやっかいですね。
中村 悪気があって言ったわけじゃなくても、引っかかるから、言うまい言うまいと逆に意識しますね。絶対に出しちゃいけないと神経質になりすぎて。
志ん朝 落語にはいっぱいあるんですよ。とりわけ関西の滑稽噺なんて、もうごく下世話な世界の噺にそういう言葉がたくさん出てきます。
中村 登場人物が語るわけですものね。だから、たとえば、誰のことを言うのでもなく、自分ことをびっこと言うのでも、だめだっていう・・・。
志ん朝 ましてや落語は、昔の裏町でしゃべっているのに、足の不自由ななんて言い方はしないんですよ。
中村 そうですよねえ。
志ん朝 明きめくらという言葉も、僕ら、高座では平気で使いますけどもね。いわゆる無学文盲ということに対して言うんで、意味が違いますから。「子別れ」という噺は、道楽がもとで、女房子供を追い出しちゃって、それがいけないことだったと目が覚めて、一所懸命やってる職人が、バッタリ子供と出くわすんです。「おっかさんが学校行かなきゃだめだって。これからは職人でも学問がなきゃだめだ。おまえのおとっつあんは職人として腕はいいけれども、明きめくらだった。おとっつあん、明きめくらなんだってねえ、よくあたいがここにいたのわかったね」って言う・・・。以上、抜粋。
何をかいわんや、である。言葉の微妙なニュアンス、日本語の持つ伝統的な言葉のパワー、そこから生まれる慣用句や洒落、言葉遊び…、これらを抜きにして落語という文化は成り立たない。ただ闇雲に「危なそうな言葉」をよけることが、文化を耕すことになるのか。そこに汲々としているマスメディアにはその役割は果たせない。コロナ禍で俄然注目を浴びた、ネットを使った配信における落語においてはどうだろうか。志ん朝師匠の「芸は消えるから、いいン」という台詞に何か答えがあるような気がする。ある限られた観客を前に、ある限られた時間と空間で繰り広げられるライブとしての落語の魅力に思いを馳せている。


