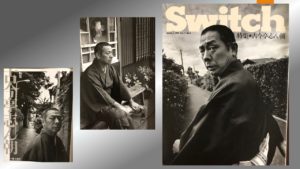【志ん朝七夜】⑥ 志ん朝肝いりの「フタベン」で育ったトップランナーたち(下)

二ツ目勉強会(通称「フタベン」)で志ん朝師匠からアドバイスを受け、現在の落語人気の一翼を担っている噺家について、きのう、「フタベン世代」と書かれた長井好弘さんの文章からほんの一部紹介したけれど、もう少し紹介したい。2014年10月に河出書房新社から刊行された「KAWADE夢ムック 永久保存版 古今亭志ん朝」で、この書籍の企画、取材、執筆を担当している石井徹也さんの「二ツ目勉強会と古今亭志ん朝」と題した噺家へのインタビューは非常に示唆に富むものなので、そこからの抜粋をしながら、考えてみたい。
まずは柳家三三師匠へのインタビューから抜粋。
「二ツ目勉強会」で初めて志ん朝師匠に聴いていただいたのは平成10年かな。最初の頃はあまりこと細かに直してくださることはなかったんです。「ろくろっ首」を演ったとき、「こういう古めかしい噺をやっておくのもいいことだ」と。「二十四孝」を演ったときは、先代(五代目柳家)小さん師匠の音をずいぶん聴いていて、言葉の癖が移っていたんです。「ああしなくちゃいけない」が「ああしなくちゃいかねえ」とかね。それを志ん朝師匠に「小さん師匠は、それが当たり前になってるけれども、君が無理に真似しようと思っても板についてないね」と言われたくらいかな。細かい部分を指導していただいた記憶はあまりないんですよ。
おそらく志ん朝師匠に最後に聴いていただいたのは「大工調べ」だったと思い」ます。そのときに「お前ならもうちょっと演るかなって思ってたんだけどな、そんなに良かぁなかったね」と言われたんですが、それで逆に「反省会ではさらっと流すだけで、相手にもされていないと思っていたけれど、少しはそういう目で見てくださったのかな?」という気がしました。
そのときは権太楼師匠もいらして「お前のだと穏やか過ぎて喧嘩にならないよ。啖呵を切るところはもっと勢いに任せてポンポンポンって言うところを、小三治師匠の真似をしてところどころ切ってゆっくり言ったりしてるんだろうけど、お前がそこだけ真似をすると勢いがそがれる」と言われました。志ん朝師匠も「そうだね」と、二、三、他のところについても「ここんところはこういう流れで言うけれども、そこんところはやっぱり息を継がないでスッといって」とか「言葉の意味だと、ここで区切るんだろうけど、そこは継がないでほかのところで」と、ちょっと細かい指導をしていただけたんです。
のちに僕が真打になる直前に「大工調べ」をまたかけたら、志ん朝師匠の惣領弟弟子である志ん五師匠が、「そのキャリアなりに」という意味で「良かった」と言ってくださった。それも嬉しかったけど、同時に「志ん朝師匠だったら何ておっしゃったかな」と思ったものです。
志ん朝師匠の場合、「こうするとお客さんからはこう見えて、自分が思っていることがもっと伝わる、もっとわかりやすくなる。だからそのためには、上下であったり自分が舞台をどう設定しているってことをきとんと頭に描いて、それを的確に表現しなさい」という考え方です。ある意味、必要最低限の技術を中心に据えた上で、「登場人物の気持ちがこうこうだから、こういう表現になるんだろ」という指導方法でしたね。以上、抜粋。
志ん朝師匠の落語に、「お芝居の舞台を基本に」という考えが流れているのは、カミシモを知らなかった新潟時代の白鳥師匠に、30分かけておしぼりを花道に見立てて説明してあげた逸話からもよくわかる。また、三木のり平に師事して、役者として舞台に上がっていたことも、志ん朝落語に大きな影響を与えていることからもわかる。それは今、演劇的な落語を演る噺家さんが人気を得ているのと、あながち離れていないような気がする。
続いて、桃月庵白酒師匠へのインタビューから抜粋。
「二ツ目勉強会」に出始めて2回目くらいでしたでしょうか。古今亭駿菊兄貴が「どうせ演るんなら志ん朝師匠の演るネタを演った方が小言が言いやすい」と教えてくれたので、「強情灸」を演りました。でも公演のすぐ後の品評会では、特に志ん朝師匠からは何も言われなかったんです。生臭いことは品評会では言わないですから。
でも、その後、呑み会になったら、志ん朝師匠から「雲ちゃんの弟子だから好きなのはわかる。演らんとすることはわかるんだけど、それじゃ金は稼げないからねぇ。それはちょっと違うと思う。演りたいことをどうお客さんに伝えるかっていう作業をするのがプロであって、そこにお客さんはお金を払うんだ。ただ君が演りたいのを見せつけるだけだったら、落語じゃなくて、美術館とかでも飾っておきなさいよ」みたいに言われて「ハハァー」って(笑)。「具体的に上手ければいいってもんでもない。やっぱりプロだったら金を稼げ」と。
それから実名を例に挙げて、「この人たちは上手かった。引き出しはあった。ただ、俺が言うのは失礼だけど金は稼げていない。っていうことは俺はプロとしてどうか?と思う。雲ちゃんはちゃんと考えて演ってるんだよ。よくよく見たら臭いでしょ、臭いんだよぉ。おじさんも臭かった、もっと臭かった。今でも臭いと言われてるけど、『強情灸』は本当に臭かった。『熱いよぉ、熱いよぉ』って演ってた」と言われました。
「金を稼げ」とか「金を取れ」といったことは、志ん朝師匠は絶対おっしゃらない方だと思っていましたから、そのお話は強烈でしたね。「芸を磨いて」とか言う方だと思ってた。もちろん相手を見てのことだと思います。金ばっかり追っている人には「芸を」とおっしゃったのではないでしょうか。以上、抜粋。
志ん朝師匠の「おじさんも臭かった、もっと臭かった」はけだし名言だ。美学とか言ってハナから気取るのではなく、お客様に「わかりやすく」「わかってもらう」ことが、まず一義的に必要で、そこで認められてから個性云々が出てくる。その上で「臭いのは嫌だ」と演者もお客様も思う芸人になったときには、そこで「臭み」を排除して「気取り」が出てくればよいということだろう。それは真打になって10年、いや20年くらいかかる作業だと思う。その次の「付き馬」についても、まず「金を稼ぐ」だ。以下、再び抜粋。
「付き馬」を演ったときは、いろいろと入れ事、遊びも入れつつだったんですが、志ん朝師匠からは「いいんだいいんだ、廓噺は今はね、なかなか通じないから。何よりもここは楽しいところなんだから、当人が楽しいってことが伝わらなきゃダメだからね。ただね、“江川の玉乗りの口上”の件はね、おじさんも本物を聴いたことがないから。雲ちゃんだろ、どうせ」と「どうせ」って言われちゃった(笑)。
「まあ、雲ちゃんだったら言うかもしれない。雲ちゃんに弟子入りしたくらいだからそういうとこが好きなんだろうけども、江川の玉乗りの口上に何か意味があるのかな?別にここだけだろ。サゲにつながるとか、このあとの道中につながるわけでもないだろ。だったら、ここは江川の玉乗りじゃなくてもいいんじゃないか?」と言われました。要は下手すると、「江川の玉乗りって何だろう」と、お客さんの思考が停止する訳ですね。
志ん朝師匠からはまたこう言われました。「廓噺は今は通じなくなっているから、できるだけお客さんにわかりやすくするためには世界観を統一させて。要はお客さんに見せる物だけど、どういう世界観かっていうのをわからせるための努力が足んない。まだ独りよがり。ハイ『付き馬』演りました、俺、頑張ってますって感じだ。今は良いけど真打になったら誰も言ってくれないよ。で、誰も金を払ってくれないよ」と、金、金、金で叱られた訳です(笑)。以上、抜粋。
現代の人にわからない言葉、思考を停止してしまう表現が出てきて、折角噺を積み上げてしまうものが崩れることに対する恐れ。それは志ん朝師匠自身にも、ものすごくあって、このムックのインタビュアーである石井徹也さんも、志ん朝師匠が早稲田大学教授の暉峻康隆先生との対談で「もう(『火焔太鼓』のサゲの)『おジャンになるから』がわからないんですよ、お客さんには」とすごく気にしていたことを引き合いに出している。古典落語の世界の中の言葉、価値観を大切にしながらも、どう現代の人たちにわかってもらうかに苦悩していたことがわかる。僕自身はおじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らして育ったので、「おジャン」は当然わかるが、同級生との会話で「なに、お前、古臭い言葉使ってるの?おじんくさい」と苛められたことがある。唐茄子とか、粗忽者とか、ルンペンとか、僕の家庭では普通に使われていた言葉が、後年、実は一般的でないことを知る。
最後に橘家文蔵師匠(当時は文左衛門)のインタビューから。以下、抜粋。
「二ツ目勉強会」ではずいぶんいろんなことを志ん朝師匠から教わったというか直されましたね。僕はそういうことをあまり気にしなくて、「むしろ直してくださいよ」ってほうだから嬉しかったです。「アラを探してください」という気でいました。
「らくだ」を演ったとき、終わった後の反省会で、「お前の『らくだ』は凄味があるね。本当にああいう奴には出会いたくないよ。でもな、お前。乱暴者とガラが悪いのは違うぞ。お前のは、目を背けたくなるような奴になってる。やっぱかわいげがないといけねぇんだよ。らくだの兄貴分の丁の目の半次と屑屋の関係は、最後に逆転するわけだから、そういうところを活かすためにも凄味を出すのはいいけれど、目を背けたくなるような怖さじゃあ、噺は誰も聴いてくれないぞ」とおっしゃいました。
また「お前は訛ってないし、聴きやすいからもっともっと稽古したほうがいい。ちょっとたどたどしいところがあるから流暢にね」とおっしゃってくださったこともありました。(中略)「千早振る」を僕が演ったとき、滅茶苦茶な「千早振る」を演ったら「あれはあれでいい。別に古典落語とはいえ現代語のクスグリを入れてもいいんだよ。でも、だったらサゲを変えろよ。登場人物の個性を変えたのはお前なりの工夫だから、俺にはできないから、そういうことは」って。(中略)だから現代語のクスグリを入れることも、別にそれがウケればよいわけで、むしろほめてくださいました。「うん、いいんだ、あれで」って。以上、抜粋。
その時代、その時代の聞き手にわかりやすいもの、そして面白いものを提供するのが噺家の仕事だという論は古今亭志ん朝師匠の落語の核をなすものだった。それは勿論、基本的な骨格がしっかりしていて初めて成立するものであることは当然だが、時代の要請で「古典」を現代に合わせて変えるべきところは変え、頑として変えてはいけないところは変えないという作業を、マクラを含めて志ん朝師匠はさかんにやっていた。だから新作にも理解が深かった。いまの人気の噺家を見ても、そのイズムをきちんと踏襲していることがわかるのである。