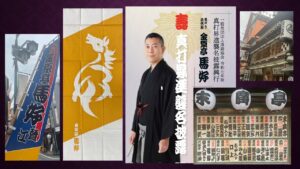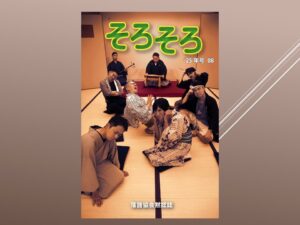浪曲定席木馬亭 国本はる乃「水戸黄門漫遊記 孝子の訴人」天中軒雲月「若き日の小村寿太郎」

木馬亭の日本浪曲協会十月定席千秋楽に行きました。
「たにしの田三郎」東家一陽・東家美/「深川裸祭の由来」港家小蝶次・伊丹けい子/「闇に散る小判」東家孝太郎・沢村まみ/「男はつらいよ 寅次郎頑張れ」玉川太福・玉川みね子/中入り/「水戸黄門漫遊記 孝子の訴人」国本はる乃・沢村道世/「め組の喧嘩」神田春陽/「サツマスチューデント~新英国密航~」東家一太郎・東家美/「若き日の小村寿太郎」天中軒雲月・沢村博喜
はる乃さんの「孝子の訴人」。代官の寺田佐門次が出したお触れの立て札、牛泥棒を訴人した者には望みの褒美を遣わすという。名乗りをあげたのは坂部村の百姓、与茂作の倅の与茂吉十一歳。先月14日に自分の父親が見知らぬ牛を連れているところを見て、どこへ行くのかと訊くと朝市に行って売り払うという。「誰にも言うのではないぞ」と父は釘を刺した。きっと牛泥棒は父親の与茂作に違いないと訴人した。
代官に呼び出された与茂作は白状する。悪いこととは知りながら、牛泥棒を働いて、十両二分で売り払った。十両盗めば首が飛ぶ。代官は九両二分の間違いではないかと助け船を出すが、与茂作は正直だ。5年前までは村一番の金持ちだったが、3年前に父が患って亡くなり、母も眼病に罹り盲目となった。さらに女房の産後の肥立ちが悪く、寝たきりに。屋敷も家財道具も売り払って、食うや食わずの日々。だが、母親に父の法事だけは済ませてくれと言われ、用立ててくれる人を探したが全て断られ、切羽詰まって思わず知らず出来心をおこしてしまった…。
与茂吉は訴人の褒美として「父の命を助けてほしい」と言う。それは出来ないと言う代官に対し、「代官様は嘘偽りの立て札を出すのか。望みの褒美を遣わすと書いてあったではないか。あまりに勝手ではないか」と抗弁する。代官は「広い世間で自分の親を訴人する奴がいるか」と言うも、与茂吉は「お父っつぁんを助けることができないなら、家族4人の首を討ってくれ。二つに一つの返事をください」。
これには代官の寺田佐門次も弱った。牛泥棒を見逃せば、公儀に対し申し開きができない。佐門次が小刀を抜いた、そのとき…お調べを見物していた水戸光圀が「しばらく!」とこれを止める。「そんなことをして仏が浮かばれようか。馬鹿者め!」。黄門様が間に入り、与茂作一家は元通りの百姓に戻ることができた。そして、佐門次も仙台藩五番家老にまで出世したという…。孝子、すなわち親孝行の決定版みたな浪曲である。
雲月先生の「小村寿太郎」。小村と牛込の仕出し弁当屋の魚平の身分を超えた友情、男同士の真心に心を打たれる。頑固一徹の小村は新政府の方針で反りが合わずに、下野。妻が大病を患い、家財道具を売り払っても、赤貧洗うが如くの暮らしになってしまった。女中が「嘘も方便」と、日に三度の弁当を運ばせて、「上流階級の勘定は年一回、大晦日だけ」とだまくらかしていたが…。
とうとう、大晦日がやって来て、魚平が「伊達や道楽で商売をしているわけじゃない!小村を出せ!」と勘定の催促に乗り込んできたが。奥座敷に通されると、そこには病で床に伏せた妻の横で両手をついて藁畳を涙で濡らす小村の姿があった。
切羽詰まって、長い間騙し続けてきて申し訳ない。一日一日が地獄の苦しみだった。一度も美味しいと思って弁当を食べたことはなかった。訴えられて縄目の恥辱に遭っても、憎みはしない。もしも許してくれるなら、私が再び国家に奉公できるまで待ってくれないか。この通りだ。
魚平の瞼に滲んだ一滴。「勿体ない。そんなにまでおっしゃってくれるなんて。手を上げておくんなさい。これから何年かかろうと、今まで通り弁当は必ず運んでまいります」。小村の頬に感謝の露時雨。奥方も堪りかねて、ワッと泣く。目に浮かぶような感動的な場面だ。
そして2年が経った明治20年。「朝鮮内乱」を伝える号外が出る。記事には小村の名が…。牛込の魚平宅の前に人力車が止まる。フロックコートに山高帽、大礼服姿の小村寿太郎だ。
思えば長い3年間、よく面倒を見てくれました。首相と外相に呼び出され、大使の大任を命じられました。家族に報告する前に、まず第一に魚平さんに知らせたかった。この支度金5千円は弁当代として受け取ってください。あなたの情けに比べれば、私はまだまだ恥ずかしい。何も言わずに笑って納めてください。
良い話だ。雲月先生では久しぶりに聴いた。いま、浪曲教室の生徒さんに、この「若き日の小村寿太郎」を教えているそうだ。天中軒では最初に習う演題。かおりさんも木馬亭の初高座は小村寿太郎だった。義理人情を唸る浪花節の魅力がもっと沢山の人たちに伝わりますように。