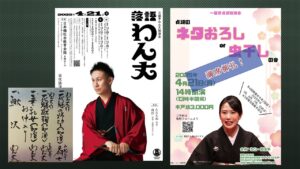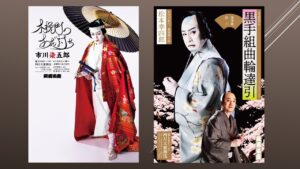ラッパ屋公演「はなしづか」、そして代官山落語夜咄 立川吉笑「ドラゴンタトゥーの男」
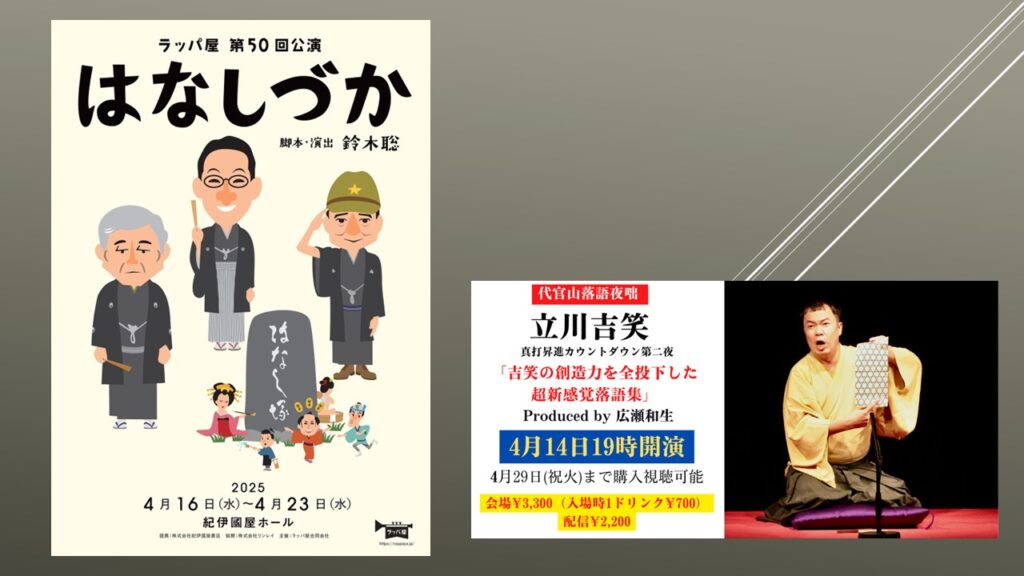
ラッパ屋第50回公演「はなしづか」を観ました。脚本・演出:鈴木聡。
「ご時世だから」という言葉の恐ろしさを改めて思った。戦時下に、落語界の幹部たちが「時局に合わない落語」として53種の噺を選び、これを禁演落語と呼んで浅草本法寺に“はなし塚”を建立し、葬った。国から命じられたのではなく、噺家自らが「自粛」したというところに恐怖を感じる。
「時代の空気を読む」と言うと聞こえはいいが、挙国一致、「欲しがりません、勝つまでは」と贅沢は勿論、不謹慎な娯楽は廃除していこうという世の中の動きに寄席の世界も同調したことは、その時代に生きていた人間ではないから判らないが、きっと抗えなかったものだったのだろう。
ラサール石井演じる世渡亭伊吉が時世に合わせて「国策落語」なるものを創作して演じていた。これも現代だからこそ、「愚の骨頂」と切り捨てることはできるが、当時としては噺家として生きる一つの道だったのかもしれない。その伊吉に召集令状が届き、戦地に出征することになったとき、伊吉は噺家仲間の春風亭昇太演じる晴々亭昇介と柳家喬太郎演じる渋柿亭喬次に対し、「本当は怖い」と本音を漏らした。大本営発表ばかり流している新聞社やラジオ局の報道を心の底では「違うのではないか」と思っている国民がほとんどだったのだろう。
やがて敗戦色が濃くなってきて、昇介や喬次の住む長屋もB29の空襲に巻き込まれ、火の粉を払って逃げようと昇介が喬次に声を掛けたとき、喬次は逃げようとしなかった。この場面が一番印象に残った。おそらく喬次の胸の内に棲み付いていたのだろう、噺の魂が走馬灯のように駆け抜けるのだ。「品川心中」のお染、「明烏」の若旦那、「風呂敷」のおかみさん、「鰻の幇間」の一八…。そして、喬次が十八番にしていた「居残り佐平次」の佐平次が酒を持って来て、二人で酒盛りをする…。このままでは喬次は焼け死んでしまうと思った昇介は喬次の頬を何発も殴り、正気に戻して事なきを得たが。
禁演落語は葬られたが、その噺の中の人物たちは決して葬られたわけではないのだ。魂を棄てたわけではないのだ。だから、終戦後に禁演は解かれ、今こうして現代の寄席で生き生きと活躍をしている。噺家一人一人の胸の中に“噺の魂”は生き残っていた。これが何より嬉しい。
脚本・演出の鈴木聡さんはパンフレットの中で的確に表現してくれている。
落語は「人間らしさ」の宝庫です。酒好き、道楽者、間違いを犯す人、喧嘩っ早い人、欲に目がくらむ人…周囲にいたらちょっと迷惑なんじゃないか、と思うようなダメ人間がたくさん出てくる。(中略)戦争をやっている時は、この「人間らしさ」が邪魔だったんでしょうね。デジタル化が進む今も、どちらかというと邪魔者扱いされている気が…。世の中がどんなふうになろうとも、心の中の熊さん、八っつぁんは元気でいてほしいなあ、と思う次第であります。以上、抜粋。
そうなのだ。この禁演落語自粛という問題は決して戦時下だけの問題ではない。特にコンプライアンスが過剰なほどに叫ばれている現代において、落語はいかにあるべきか?という問いでもあるように思う。そんなことを思った芝居だった。
配信で「代官山落語夜咄 立川吉笑 真打昇進へのカウントダウン第二夜」を観ました。今回はイラストをスクリーンに投影して、言葉で説明できない部分の表現を形にした、まさに新感覚の落語三席だった。
「でたらめの出目」。サイコロ職人の親方が弟子たちに自分の作ったサイコロを千回振らせ、出た目を記録して、そのサイコロがちゃんとしたサイコロなのか統計を取らせるという設定だ。ところが、弟子たちは千回振るのを面倒がって、適当な記録を親方に提出する。「二一三六」が繰り返される癖のある者、中に「七」や「九」というあり得ない数字を書く者、数字を記号化したためにアラビア文字みたいな記録になる者…。乱数表のようなものを期待していた親方だが、真面目に三か月前から千回振ったという銀さんの記録がなぜか「一二三四五六」を繰り返していたという皮肉…。「これでは売り物にならない」。数学好きの吉笑さんらしい。
「ドラゴンタトゥーの男」。棟梁が背中に彫っている昇り龍の刺青がカッコイイ!と話題になって、長屋の連中が真似をするが…。彫り師に「あの棟梁みたいに」と頼むことによって、様々な刺青が彫られる面白さ。棟梁の後ろ姿そのものを彫ってしまったり、前を向いて自分を見ている棟梁を彫ってしまったり、まだそれはいい方で、棟梁の周辺の犬が棒に当たっているところや黒船が来航した様子やスリが財布を盗んで逃げている現場…とめちゃくちゃ情報量の多い刺青になっているという…。そして、銀さんは二分しか持っていないので、「龍の一部でいい」と頼んだら、デッサンしか彫られなかったというのが面白い。これもイラストの必然性を感じる落語だ。
「後出しの祭」。三つの町がそれぞれにじゃんけんの神輿を担いで集結するという神事という設定がまず面白い。「最初はグー」なので、三町ともグーの神輿で集結するのはお約束。そして、次に何の神輿を担いでくるかで勝負が決まる。後出しはルール違反になるので、偽装パーで実はチョキという神輿を担いできた町。相手はパーと見て取って、チョキの神輿を担いでくるが、アイコになっちゃう!グーを担いでくれば良かったというのが可笑しい。さらに発展形で、「あっち向いてホイ」神輿があるというのは、いかにも吉笑さんらしいユーモアで流石である。