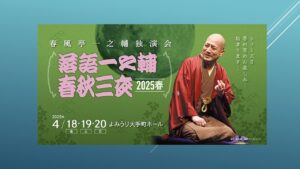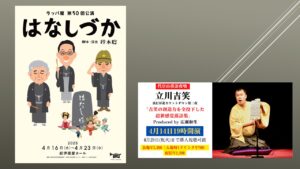貞鏡のネタおろしor虫干しの会 一龍斎貞鏡「仙台の鬼夫婦」、そして落語わん丈 三遊亭わん丈「花魁蹴鞠」

「貞鏡のネタおろしor虫干しの会~一龍斎貞鏡独演会」に行きました。「仙台の鬼夫婦」「清水次郎長伝 お民の度胸」「真景累ヶ淵 宗悦殺し」の三席。
「仙台の鬼夫婦」、ネタおろし。井伊直人に惚れて夫婦になったお貞は賭け碁にうつつを抜かす亭主に資金を提供し続けていたが、300両の持参金は底を尽き、嫁入り道具を売り払い、挙句に親に無心する有り様。ここで碁をやめろと言わずに、武士の本分たる剣術の奥義を見せて貰いたいというのがお貞の賢女たる所以だ。自らの薙刀で立ち合いを申し込み、直人が勝てば100両渡すが、負けた場合はその100両を持って剣術の修行に出てほしいと進言する。
果たして、お貞が勝って直人は江戸木挽町の柳生但馬守宗矩に入門し、三年修行した。仙台に戻ってお貞と立ち合うも、また直人は負けてしまう。再び柳生道場へ行き、死に物狂いで稽古をして二年。免許皆伝となって仙台へ。すると、お貞は直人の立ち振る舞いを見ただけで、「どうぞ家に上がってください」。直人に寸分の隙もないことが判ったのだ。
お貞とともに、そこに待っていたのはお貞の父、真砂三十郎だ。「これまでの無礼をお許しください」。三十郎の父、三左衛門は上杉との戦いの際に、直人の父である井伊直江に命を救ってもらった恩義があった。その後、直江は切腹。三左衛門は三十郎に対し、「直江の息子、仙三郎の後見をせよ」と言って死んだという。その仙三郎こそ、井伊直人である。
ここの件を読む高座を僕は初めて聴いた。お貞の賢女ぶりが勿論この読み物の眼目だろうが、さらにお貞の父の三十郎の熱い思いが直人を立派な武士にしたという部分もとても素晴らしいと思った。
「お民の度胸」。石松を匿った七五郎とお民の夫婦。七五郎はやがて襲ってくるであろう都鳥吉兵衛らを予測して、お民に対し「文右衛門のところへ帰れ」と言う。だが、お民は「なんで離縁しなきゃならないんだい。度胸だけは誰にも負けない。もし殺されたときは、お前さんと心中したと思って諦める」と覚悟を伝えるところがすごい。
都鳥一家がやって来て、「石松は来てないか」と訊く。「確かに来た。だが、昨夜に一緒に飲んだ後、帰った。吉兵衛さん、石松に金は返したかい?」。それでも疑う吉兵衛に対し、お民が言う。「怪しいと思うんだったら、家捜しすればいい。あそこの戸棚にいるかもしれないね」。それに追い打ちをかけるように「俺も小松村の七五郎。もし、いなかったら、ただおかないぞ」。
すっかり尻込みする都鳥一家に言ったお民の台詞がいい。「石松は何人で来たんだい?たった一人?…それがお前さんたちは10人で血刀ぶらさげているのかい?」。強い女を描くと貞鏡先生は天下一品だ。
「宗悦殺し」。金貸しの皆川宗悦が深見新左衛門の家を訪ね、50両の借金の利子だけでもいいから返してくれと迫ると、新左衛門は「酒が不味くなる。無礼討ちにするぞ」。宗悦は「無礼?無礼なのはどちらですか。斬れるものなら斬ってみろ」と返すと、酔った勢いもあって新左衛門は宗悦を殺してしまう。
以来、新左衛門の妻おまさが患い、枕には毎晩のように宗悦が現れ、「苦しいか。もっと苦しめてから殺してやる」と言う。新左衛門もうなされ、眠れない。そんな日々が過ぎ、一年が経った。宗悦の祥月命日の極月二十日。流し按摩を呼び、肩の凝りを療治してもらうと…。「私は小石川、貧乏人の巣、戸崎町から参りました」。戸崎町は宗悦が住んでいたところだ。
嫌になって、新左衛門が「もうよい、帰ってくれ」と言うが、按摩は肩を揉む。「痛い!」。左の肩を押さえると、乳の下かけて痛む。「あのときの痛みはこんなものじゃなかった…去年の今月今夜…斬られた宗悦は…」。新左衛門が振り返ると、そこには宗悦が!「迷ったか!」。斬り捨てると、それは宗悦ではなく、招き入れた按摩。今度は妻のおまさが宗悦に見えて…、新左衛門は刀を振り回し、妻も斬り殺してしまう…。父である貞山が得意とした「真景累ヶ淵」の序開きを貞鏡先生が鮮やかに読んだ。
「落語わん丈~三遊亭わん丈独演会」に行きました。「花魁蹴鞠」「たらちね」「鰍沢」の三席。開口一番は入船亭扇七さんで「花魁の野望」だった。
「たらちね」をネタおろし予定だったが、途中で絶句。扇七さんが引き継いで、続きを演じるというハプニングが起きた。扇七さんがわん丈師匠の作品「花魁の野望」を教わり、代わりにわん丈師匠が扇七さんから「たらちね」を教わった。いわゆるネタ交換だったのだが…。
前日まで鈴本演芸場でトリを勤めていて、覚える時間がなかった。自作の「花魁蹴鞠」もネタおろしだったので、負荷が大きかったのだろう。終演後に「こういう噺は若いうちに覚えないと駄目だね」とおっしゃっていた。円丈師匠に入門して最初に「八九升」を習った。続いて数席の前座噺を教わったそうだが、「たらちね」は習いそびれたという。改めて別の機会でわん丈師匠の「たらちね」を聴きたい。
「花魁蹴鞠」は「花魁の野望」の続編として、現在のサッカーに興味を持って町内の蹴鞠大会に参加するという噺。上総屋旦那がカズ、飯炊きの権助がゴンではなくてメッシ、解説がセルジオ越後屋という駄洒落。笛が吹かれ、黄色い札(イエローカード)が出されると、それは「警告」の意味だと説明され、思わず「傾国?」と反応してしまう花魁だ。網の前の守護神(ゴールキーパーだと思う)を買って出た花魁、ペナルティーキック?の球に自分の櫛を刺してゴール?を阻止して、MVPに輝く。選手が入場する際に禿を連れていたのが、現在のサッカーで子どもを連れて入場する由来になったという…。
もう少し練り上げて、通常の寄席でも掛かるのを楽しみにしたい。