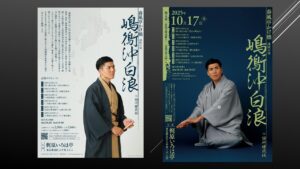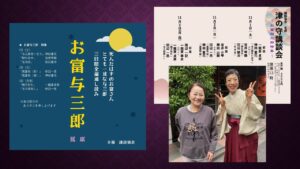津の守講談会「お富与三郎」連続口演 神田菫花「与三郎生い立ち」宝井琴鶴「馴れ初め」田辺銀冶「玄冶店」

津の守講談会初日に行きました。今月は神田菫花先生プロデュース「お富与三郎」の連続口演の三日間だ。
「三方ヶ原軍記」宝井琴人/「猿飛佐助 幸村との出会い」田辺凌々/「信長の最期」神田おりびあ/「出世浄瑠璃」一龍斎貞奈/「お富与三郎 与三郎生い立ち」神田菫花/中入り/「お富与三郎 馴れ初め」宝井琴鶴/「お富与三郎 玄冶店」田辺銀冶
菫花先生の「与三郎生い立ち」。日本橋横山町の鼈甲問屋、伊豆屋の若旦那は美男子で、放蕩三昧の日々。友人の神田川の旅籠、下田屋の茂吉と一緒に隅田川に花見に出かけ、その足で吉原に向かう。初めての店がいいだろうと入った中万字屋で、与三郎は九重にもてたが、茂吉は雲之井にふられ、「もう帰ろう」と騒ぎ出す。仕方なく、夜明けに店を出て、山谷堀で澤瀉屋という船宿の女将に声を掛け、両国まで船を出してもらうことに。
霧が出て、船頭の仙太郎は船の上で落ち着きのない茂吉に「おとなしくしてくれ」と注意するが、茂吉が聞く耳を持たないと、「田舎者」「猿の方がよっぽど利口」と罵る。怒った茂吉は殴りかかろうとするが、仙太郎がよけると、バランスを崩して川の中に落ちてしまった。首尾の松に船を括り、仙太郎は与三郎を一人にして、川に潜って茂吉を探す。だが、川の流れが速く、どこへ行ったのか判らないと、暫くして仙太郎が川から上がってきた。
「仕方ない。永代まで流されたんでしょう」と仙太郎は言って、このことは自分と与三郎の二人に胸の内にしまい、決して口外しないようにということになった。「これが露見するとただじゃあすまない」。与三郎は仙太郎に5両の口止め料を渡す。
人の噂も七十五日。下田屋から何度か茂吉の行方を訊いてきたが、知らぬ存ぜぬを貫いた。困ったのは仙太郎が何度も無心に来ることだ。きりがない。困り果てた与三郎は番頭の善右衛門に相談。「20~30両のまとまった金を渡して、腐れ縁を切りましょう」ということになった。だが、それ以降、仙太郎が現れなかった。
与三郎が薬研堀にある薬湯に行った帰り、「お久しぶりで」と声をかける男が。仙太郎である。母親が患い、女房が産後の肥立ちが悪く、子供は疱瘡に罹って、まとまった金がいるという。「百両ほしい」。それは何でも無茶だと思った与三郎は「勝手にするがいい」と言い放った。すると、奉行に訴えるという。「あっしとお前さんは牢に道連れですよ」。
路上での口論を聞いていた浪人風の男が仲に入る。「伊豆屋の与三さんじゃないですか」。顔見知りの関良助という元川越藩士だ。「道端ではなんだから、私の家で話しませんか」。良助の家で与三郎と仙太郎が一部始終を与三郎が話す。良助は「金の成る木でも見つけたと思ったのかもしれないが、迷惑な話。この一件はわざとやったわけではないので罪にはならないだろう。ただ、黙っていたは良くなかった。私が百両、立て替えましょう」。そう言って、与三郎を帰し、仙太郎と二人になる。
良助は百両はあるが、ここにはない、或る人に預けている、一晩泊まっていただき、明朝に自分が取りに行くという。だが、仙太郎は「今すぐに」と承知しない。或る人は飯田町の万字屋という酒屋にいるとのことで、「近所じゃないですか。二人で今から行こう」と仙太郎が言うので、出掛けることに。外は雪が降り始め、たちまち銀世界になった。九段坂下まで行くと、良助はいきなり刀を抜き、仙太郎の右肩を斬る。「お前のような悪党を生かしておけない」と言って、トドメを刺して、仙太郎は息絶えた。
亡骸は堀に投げ込み、横山町へ。伊豆屋に行って、主人の善兵衛に全てを話した。与三郎は人目のつかないところに住まわせた方が良いということになり、善兵衛の兄の源右衛門が営む木更津の藍問屋へ預けることにした。名目は「女にもてすぎて困る」…すごい口実だ。
琴鶴先生の「馴れ初め」。与三郎は木更津で退屈な毎日。吾妻明神の祭礼があって、碇床の金太郎が誘って、「見晴し」という料理屋の二階で一杯やっていた。店の名前の如く、木更津の海が一望できて、気持ち良い。
隣の部屋が賑やかだ。金太郎が覗くと、歳は二十五、六の実にいい女がいる。木更津の博奕打ちの親分、赤馬源左衛門の女房、お富だ。元は深川の売れっ子芸者で、横櫛のお富と渾名され、源左衛門が身請けしたのだった。部屋には一の子分のみるくいの松五郎がいる。金太郎が部屋に呼ばれ、与三郎を紹介した。「江戸生まれの江戸育ち」と聞き、お富は上機嫌だ。
しかも、美男子。与三郎はお富に見惚れたが、お富も与三郎に見惚れた。両想いだ。これが縁となり、深い仲になった二人はちょくちょく源左衛門の目を盗んでは逢瀬を重ねた。段々と大胆になり、お富は亭主のいない間に家に引っ張り込むようになる。間男だ。
三か月ぶりに我が家に帰ってきた源左衛門は松五郎を連れて湯屋に行く。松五郎が「親分の留守の間に親分の顔に泥を塗った奴がいる。姐さんに虫がついたんですよ。知らぬは亭主ばかりなり」と密告する。そして、一芝居打つことにした。急用でまた出掛けなくてならなくなった。どうしても名代を立てられない義理のある親分の花会があると嘘をつく。
お富は喜び勇んで、与三郎に「今夜来てくれ」と手紙を届ける。そして、与三郎が忍んでやって来た。源左衛門が裏木戸から様子を窺う。雨戸をピシャリと閉めて、よろしくやっている男女の声が聞こえる。源左衛門は雨戸を蹴破り、現場に乗り込んだ。「よくも俺の顔に泥を塗ったな!」と与三郎に馬乗りになる。「この顔を二目と見られないようにしてやる」。刀で全身に切るも切ったり、三十四箇所の刀傷をつけた。
お富は逃げる。松五郎が追いかけるが、海へ飛び込んでしまった。「与三さん、三途の川で会いましょう」。一方、与三郎は源左衛門がトドメを刺そうとするところで、金太郎が現れ、一命を取り留めた。血みどろの姿で藍屋へ。幸い、急所は外れていたので命が助かったのだった。この一件で、与三郎は日本橋横山町の伊豆屋へ戻る。
銀冶先生の「玄冶店」。与三郎は人に見られたくない顔になってしまい、「いっそ死んでしまいたい」と鬱々としながら、三年が経った。両国の川開き。頬被りをして出掛けた。そのときに目の前にお富そっくりな女が通り過ぎた。後をつけると、玄冶店に。女が中に入った家を格子越しに覗いていると、「何をしているんだ」と、ごろつき風の男二人が声を掛ける。「ここは俺たちのお得意様だ。新顔に荒らされたくない」と言う。蝙蝠の安五郎と目玉の富蔵だ。
「知っている女が…」と言う与三郎に、「頬被りなんかしないで、顔を見せろ」と言うので、頬被りを取ると、「お見逸れしました」。事情を話すと「切らずの与三の噂は聞いたことがある。その与三郎かい?」。そこで三人で組んで強請に行くことにする。
「どなた?」というお富の声に、安五郎が「世話になった親分の倅が顔に傷を負ってしまった。湯治に行かせたいので、草鞋銭をくれ」と言う。お富は金包みを渡すが、200文しかない。安五郎は居直り、「お前の旦那の店へ行って、大暴れしてやる!」と脅す。すると、お富は豹変し、自分は横櫛のお富と幅を利かせた芸者で、木更津の親分の女房になったこともある、お前みたいな小悪党なんか怖くもない!と啖呵を切る。
すっかり怖気づいた安五郎は「傷の兄ぃの出番だ」と与三郎を促す。与三郎がお富に言う。「もし、ご新造、私がわからないんですか」。「傷に驚いていたら、世間を渡っていけない」と言うお富。「私の声を聞いて、もう一遍、この顔をご覧よ」「あんた!与三郎さん?」「初めてわかったね」。
お富が言う。わかりましたとも、与三さん。よく生きていてくれました。死んだと思って、旦那に頼んで仏壇を拵えて、位牌に向かって朝に夕に線香をあげていたんです。二人の縁は深かったんだねえ。
安五郎が「この旦那に因縁をふっかけて、莫大な金を巻き上げよう」と言うと、「その因縁とやらは、この私が伺いましょう」という声がする。井筒屋の番頭、多左衛門だ。一部始終を聞いていたという。びっくりしたのは日頃世話になっている富蔵。ひたすら謝る。多左衛門は小判2枚を渡し、「二人で一枚ずつ。めっきり、はっきり、これっきりだぞ」。
そして、「傷のお兄さんは残ってください…与三さんだね。お富から惚気まじりに聞かされていました。死んだとばっかり思っていました。生きていたと判れば、私は身を引きます。二人で仲良くやってください」。そして、自分の心持ちだと言って、三十両を渡した…。なんとも、物分かりの良い人物だ。