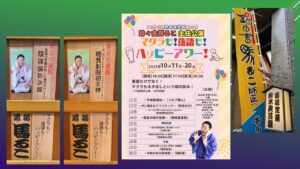けんこう一番!三遊亭兼好「淀五郎」、そしてBunkamura「リア王」

「けんこう一番!~三遊亭兼好独演会」に行きました。「狸札」「禁酒番屋」「淀五郎」の三席。前座は三遊亭げんきさんで「子ほめ」、ゲストはオペラ座の道化師のみまさんだった。
「淀五郎」。四段目で、團蔵演じる由良之助が淀五郎演じる判官に近づかないで花道から動かない理由が明確に示されていて、得心のいく高座だった。團蔵は淀五郎の芸に見所があるからこそ、相中から名題に大抜擢してまで判官の代役を任せた。淀五郎の芸が悪いのではなく、了見がなっていないのだということがよく判った。
初日の芝居が終わって、淀五郎が團蔵の楽屋を訪ねたときの團蔵の言葉。
すぐに近くに行きたい。でも、行けない。殿様が腹を切っているから傍に行けるんだ。淀五郎が嬉しそうに腹を切っているところに行けるか。どこか悪いところがありますか?良いところがあるから、悪いところを言える。どこも良いところがないのに言えるか。どのように腹を切れば良いか?本当に切ればいい。死んでしまう?下手な役者は死んだ方が良い。
淀五郎は明日、腹を切って本当に死んでしまおうと思った。そして、暇乞いに中村座の中村仲蔵を訪ねる。「花道の一件か」と察した仲蔵に、淀五郎は「團蔵親方は教えてくれないんです」と訴えるが、仲蔵は三河屋さんは親切な人だと言って、淀五郎の芝居を見る。「淀さん、すまないが私でも傍に行かれないよ。三河屋さんはちゃんと教えているよ。三河屋さんはわざわざやりにくい思いをして、見込んだ淀五郎に戻れ、早く上手くなれと言っているんだ」。
仲蔵はさらに淀五郎に言う。
名題になって嬉しいか。判官は自分の短慮から切腹に処され、御家を断絶され、悔しい。すまない、申し訳ないと思っている。何て馬鹿なことをしたんだろうと思っている。だが、お前さんは「さあ、見てください」「褒めてください」と言わんばかりの判官だ。了見を変えなさい。
そして、仲蔵自身が判官切腹をやってみせる。兼好師匠の演出ではその一言である。了見について言及しただけで、九寸五分の持ち方や手の膝への置き方、青黛を耳の裏の仕込んでおく等といって技術的なアドバイスについては省いている。
仲蔵の判官を食い入るように見た淀五郎は翌日にはすっかり判官になりきった。團蔵だけでなく、共演者が皆、「昨日までの淀五郎とは違う」と思ったという。團蔵は言う。「出来た!たった一晩で別人のようだ。不思議な奴だ…堺屋だな」。
了見の持ち方で芸が豹変する。これは歌舞伎に限ったことではないだろう。技術論より、了見。それを強調した兼好師匠の高座は見事であった。
Bunkamura「リア王」を観ました。作:ウィリアム・シェイクスピア、上演台本・演出:フィリップ・ブリーン。
ブリテンの王リアを大竹しのぶが熱演した。
老境を迎え、自ら退位を決意したリア。三人の娘に国を分割して与えようと娘たちを呼び寄せるが、長女ゴネリル(宮沢りえ)と次女リーガン(安藤玉恵)は言葉を尽くして父への敬愛を最大限に表現したが、日頃リアがもっとも愛していた末娘のコーディリア(生田絵梨花)は飾り立てた言葉を口にせず、実直な物言いに終始した。激怒したリアはコーディリアを勘当し、領地をすべて姉娘二人に分け与えてしまった。
退位後は姉娘二人の世話になりながら隠居生活を送ろうと考えていたリアだが、いずれも温かくもてなされるどころか、厄介払いされる。もはや国王の威光も威厳も通用せず、お気に入りの道化(勝村政信)だけを連れて嵐の荒野にさまよい出たリアは狂気に取りつかれていく。
舞台最終盤。リアからの勘当後、フランス王と結婚したコーディリアは、父を助けるため、フランス軍とともにドーヴァーに上陸した。再会を果たしたリアとコーディリアは真の愛情を確かめ合う。だがフランス軍はブリテン軍に敗北し、リアとコーディリアは捕虜となる…。
この物語で重要な役割をしているのは、山崎一演じるグロスター伯爵だ。王リアに仕えていたが、その苦境を知って心を痛めて領地に匿い、密かにドーヴァーへ逃がそうと画策した。しかし、ゴリネルとリーガンと通じているエドマンド(彼はグロスターの妾の子なのだが)がこれを知り、罰としてグロスターの両目を抉り取ってしまう。
プログラムの中で上演台本・演出のフィリップ・ブリーンがこう書いている。
私はおそらく、「阿呆ばかりの大舞台」に立つもう一人の道化にすぎない。(中略)自らの目を抉り取り何も見えないようにして、この「狂った」世界の中で、祝福された「正気」で生きるという誘惑に惹かれている。リアを見てほしい。リアはあれほど多くを耐え抜いた後でさえ、最後の瞬間二人の上の娘の死体が足元に横たわっているのを「見ない」ことを選ぶ。それらはコーディリアと同じようにそこにあり、同じように死んでいるのに。あまりに耐え難いために見ないことを選んだのだ。まさに人間の悲劇である。
「リア王」は、恐怖と根源的不安に揺れるこの時代に、直接的にも間接的にも語りかける。新たな「王」たちの時代において、多くの人々の目は無駄にされる。しかしシェイクスピアは、この最も暗い悲劇の中に、壊れやすいながらもひとつの希望を示している。ある種の「狂気」に宿る希望。それは、王たちが新たな虐殺に喜々として乗り出そうとするその時にこそ、「これまでのお仕えなど何ほどでもない、ここでお止めするのが一番の務めと存じます」と言えるだけの狂気である。以上、抜粋。
人間が世の中の出来事やモノを見る「目」の大切さ…それをグロスター侯爵の抉り取った両目に象徴させているのだろうか。