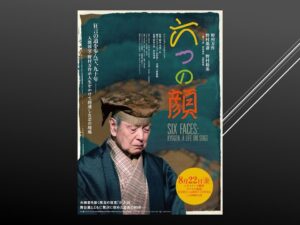両極端の会 柳家三三「手形怪談」、そして扇辰・喬太郎の会 柳家喬太郎「因果塚」
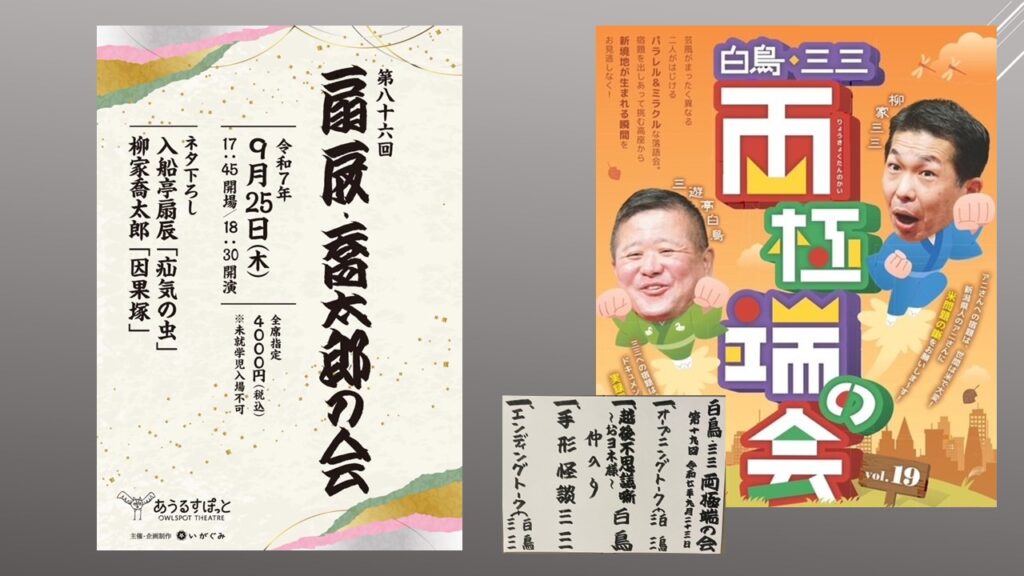
「白鳥・三三 両極端の会」に行きました。柳家三三師匠から三遊亭白鳥師匠への宿題は米問題の噺、白鳥師匠から三三師匠への宿題は実録風現代ホラーであった。
白鳥師匠が創作したのは「越後不思議噺~おヨネさま」。減反政策が盛んに叫ばれていた昭和50年代、新潟の山奥の村で爺さんが死ぬ間際に「米を馬鹿にする人間に天罰を下してください」と鎮守の森のおヨネ様に遺言を遺して死んでいった。
時代は平成となり、落語家の三遊亭Q蔵は糖尿病のために米を食べない暮らしをしていた。弟子のQ太郎と新潟のある村に二人で旅に行って道に迷ったときに出逢った婆さんが白飯をご馳走してくれた。だが、Q蔵の「米は毒だ」と言っておかわりを断る。この発言に婆さんが怒り出し大量のおにぎりを機関銃のようにぶっ放した。この婆さんこそ、鎮守の森のおヨネ様だったのだ。そして、本当はおにぎりが大好きだったQ蔵は「美味い!お米、万歳!」と目覚める。そして、このことは決して誰にも喋ってはいけないとおヨネ様に口止めされた。
時は流れ令和になる。Q蔵は亡くなり、Q太郎がある女性と結婚したが、その新潟出身の女性が実は…。奇想天外、荒唐無稽な白鳥落語の真骨頂を見た。
三三師匠が創作したのは「手形怪談」。主人公(名前は言っていなかったので、便宜上ヒルタにします)とタナカとタカハシの3人が「怖い話」をしようと居酒屋に集まった。話をするのはヒルタで、その話の途中でくだらない冗談を言ったりして話の腰を折るのがタカハシという構図だ。
ヒルタの第1話。関西のある県。峠越えのトンネルがあった。でも、3年前にバイパスができて、そのトンネルは旧道になって、あまり利用する人はいなくなってしまった。そのトンネルに時々「幽霊が出る」と噂になり、会社の仲間10人で車3台に分乗して行こう!ということになった。実際に行ってみると、入り口は綺麗に整備され、外灯も点いて明るく、「期待はずれ」の雰囲気。それでもトンネルの中に行ってみようと車を降りたが、一人の女性だけ「私、降りない。残る」と言い張るので、一人を残して9人で中へ入った。何もなかった。皆が戻ってきたら、一人残った女性が「実は降りたくなかったのではなく、物理的に降りられなかった」と言う。立ち上がろうとすると、両方の足首が何かに捕まれていたのだという。皆は思いつきの嘘だろうと思ったが、いざ解散ということになったら、短パンにサンダル姿だったその女性の足首に紫色の手形が付いていた…。
第2話。大学の先輩が夜、酔って自宅のマンションに帰ろうと、エレベーターに乗ったら、ちょうど2時22分にエレベーター内の鏡が突然真っ暗になって、それまで自分が映っていたのに、血まみれの人が鏡の中から一歩一歩近づいてきて、手を伸ばしてきた。そして、手は血に染まっていた。エレベーターはちょうど5階に着いたので、先輩は慌てて降りて自分の部屋に入った。翌朝、エレベーターに「使用禁止」の札が貼られていた。階段で一階まで降りると、業者の人がいて、「鏡に血の手形がついて、拭いても拭いても取れない」と言っている。どうも鏡の内側に血がついているらしい…。
第3話。今度はヒルタ自身の体験。3年前に取引先のある名古屋に出張に行った。緊張する打ち合わせだったので、肩が凝り、ホテルにチェックインするときにマッサージを頼んだ。混み合っているので夜遅くなると言われたが、それでも頼んだ。疲れていたので、ベッドでウトウトしていると、ドアを叩く音がしたり、ガチャガチャとドアを開ける音がしたり、ピンポーンとチャイムを鳴らす音がしたりしたが、「どーぞー」と反応はしたものの、疲れてすぐに寝入ってしまう。そのうち、ドアが開いて、ジトジトというカーペットを踏みしめる音がした。明らかにベッドの自分に近づいているようだ。自分の右、そして枕元、さらに左から足音が聞こえる。だが、左側はすぐ壁でスペースはない。おかしい。そのうち、シーツを撫でる音が聞こえ、耳元で「いかがします?」という声がした。驚いて起き上がると、それまでの物音は一切消えて、自分は全身ビッショリと汗をかいていた。そして翌朝。右耳の横に手形が残っていた…。
これらの話を聞いていたタカハシはトイレに行く。タナカがヒルタに「よくあんな体験して平気だな」と言うと、ヒルタは「嘘だよ。全部作り話だよ」。だが、トイレから戻ってきたタカハシの頬に紫色の手形が…。それを指摘すると、タカハシは慌ててトイレの鏡で確認し、「何もないじゃないか!」。ヒルタは「何か悪いことが起きる予兆かもしれないから、気をつけて帰れよ」と言って別れた。
それでもタカハシのことが気になったヒルタはタカハシに電話したとタナカに言う。「何もなかったけど、かみさんが女で遅くなったんでしょうと言って、往復ビンタされたよと笑っていたよ」。すると、タナカが「それが一番怖い。タカハシのかみさん、去年亡くなったよ」。
一つ一つの怪談も優れているし、それをヒルタとタカハシの掛け合いで巧みに構成している。そして、見事なサゲ。三三師匠の創作能力の高さに舌を巻いた。
扇辰・喬太郎の会に行きました。入船亭扇辰師匠が「疝気の虫」(ネタおろし)と「ねずみ」、柳家喬太郎師匠が三遊亭円朝師匠作「離魂病」より「和国楼」~「因果塚」(ネタおろし)だった。開口一番は入船亭辰むめさんで「弥次郎」だった。
喬太郎師匠はまず一席目「和国楼」で、花里花魁と深川大芳の若棟梁・伊之吉の駆け落ちを描く。海軍の海上渡に350円で身請けされることが決まった花里だが、板頭で姉のような存在の小主水花魁が花里に「本当は了見していないね。お前、死ぬつもりだろう」と見抜かれ、「贅沢だ。目障りだ。死んでおしまい」と海に突き落とす。すると、船で待機していた伊之吉が花里を救い、大海原へと船を漕いで二人は逃げていく。実は小主水の指図によるものだったと花里は伊之吉から知らされる。駆け落ちを応援していたのだった。
そして、二席目「因果塚」。菅野伊之助は神奈川で百姓をしている育ての親である甚兵衛夫婦のところにお若と二人、駆け落ち同然に身を寄せた。それから20年が経ち、二人の間に生まれた息子・岩次は18歳になる。お若と伊之助はずっと気に掛かっていたことがあった。20年前にお若の伯父、下根岸の高根晋斎に無断で駆け落ちをしてしまったことだ。まだ生きているのであれば、謝りたいと二人は考え、岩次を伴って江戸へ出る。
まずは二人を仲介した下谷に住む鳶頭の勝五郎のところへ挨拶する。勝五郎は伊之助が生きていたことに驚くが、それ以上に伊之助と夫婦になったお若がそこにいることに驚く。それでも勝五郎は承知して、親子三人を高根晋斎にところに引き合わせに行く。高根も勝五郎から話を聞き、信じられない様子。というのも、根岸の高根宅にお若はこの20年、ずっと気鬱を患いながらも同居しているからだ。
「兎に角、会ってみよう」。お若、そして伊之助が20年前に無断で駆け落ちしたことを謝罪する。「顔をよく見せなさい」。確かに、お若である。高根は奥にいるもう一人のお若に声を掛ける。「お若、出て来なさい」。二人のお若が揃った。瓜二つである。高根は考えた。書物で読んだことのある「離魂病」ではないか。魂が抜けだし、もう一人の自分に乗り移るという。この病は二人が顔を合わせると、24時間以内に生命を終えると書かれていた。どうしよう。
家の外で言い争いが聞こえる。廓の若い衆三人と男女だ。事情を訊くと、「品川の和国楼から足抜け」をしたのを捕まえたのだという。高根は若い衆に「逃がすようなことはしない」と約束し、その男女を呼び寄せて話を訊く。男は深川の大工の棟梁、芳太郎のところの若棟梁の伊之吉。女は花里という花魁だった。
さらに詳しく訊くと、伊之吉は芳太郎のところに養子として引き取られた。また、花里は大坂の越前屋佐兵衛のところに養子として引き取られたが、両親が死んでしまい、品川へ流れたという。そして、本名はお米という。伊之吉とお米は同い年だった。
高根は確信した。伊之吉とお米は、お若が狸の種を宿し生まれた双子だったのだ。しかも「お前たちを産んだのはこの私」と二人のお若が口にする。因果の歯車というのは、どこまで幸のないものなのか…。和国楼に若い衆に350円を渡し、高根はお米を身請けした。
しかし、伊之吉とお米は「愛し合った者同士が双子、それも狸の子とは…私たちも畜生同様」と儚み、「この世では所帯を持てないが、あの世で夫婦になろう」と綾瀬川に身投げした。
そして、二人のお若も刻々と命の期限が迫る。ニコニコしていたお若だが、その姿が次第に薄くなっていき、煙のように消えた。そして、もう一人のお若が目を瞑って倒れた。その様子を伊之助と岩次は見守った。伊之吉とお米が千住大橋でどざえもんで見つかったという報せが届く。錯乱した伊之助は松の木に首を括って自害した。
岩次は高根晋斎に言う。「こんな田舎者ですが、菩提を弔いたい。力になってください」。岩次は出家し、塚建立の費用捻出のため諸国を行脚し、2年後に因果塚を建立した。そして、岩次は八十四歳の長寿で亡くなったという…。三遊亭円朝師匠らしい因果因縁の噺がここに完結した。喬太郎師匠、ありがとうございます。