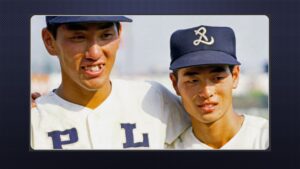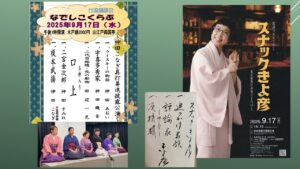【ファミリーヒストリー】落語家 立川志らく

NHK総合テレビで「ファミリーヒストリー 立川志らく」を観ました。今年、芸歴40周年を迎えた落語家の立川志らく師匠の先祖を辿るドキュメンタリーを興味深く拝見した。
本名・新間一弘、昭和38年8月生まれ。父の英雄と母の富士子は90歳と84歳でともに健在だ。まずは英雄の父、志らくの祖父である深谷伊三郎が日本の鍼灸師の中で権威であったことに驚かされた。
明治33年に東京市麹町区中六番町、現在の千代田区番町に栄太郎の長男として生まれた。明治4年創立の番町小学校の同窓会名簿に、深谷伊三郎の名前が大正2年卒業、男1組として記載されていた。この辺りの子どもは裕福な屋敷住まいが多く、人力車で通う子もいて、俥夫の待機場所が用意されていたという。
だが、伊三郎は小学校を卒業すると、奉公に出されてしまう。本郷の箱を作る店だった。小学3年生のときに母が亡くなり、父の栄太郎は後妻をもらったために奉公に出されたそうだ。だが、伊三郎は大正13年に日本大学専門部法律科に入学する。日本法制学会の普通文官養成講義録で通信教育を1年間受けた者は無試験で大学に入学できる制度を利用したのだった。
しかし、入学の2年後に世界恐慌、その後の昭和恐慌と就職することが難しい時代になってしまった。伊三郎は何か社会貢献できることはないかと考えたとき、入学前に肺結核を患って東洋医学の灸による治療をしたことを思い出し、鍼灸師になる道を選んだ。当時としては極めて稀な例だったが、伊三郎は後世に名を残す鍼灸師になる。人体に触れる熱さをやわらげようと、竹筒による灸熱緩和機を考案し、実践した。今でも月一回開かれる深谷灸法勉強会では、この竹筒による灸法が伝承されている。
伊三郎は試験を重ねて客観的データを取り、その研究成果を発表する鍼灸治療雑誌を発刊、謄写版による印刷技術を習得し、製本までした。昭和10年に英雄が誕生。好きなことをとことん極める伊三郎の影響を受け、英雄はスペインのギタリスト、アンドレス・セゴビアに心酔し、音楽の道を志した。
当然、父の伊三郎は反対した。だが、英雄はそれを押し切り、プロのギタリストになる。そして、英雄のギター教室に通って来た、浜松出身の女性に一目惚れする。その女性こそ、新間富士子である。新間家は反対したが、猛烈な英雄の情熱に折れ、富士子の父である新間明が「新間姓を名乗る」ことを条件に、結婚を認めた。昭和37年のことである。そして、長男の一弘(志らく)、次男の清登が誕生した。
伊三郎は英雄のリサイタルを観に来て、こう言ったという。お前が一人前の音楽家であることがわかった。この人たちを失望させないように努力しなさい。伊三郎は昭和49年、74歳で亡くなった。
志らくの母、富士子の祖父、新間金三郎は静岡県敷知郡浜松町八幡地に安政5年に生まれた。明治22年の浜松町議会議員名簿に金三郎の名前が載っている。当時は直接国税を15円以上納めている日本人男子のみに選挙権が与えられる制限選挙だった。静岡県の人口の僅か1%、111人に1人、21戸に1人という割合だった。
金三郎の長女、好子は西遠女子学園で学んだ。4年制の高等女学校である。大正13年3月の卒業アルバムに写真と名前が載っていた。好子と同級生だった川井かつゑの兄である川井明が好子を気に入り、アタックしたが失敗に終わる。だが、このことが後に運命の人となるから不思議である。
好子は女学校卒業後の大正14年に加藤通彦と結婚。新間姓を名乗る。浜松駅前の遠州自動車商会などに土地を貸し、生計を立てていた。だが、昭和4年に通彦はチフスを患い、急死してしまう。三人の幼子を抱え、路頭に迷っていた好子に再び求婚したのが川井明だった。
明は川井林平の長男として生まれた。浜松蒲村(後の丸塚町)で一、二を争う土地持ちで、農業を営んでいた。明は浜松中学(現在の浜松北高校)を卒業し、東京に出て、中央大学専門部法科を卒業した。林平は当然稼業の農家を継ぐものと考えていたが、明は「好子と結婚したい」と親の反対を押し切り、家を出る。戸籍には「明ヲ指定家督相続人排除」と記され、半ば勘当という形で好子と結婚する。そして、昭和16年に富士子が誕生した。
明と好子の夫婦は空襲に遭った浜松の地で、戦後は白木屋という旅館を開業する。昭和32年に開かれた浜松国体では一泊二食で800円から1000円で部屋を提供した。芸事が好きだった好子は旅館の部屋を利用して、踊りや三味線の稽古をする教室を開いた。昭和44年、明は64歳で亡くなる。
志らくの父、英雄はギタリストとして才能を開花させる一方で、多くの趣味を持った。けん玉やダーツはその専門書を刊行するほどの凝りようで、志らくも幼少時代はけん玉で腕を上げたという。英雄が持っていた落語全集のレコードがきっかけとなり、「ドリフターズより面白い」と志らくは落語に傾倒するようになる。
母の富士子も専業主婦では飽き足りず、長唄三味線を専門的に習った。弟の清登も40歳でサラリーマンを辞め、ギタリストに転向した。「やりたいことをとことんやる」というDNAが新間家に流れていたのだ。
昭和57年に日本大学芸術学部に入学した志らくは大学4年生のときに立川談志に入門、大学を中退して好きな道に邁進した。昭和63年に二ツ目に昇進したとき、黒紋付を贈ってくれたのは母方の祖母である好子であった。クリーニング屋に出すと、「150~200万円する」高価なものだと判った。その好子も平成5年に88歳で亡くなった。
やりたいことをとことんやる。立川志らくの落語にかける情熱の原点が、祖先を辿ると見えてきた。面白い番組だった。