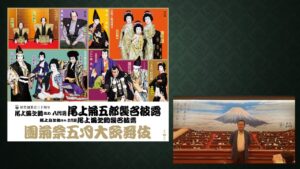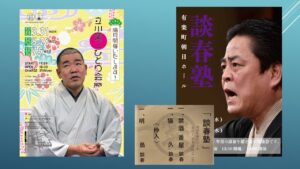桃組公演 林家つる子~蝶花楼桃花「ねずみ」リレー

浅草演芸ホール五月下席七日目夜の部に行きました。今席は桃組公演、蝶花楼桃花師匠が主任を勤め、出演者全員が女性芸人という特別興行だ。そして、今回の目玉はつる子師匠→桃花師匠の「ねずみ」のリレー落語である。
「寿限無」翁家丸果/「転失気」古今亭雛菊/「加賀の千代」古今亭佑輔/余興 桃花・小梅/「マキシム・ド・呑兵衛」三遊亭律歌/「そば清」古今亭駒子/粋曲 柳家小春/「でもね」神田茜/「初天神」古今亭菊千代/奇術 松旭斎美智・美登/「熊の皮」三遊亭歌る多/中入り/「匿名主婦只野人子」弁財亭和泉/漫才 ニックス/「あくび指南」柳亭こみち/三味線漫談 林家あずみ/「ねずみ」(上)林家つる子/「ねずみ」(下)蝶花楼桃花
つる子師匠。冒頭、客引きをしていて居眠りをしてしまった卯之吉の夢が良い。母の病床に食事を運び、「早く元気になって、お父っつぁんと三人でお寿司を食べに行こうよ」と気丈に母を励ます優しい子どもであることが伝わる。居眠り中の卯之吉に旅をしていた左甚五郎が声を掛け、鼠屋に泊まるきっかけとなる。
布団もない、食事の用意も出来ない、奉公人もいないのに、なぜ旅籠をしているのか。甚五郎に主人の卯兵衛は「訳があるのだろう。聞かせてくれ」と言われ、「肚の底まで見透かされていますね。まあ、年寄りの愚痴を聞いてください」と言って、以前は仙台一大きな旅籠、虎屋の主人だったと明かす。
三年前に女房に先立たれ、後添えに女中頭のお紺を迎えた。七夕祭りで宿泊客が賑わっていたとき、二階で客同士が喧嘩をはじめ、その仲裁に入ったら、梯子段の下まで突き落とされ、腰を打って、抜けてしまった。医者には二度と立てないと言われた。それで宿のことはお紺と番頭に任せ、物置小屋に住まうようになった。それがある日、知人の生駒屋が「どういうことだ?」と言って、飛び込んできた。生駒屋からあんな話を聞くとは夢にも思わなかった。
「その生駒屋の話は桃花師匠が続けます」と言って、高座のバトンを桃花師匠に渡した。
生駒屋は訊く。なんであんな馬鹿な真似をしたんだ。虎屋を番頭に譲ったそうじゃないか。「この旅籠を譲るものなり」と書いた証文に、印形が押してある。見せてもらった。印形はお紺に預けてある?お紺と番頭は出来ているんだ。お紺は「あんな腰抜けの面倒なんか見てられるか」と言っていると卯之吉が俺に泣きついてきた。それからは三度三度の食事は生駒屋から廻しているんだ。
卯之吉の体を見たことがあるか?この痣や傷はどうした?と卯之吉に訊くと、「金ちゃんと喧嘩した」。なぜ、そんな嘘をつくんだ!と怒鳴ると、「おっかさんはなんで死んだんだ?!」。帳場の金が合わないと言って、お紺と番頭が卯之吉に濡れ衣を着せて、折檻していた。卯之吉は生駒屋さんにもうこれ以上心配かけさせられない、世話になっているわけにいかない、旅籠を始めようと思うと言った。もらい泣きした。父親と二人で旅籠をやって、お紺と番頭を見返してやるんだ!と卯之吉は天国の母親に誓ったのだ。
甚五郎は、卯兵衛の腰が抜けたのをいいことに、お紺と番頭が虎屋を乗っ取ったことを知り、まさに「飼い犬に手を噛まれた」深い事情を知った。鼠屋という名前は、物置小屋の主だった鼠に義理立てしたということも判り、何とか卯兵衛と卯之吉を救ってあげたいと考えた。「木っ端はありませんか。少しでも多くの泊まり客が来るように、鼠を彫りましょう」。
卯兵衛が宿帳をつけ、この旅の男が名人の左甚五郎だと知るが、甚五郎本人は「名人?よしておくれ。それで扱いが変わるのは嫌だ」と返したのが、いかにも謙虚な人柄を表していて良い。どんなに金を積まれても、気持ちの乗らない仕事はしない。それこそが名人肌。自分の出来ることで人助けをしたいという甚五郎の優しさが出ている。
左甚五郎作、福鼠。盥の中で動く木彫りの鼠は評判を呼び、近郷近在から多くの客が押し寄せた。それに反して虎屋の経営が左前になる。お紺と番頭は飯田丹下に依頼し、虎を彫ってもらった。この虎を見て、甚五郎と二代目政五郎が口を揃えて「それほどの虎じゃない。目に恨みを持っている」と言った。それはとりもなおさず、お紺と番頭の了見そのものだったといえよう。
つる子師匠、桃花師匠によるリレー落語「ねずみ」、お見事だった。