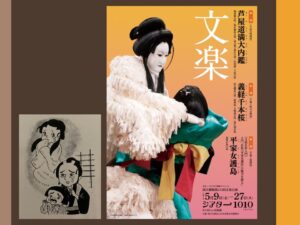志の輔noにぎわい 立川志の輔「ねずみ」、そしてケムリ研究室「ベイジルタウンの女神」
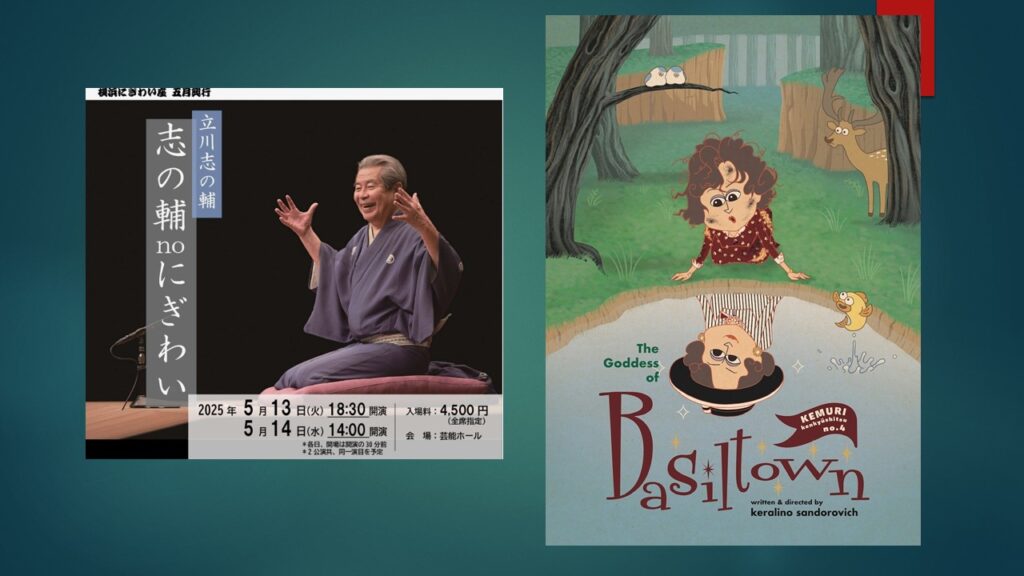
「志の輔noにぎわい」に行きました。「ちりとてちん」と「ねずみ」の二席。ゲストは玉川奈々福先生で「牧野弥右衛門の駒攻め」、曲師は広沢美舟さんだった。開口一番は立川志の彦さんで「千早ふる」だった。
「ねずみ」。左甚五郎が鼠屋に泊まることになり、「この宿は泊まった者が一家を養う仕組みになっているんだね」と言う台詞が優しく感じた。釈迦に説法かもしれないが、旅人が一番楽しみにしているものは「提灯の灯」、二番目が「女中さん」だという。旅の疲れを癒してくれるからだ。それなのに、この宿にはそれがない。なぜ、宿をやっているのか。何か特別な事情があるのだろうと思った甚五郎が優しく「酒が来るまでの繋ぎに聞かせておくれ」と主人の卯兵衛に問いかける形で身の上話がはじまるのが良い。
以前は仙台一大きな宿屋、虎屋の主人だった。三年前に女房に先立たれ、後妻に女中頭のお紺を迎えた。七夕祭りで満員の宿で客同士の喧嘩があり、仲裁に入ったら、二階から下に突き落とされ、腰が抜けてしまった。その後、宿屋は番頭の丑蔵とお紺が切り盛りしていたが、息子の卯之吉に継母であるお紺が暴力を加えていることが判り、納屋に父子二人で移り住んだ。印鑑を預けていたのが仇となり、宿屋を丑蔵とお紺に乗っ取られてしまった。以来、三度の食事は旧知の生駒屋が面倒を見てくれた。
だが、卯之吉は「自分たちで稼いで、自分たちで食べていこうよ」と、宿屋を始めたいと言い出した。私がうんと言っていないのに、お客を連れて来た。「この子が泊まってくれと言うから来た」という“お客様”は、翌朝には「こんなにゆっくり眠れた宿はないよ」と言ってくれた。以来、月に5、6人のお客様を泊めている。
甚五郎は「辛い話をさせて済まなかった」と言って、御礼に何か彫りたいから木屑があったらくれないかと頼んだ。「一人でも多くの方が泊まれますように」という願いをこめて彫るという。元は納屋だったので、鼠に義理立てして「鼠屋」という名前にしたという卯兵衛の優しさに共感し、福鼠を彫ったという。土間の隅に盥を置き、中に鼠を入れて、「左甚五郎作 福鼠」と看板を立て、甚五郎は去って行った。
木で彫った鼠が盥に中で動いている!評判は広がり、収入は増え、「多くの人たちに見てもらいたい」と建て増しを繰り返し、とうとう仙台一大きな宿になった。腹の底が煮えくり返っているのは虎屋の丑蔵とお紺である。甚五郎のライバル、飯田丹下に虎を彫ってもらい、睨みをきかせた。福鼠は途端に動かなくなってしまった。
このことを手紙で知って駆け付けた甚五郎が鼠と会話するところが良い。「俺はお前に命を吹き込んだ。魂を入れたつもりだ」「どうも、親方。お久しぶりです」「お前に皆がガッカリしている。あんな虎に怯えるように拵えたつもりはなかった。なぜ、動くのをやめたんだ?」「虎?あれ、猫だと思った」。魂をこめる名人・甚五郎が優しくて、愛嬌のある人物として描かれている良い高座だった。
ケムリ研究室「ベイジルタウンの女神」を観ました。作・演出:ケラリーノ・サンドロヴィッチ
大筋はこうだ。緒川たまき演じるマーガレットは大企業ロイド社の社長として貧民街のベイジルタウンの再開発を目指している。第8地区と第9地区は所有しているのだが、第7地区を買収したいと考え、所有者であるソニック社の社長タチアナ(高田聖子)と交渉する。タチアナが提案したには“ある賭け”だった。マーガレットが一カ月間、無一文で正体を明かさずにベイジルタウンで暮せたら、第7地区は譲る。だが、途中で断念したら、第8地区と第9地区をタチアナが貰うというものだ。マーガレットはその賭けに乗り、ひょんなことから出会った王様という渾名の乞食(古田新太)、ハムという渾名の乞食(水野美紀)の兄妹のバッラクに居候することになるが…。
時間の経過とともに、マーガレットはベイジルタウンに暮らす乞食たちと心が通じ合う。これがこの芝居の最大の肝だ。
パンフレットに「自己再教育としてのなりすまし」と題して、評論家の荻野洋一氏が以下のように評している。
マーガレットの高慢さや気取った態度はベイジルタウンの住民たちの困惑を掻き立てはしても、それがシリアスな階級対立に発展しないどころか、憎めない「キチガイ」として、かえって彼女がある一定の人気(?)を博していく点は、本作の喜劇の粋たる所以だろう。
彼女に名づけられた「チキン」というみすぼらしくも愛すべきあだ名は、そのまま乞食たちの寛容さを示し、カルチャーギャップコメディにとどまらず、フランク・キャプラ流の人民喜劇の色もにじませている。(中略)
「ミイラ取りがミイラになる」ような形をもって自己再教育を図る。マーガレット・ロイドはベイジルタウンでの貧窮生活から少女時代の純粋さを取り戻すヒントを得、また同時に資本家階級としての自己のあり方を再審に付すための知見も獲得する。以上、抜粋。
KERA氏に「そんな難しいことを考えずに、喜劇として楽しんでくださいよ」と言われそうだが、僕自身は喜劇を大いに楽しめたし、本当に細部にわたって笑いを計算した演出をされているなあと感心した。その上で、だ。資本家と乞食の交流を通して、マーガレットがこれまでの価値観や偏見を見直し、実に“人間的な”魅力ある女性に成長する物語だなあと思った次第だ。
ケムリ研究室のシリーズは第2回「砂の女」、第3回「眠くなっちゃった」、そして今回(第1回の再演ではあるが僕は初見)と観てきて、KERA氏と緒川たまき氏のコンビネーションに感服したのだった。