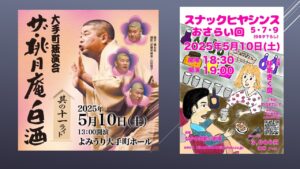立川吉笑独演会「声飛脚」「井戸の茶碗」、そして渋谷らくご 田辺いちか「玉川上水の由来」立川笑二「お直し」

「二ツ目最終章 立川吉笑独演会」に行きました。「ぷるぷる」「声飛脚」「井戸の茶碗」の三席。
「ぷるぷる」。松ヤニを舐めてしまったために唇がくっ付いてしまった八五郎が、大家を訪ねたのは「恋の相談」というのが可笑しい。ぷるぷるさせながら、「好きな人ができました」と言う八五郎に対し、大家が「その前に唇を元に戻すことが先だろう!」。堪らない。
「声飛脚」。手紙を運ぶ飛脚“紙飛脚”の手間賃が暴落し、8割は将棋というのが、まず可笑しい。「三二金」とか「一四歩」とか、次の手を運んでもらって対局をするという…。「お客様の思いを運んでいる」という使命感はどこへやらで、もしかしたら埋蔵金の在り処が書いてあるかもしれないと、飛脚はまず中味を見てしまう。
今では“声飛脚”に取って替わられているというのも愉しい。上方の旦那から江戸の番頭へ「前掛けの件。見つかった。疑った私が悪かった。今度、一緒に飲もう」という温かいメッセージを声真似含めて飛脚が代行して運ぶ。「葱と一緒に炊いたら柔らかくなるよ」は一体何が柔らかくなるのか気になる。ポチの鳴き声だけだったり、落語一席まるまる三か月かけて覚えて伝えたり。一体、どんな目的で飛脚に思いを託しているのだろうと考えると面白い。
「井戸の茶碗」。千代田卜斎が屑屋の清兵衛に紙屑を引き取って貰い、「七文」と言われたときに正直に「それでは足らない」と貧しい暮らしを包み隠さずに訴え、仏像を引き取ってくれないかと頼むところに好感が持てた。普段は目が利かないから紙屑以外は扱わない清兵衛だが、千代田氏を何とかしてあげたいという気持ちから200文で引き取るところに情を感じる。
仏像の台座から50両が出て、仏像を買った高木作左衛門が千代田氏に金子は返却してほしいと依頼を受けた屑屋清兵衛が千代田氏を訪ねるが…。300文で仏像が売れたので100文の儲けの半分を受け取ってほしいと言うだけで、「浪人はしていても武士の魂は捨てていない。武士の心は錆びていないつもりだ」となかなか受け取らず、ようやく「見ての通りの貧乏暮らし。50文は助かる」と受け取ったが、50両については「わしの目が節穴だった。子孫困窮の折りに使えというものだったのかもしれないが、わしはそれを売り払ってしまったのだ。そんな施しを受ける筋合いはない」と拒む。
大家が仲に入り、千代田、高木に20両ずつ、清兵衛に手間賃として10両という妥協案を提示するも、千代田氏は頑なである。そこで、大家が偶々目に止まった茶渋のついた茶碗を20両のカタにしたらどうかと提案し、ようやく千代田氏も折れる。だが、その茶碗が関ヶ原の戦い以来行方知らずとなっていた青井戸の茶碗と判明し、細川の殿様が300両で買い上げた。半分の150両は高木氏が受け取ることにしたが、問題は千代田氏だ。
150両を持って来た清兵衛が丁寧に説明するも、武士の魂云々と言って受け取りを拒み、挙句には「お崎!刀を持て!」。正直者の清兵衛もこれにはキレた。「千代田様の言うことは立派。でも、返すのだったら、自分で返せよ!」。これを聞いて、千代田氏は目が覚めた。「自分のことしか考えていなかった」。
そして、150両を受け取る代わりにと言って、娘のお崎を高木氏の嫁に貰ってくれないかと提案する。娘の様子が最近おかしい。お父様に似て、真っ直ぐな高木様に会ってみたいと言う。どうやら、高木様に惹かれているようだ。この理屈はとても良いと思った。娘をモノとして扱うのではなく、娘の恋心を大切にするという演出が素敵だなと思った。
配信で「渋谷らくご ふたりらくご」を観ました。田辺いちかさんが「玉川上水の由来」、立川笑二さんが「お直し」だった。
いちかさんの「玉川上水の由来」。庄右衛門と按摩・松の市の心の通う会話が良い。庄右衛門は神田上水では足りなくなった江戸の生活用水を何とかしたいと考え、百姓の身分でありながら、お上に計画書を提出して採用された。だが、当初の目論見通りに工事は進まず、幕府から預かった資金は底をついてしまった。仕方なく自分の身代を売り払って進めたが、これでも足りない。工事は幡ヶ谷まで来ており、九分は済んでいるが、あと一分が残ってしまい、人足に払う給金が滞ってしまった。あと300両は必要だという。
松の市が自分の身の上話をする。四歳のときに煮え湯を浴びて目が瞑れた。捨て子をされ、拾って育ってくれたのが先代の松の市という按摩だった。十歳のときに先代が流行り病で亡くなり、自分が名前を継いで按摩になった。幕府に金を納めると人間並みに扱ってくれると聞いた。千両で検校、三百両で座頭になれるというので、女房も持たずに稼いでは貯め、三百両が貯まった。来春には座頭になれると喜んでいる。
そこに資金繰りに走っていた弟の清右衛門が帰って来て、「どこへ行っても駄目だった」と言う。庄右衛門は松の市に祝い金だと一両を渡し、帰す。「旦那、真っ直ぐに道を歩いたら、神様は見捨てないですよ」と言い残して、松の市は去った。
庄右衛門と清右衛門の兄弟は幡ヶ谷に行き、人足頭の吉五郎に「金は出来なかった。私たちを打つなり、叩くなり、殺すなりしてくれ。だが、ここまで作った水路は埋めないでくれ」と頭を下げる。すると、そこに届け物があった。按摩が包みを渡したという。50両の切り餅が6個、300両だ。庄右衛門は「松の市さんだ。お借りしよう。後日に返済して御礼を言えばいい」。
果たして、羽村から四谷大木戸まで、武蔵野台地43キロの玉川上水が完成した。庄右衛門と清右衛門は玉川の苗字を許され、旗本200石となった。玉川兄弟は松の市の行方を捜し、検校の位を授けようとしたが、見つからなかったという。玉川上水という偉業の陰には一人に按摩の心意気があったという…。素敵な読み物である。
笑二さんの「お直し」。物語の発端は、お茶を挽いてばかりいる夕霧を見るに見かねて、旦那が若い衆の半次に「夕霧の気を盛り立ててあげるように面倒を見てやってくれ」と頼んだことにした工夫が良い。「優しすぎるのは良くない」と言われていたものの、所詮男と女。吉原のご法度を犯して深い仲になってしまう。旦那は見て見ぬふりもできず、二人を呼び出すと、半次は「一緒になりたい。身請けしたい」と言う。夕霧には50両の借金が残っていたが、半次の情熱を買い、証文を巻いて、親許身請けということにして、夫婦にしてやる。旦那は「半次は馬鹿で真っ直ぐだ。生かすも殺すも女房次第だよ」と言うが…。
夕霧は本名のお崎という名でおばさんとして働き、半次は今まで通りの若い衆。真面目に働くと豊かになり、仕事にも張り合いが出て来る。だが、駄目なのはいつも男だ。千住で遊び、居続けをして、仕事に来ない。そのうちに博奕に手を染め、借金の山を作る。お崎もそうそう言い訳が続かず、店をやめることになる。
「どうするんだい?」。半次は熊から「蹴転(けころ)をやってみないか」と誘われたことを話す。若い衆は俺がやる。女の子はお前がやれ。以前はやっていたろう。お崎が訊く。「私にそんなことをさせて平気かい?」「平気じゃないよ」「平気でないと困るんだ。線香の本数を増やすために、客を引っ張るのが仕事。焼き餅を妬いたら駄目なんだよ。できるかい?」「できるよ」。お崎が言う。「お前さんが女遊びや博奕をしていたのは知っていた。止めなかった私が悪い。でも、お前さんは命の恩人。身請けすると言ってくれた。だから、意見ができなかった。でも、これからは言いたいことは言わせてもらうよ」。
無理やり引っ張り込んだ酔っ払いの客。「あんなまともな女がいるんだ。看板?酷い女が後から出てくるんじゃないのか」「さっきから呼んでいるんだ。こっちへいらっしゃいよ…冷たい手をして、どこで浮気をしていたんだい」「お前こそ、なんでこんなところにいるんだ。お前みたいないい女がどうしてここにいるんだ」「お前さんが来るのを待っていたんだよ」「惚れている男はいるんだろう?」「さっきからここにいるじゃないか」「お前さえ良ければ一緒にならないか」「借金があるんだよ」「いくらだ?」「50両」「それっぱかりでいいのか。明日にも支度できる。一緒にならないか」「まあ、嬉しい」「こんなところで女房が見つかるとは。仲良くしような」「たまには喧嘩もしたいね。打っておくれ。好きな人に打たれるとゾクゾクするんだよ。半殺しにされたいね…手を貸して…ねえ、ドキドキしているだろう?」「明日、来るから待っててくれ」「きっと来ておくれよ」。
半次は何度も「直してもらいなよ」と声を掛けたが、帰る客から勘定を取るのを忘れている。「やってられないや。あの野郎と一緒になるのか?半殺しにされたいのか?…妬いてねえよ。嫌な気持ちがするんだ。あの男と一緒になるのか」。呆れたお崎が言う。「この商売よすかい?そうかい、よそう、よそう。焼き餅は妬かない約束だった。私だって、やりたかないんだ。でも二人で一緒にいるためにやっているんだ」。夫婦の情愛がここに出る。
そして、ここまでの噺が旦那が喜助に話していたことだったという…。「今の俺(半次)があるのは、皆あいつ(お崎)のお陰だ」。半次が大見世の旦那に出世して、女将さんは当然お崎だ。悲惨な廓噺をハッピーエンドという形にした笑二さん、流石である。