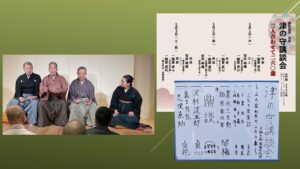玉川太福月例独演会「地べたの二人 鼻」、そして真山隼人ツキイチ独演会「御霊文楽座 心の肩衣」

玉川太福月例木馬亭独演会に行きました。
「浪花節じいさん」玉川き太・玉川みね子/「隣の席」「地べたの二人 鼻」玉川太福・玉川鈴/中入り/「粗忽の使者」玉川太福・玉川みね子
「隣の席」は太福先生が得意とする身辺雑記浪曲。玉置浩二のオーケストラコンサートを観に福岡まで出掛けたときのことを愉しく唸る。聴き手がコンサート会場にいるような気分にさせる話芸は流石だ。特に隣の席に座っていたベレー帽をかぶった物静かな老紳士の一挙手一投足がとても気になったというところ、ユーモアを交えて描写するのがとても面白かった。
「地べたの二人 鼻」は芥川龍之介「鼻」を原作として、「地べた」シリーズに置き換えた創作だが、太福先生もおっしゃっていたが「芥川ファンが聴いたら怒るかもしれない」。原作と断らなくてもいいような気がするストーリーだ。
ある日、齋藤さんの鼻が朝起きたら15センチほど伸びていた。痛くないという。金井君はある衝動に駆られた。触ってみたい…。齋藤さんは気軽に「触る?」「いいんですか?」「いいよ。目を瞑るか?開いた方がいい?薄目?…」「失礼します…結構、柔らかい!」。
齋藤さんは耳鼻科、整形外科、大学病院などに診察してもらったが、医師は首を傾げるばかり。原因不明で、「様子を見ましょう」。それから、一週間。マスク社会だから違和感はないが、飲食店には入りづらいという。「物理的に…麺類、特に熱いものは駄目」と思っていたが、左手で鼻を持って食べればいいと気づく。でも、「レンゲは使えませんね」。
金井君がインターネットで解決法を見つけてくれた。鼻を茹でて、踏む。鼻から油のようなものが出るから、それを毛抜きで抜く。齋藤さんが訊く。「逆に伸びないか?」。兎に角、やってみましょう!となり、カセットコンロを持ってきて湯を沸かし、熱湯に鼻をつける。そして、引き揚げて、齋藤さんが床に寝そべり、金井君が足で鼻を踏みつける。油のようなものを毛抜きで抜くと、何と鼻が縮まった!
「助かったよ」と御礼を言う齋藤さん。熱々の鉄板ハンバーグをご馳走してくれた。鼻がなぜ伸びたのか。原因は不明だ。だが、金井君は密かに「また鼻が伸びてくれないか…あの踏みつける快感が忘れられない」と思っている。「地べたの二人」のシリーズの新機軸を見た。
「粗忽の使者」は落語浪曲で、大西信行脚色。昭和51年に師匠福太郎が口演した高座の録音が見つかり、台本もあったので演じることにしたという。落語がベースだが、浪曲らしく人情噺っぽい演出が良かった。
使者の口上を忘れてしまった地武太治部右衛門は切腹して詫びるという。この話を聞いた大工の留公が「指先に力量のある者」として名乗りを挙げ、田中三太夫に席を外してもらったときに治部右衛門に言う台詞が浪花節だ。
親にもらったこの命、粗末にはしないぞ、腹を切って武士の面目は立つかもしれぬが、親の立つ瀬はどこに立つ。馬鹿な子ほど親は可愛い、死んだその後、おふくろさんが春が来るたび思い出して泣くだろう。
それゆえに治部右衛門の尻をひねりに留公が名乗りを挙げたというのだ。実際、指先ではなく釘抜きで堅い尻を思い切りひねることで治部右衛門の命は助かった。落語の滑稽噺も浪花節になると人情味が増す。面白い。
真山隼人ツキイチ独演会に行きました。「イニシャルD」「善悪二人小僧」「御霊文楽座 心の肩衣」の三席。曲師は沢村さくらさん。
「イニシャルD」はエッセイ浪曲。先月のツキイチ独演会終演後に20時12分発の新幹線で大阪に帰らなくてはいけなかった。翌日の朝早い会をブッキングしていたことに気づいたのだ。ツキイチ独演会が金曜日開催だったので19時開演。間に合わないといけないので、20時30分に終演して、速攻で後片付け、着替えをして、タクシーを拾って上野駅に行き、上野東京ラインに20時54分に乗る計画だったが…。タクシーの運転手がもたもたして、上野駅に着いたのが20時54分。万事休す!と思ったら、上野東京ラインが4分遅れの運行だったために助かったという…。イニシャルDのDはダブルブッキングのDだとか(笑)。
「善悪二人小僧」。両替商の亀屋清左衛門の丁稚、与之吉は十三歳にして主人を暗殺して蔵の金五千両を盗み出すという大胆な計画を企てる。酒にハンミョウを入れて簡単に主人は事切れ、千両箱5箱を運び出して竹藪の地下に埋めた。三年ほど逃亡して戻ってきたところで掘り返し、さも儲け仕事をして帰ってきたと装うという魂胆だ。だが、その旅の支度をしているところを同じ丁稚の亀蔵に箪笥から三十両を盗んだところを見つけられてしまう。
一両やるから黙ってくれと頼み、父親が急死して茫然としている若旦那に「四国八十八カ所を巡礼して、旦那の菩提を弔う」と言って、旅に出ようとするが…。亀蔵が「一緒に連れて行ってくれ。連れていかないと、あのことを言ってしまうぞ」と脅すので、仕方なく二人で巡礼の旅に出る。
宿で与之吉がうなされながら寝言を言っているのを亀蔵は聞いてしまった。「旦那を殺して、五千両を竹藪に埋めた。許してください」。与之吉が目を覚ましたので、亀蔵があの寝言は本当か?と訊く。これは拙いと与之吉は何度も亀蔵の首を絞めて殺そうとするが、うまくいかなかった。あるとき、海べりに出たので与之吉はここぞとばかりに亀蔵を突き落とした。「お前は知り過ぎた。成仏しておくれ」。
だが、海の藻屑となるはずの亀蔵は漁師の船に助けられた。その後も“可哀想な巡礼さん”として行く先々で世話になり、後に弘法大師になる僧にも助けられた。そして、七年ぶりに亀屋清左衛門の店に戻ると、小間物屋の暖簾を出して亭主として構えている与之吉がいた!「久しぶりだな、与之ちゃん!」と声を掛けると…。「ちょうど時間となりました」で終わった。この先がとても気になる浪曲らしい終わり方だった。
「御霊文楽座 心の肩衣」。江戸で修業を終えた豊竹豆太夫が師匠の靭太夫の許に戻ると、弟弟子の富士太夫が二代目靭太夫を襲名していた。「自分が一番弟子なのに!」と怒り心頭。そこへ初代靭太夫の娘お糸が来て事情を話す。
靭太夫没後、多額の借金が残った。それを富士太夫夫婦が肩代わりしてあげて、元の暮らしに戻れた。母は風邪が元であの世に逝ったが、そのときに「豆太夫には悪いが二代目を富士太夫に継がせるのが、せめても恩返しだ」と遺言を遺して死んだ。「許してあげてください」とお糸は頭を下げる。
茫然としている豆太夫に源さんが声を掛ける。「二代目は口がうまいからね。お前さんに加勢しようと思っていた…泣いているのか?」。豆太夫が言う。師匠の名前を継ぎたいと修業を続けてきた。この浄瑠璃本には血の滲むような努力が詰まっている。俺は今日限りで浄瑠璃をやめる。これは師匠が二十五歳で名披露目をしたときに母親に縫ってもらった肩衣だ。七年前、江戸に修業に行くとき、師匠が餞として「うちは貧乏で何もないが、この肩衣はお前にやる。お前が名披露目をやるときは、これを着けてくれ」と言われて譲ってもらった肩衣だ。
辛い修業も何のその。肩衣を眺めて、師匠の名前を継ぐという希望を胸に抱いて、ここまできた。それが、名前を取られ、希望を取られ、あとは涙に暮れるばかりだ。男泣きする、春の雨。源さん、火種を貸してくれ。この浄瑠璃本と肩衣を燃やしてしまおうと思う。
そのとき、背後から「待て!」という声が聞こえる。初代の相三味線だった鶴澤清六だ。名前を取られたから、やめる?お前は名跡で浄瑠璃を語るのか?名跡がなんじゃい。二代目がなんじゃい。そんなもので一人前になれると思うか。焼いてしまえ。よく聞け。芸人というのはお客様あってこそ。稽古を重ね、お客に「上手くなった」と言われるのが、何よりの喜びと違うのか?
靭太夫が死んだとき、わしも三味線をやめようと思った。だが、それで天下の師匠に顔向けできようか。お前が江戸から戻ってきたときに、立派な太夫にしてやろうと艱難辛苦を乗り越えてきた。それが名跡にこだわり、太夫をやめるとは、人でなしだ。そんな了見なら、焼け!
豆太夫は目が覚める。「よく言ってくれました。これから先は名跡に構わず稽古して、あの二代目を見返します」。そう言って、清六の手をギュッと握りしめる。「さすが俺が見こんだだけのことはある。俺はお前の浄瑠璃を弾いてやる」。
そして、文楽座で「伽羅先代萩」を語り、評判を取る。名前も豆太夫から古い靭、古靭太夫と改めた。この歓声も清六のあの厳しい意見があればこそ。素敵な出世譚を聴いた。