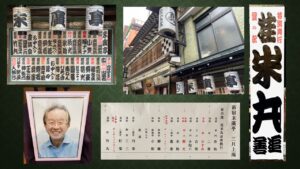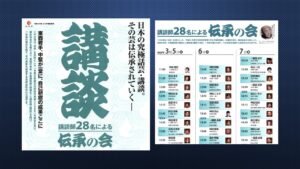浪曲定席木馬亭 天中軒雲月「忠僕直助」天中軒月子「あゝ横綱玉の海」玉川奈々福「河内山宗俊 上州屋玄関先」、そしてYEBISU亭

木馬亭の日本浪曲協会三月定席四日目に行きました。
「名槍日本号と黒田節」天中軒かおり・沢村博喜/「出世定九郎」三門綾・広沢美舟/「身代り音頭」港家小そめ・沢村博喜/「天保六花撰 河内山宗俊 上州屋玄関先」玉川奈々福・広沢美舟/中入り/「あゝ横綱玉の海」天中軒月子・玉川鈴/「徂徠豆腐」一龍斎貞友/「からかさ桜」澤雪絵・玉川鈴/「忠僕直助」天中軒雲月・広沢美舟
かおりさんの「名槍日本号と黒田節」はネタおろし。実は酒豪の母里太兵衛が黒田の殿様と「守れれば100石の加増」という禁酒の約束をして広島の福島正則のところへ使者に赴く。同じく酒豪で知られた福島公が太兵衛に酒を勧めるが、太兵衛は「不調法で」「下戸で」と盃を受け取ろうとしない。「確か母里氏は大酒飲みと聞いている」と意地でも飲まそうとする福島公。主人との約束を守るのか、福島公に恥辱を注がれるのを避けるのか、板挟みになった母里太兵衛はどうするのか…。というところで、「お時間が来ました」。前座の15分高座ゆえ仕方ない。この続きが聴けるのを楽しみしたい。伸びやかで綺麗な声だけに応援していきたい。
奈々福先生の「上州屋玄関先」。河内山が上州屋を訪れたとき、番頭は「鬼門金神暗剣殺」と思ったという表現が良い。簡単に言うと、不吉な人物到来ということであるが、こういう言葉を大事にしているところが奈々福先生の魅力だろう。
上州屋彦右衛門の一人娘で十七歳になるおなみが、雲州十八万六千石松平出羽守に行儀見習いで女中奉公したところ、殿様のお手がついた。妾として迎えることを断るなら、死骸で下げ渡すという強硬姿勢に、親戚一同が顔を揃えて思案投げ首している。この取り込みごとを解決してやると請け合った河内山。500両という報酬を要求するところが、面の皮の厚い河内山の河内山たる所以だ。
河内山は袈裟衣を着て、水晶の数珠を持ち、東叡山寛永寺の宮家親王の使僧として雲州松江侯屋敷に出向く。家老の小林大膳に対し、ニッコリ笑って堂々と「おなみを上州屋にお下げ渡し」する旨、“宮家の言伝”として言い渡す肝の太さは流石である。事は上手く運ぶように見えたが、最後の最後で雲州侯が“宮家の使僧”は御数寄屋坊主の河内山宗俊であることを見破る…。さあ、どうなる!というところで「丁度時間となりました」。河内山のふてぶてしさを十分に表現した高座がとても良かった。
月子先生の「あゝ横綱玉の海」。「NHK解説 初代玉の海梅吉」と「二代目玉の海こと片男波嶽太郎」の連名で贈られたテーブル掛けで、第五十一代横綱玉の海の物語だ。
中学生だった正夫少年は父親が早逝したため、母親がブロック工事の現場で働くという家庭環境に育った。教師の川原先生が「お母さんを安心させるために力士になれ」と勧め、正夫も「自分が出世の道を掴めたら親孝行になる」と決意、昭和34年に14歳で蒲郡から上京し、二所ノ関部屋に入門する。歯を食いしばり、血の出るような稽古に励んだが、なかなか芽が出ない。目を覚ましてくれたのは、初代玉の海の梅吉だった。横に飛んで勝った相撲に対し、大目玉を食らわせたのだ。「相撲の基本は攻撃だ。押しの一手で前へ進め」。
また、片男波親方となった二代目玉の海も「母親に会いたいか?それならば、男になって会いなさい。胸を張って会える身分に出世しろ」と檄を飛ばし、玉乃島という四股名となった正夫は奮起した。そして、心の中で「自分が男になれたら、三代目玉の海を襲名したい」と誓った。
昭和38年、新十両。39年、新入幕。41年、大関昇進。43年に大関在位13場所で初優勝を果たす。45年春場所に横綱昇進。梅吉が「おめでとう」と声を掛けると、玉乃島は思い詰めた顔をして、「一生のお願いがあります。玉の海の名前をいただきたい。私にとっては忘れられない名前、梅吉親方と片男波親方と絆を持っていたいのです」。これには梅吉は嬉し泣きしたという。
昭和46年春場所には目標だった大鵬を千秋楽結びの一番で破って5回目の優勝を果たす。柏鵬時代が終わり、角界を背負うのは北の富士と玉の海、北玉時代の到来だと言われた。名古屋場所には悲願の全勝優勝。地元蒲郡の母親と喜びを分かち合った。
だが、病魔が襲う。昭和46年10月11日、急逝。北玉時代は突然終わってしまった。人生27年、相撲に賭けた13年。玉の海正洋の短く燃えた生涯を月子先生は相撲甚句で謳いあげるという素敵な演出で高座を飾った。
雲月先生の「忠僕直助」。岡島八十右衛門の許を逆暇して去っていった下郎の直助が10年ぶりに帰ってきた。高名な刀鍛冶、丸津田助直と名を改めて、稲荷丸と名付けた名刀と200両を持って戻ってきた。というのも、主人の岡島が大野黒兵衛に「お前の刀は鈍刀(なまくら)だ」と恥をかかされたのを遺恨に思い、直助が大坂に刀鍛冶の修行に出て、主人の無念晴らしをしようと心に秘めたのだった。
講談と違うのは、この後のストーリー、即ち大野黒兵衛への意趣返しに重点を置いているところだ。大野が岡島の腰の刀を目敏く見つけ、「これは名刀だ。丸津田助直ではないか」と指摘すると、岡島は「縁故の者が土産に持ってきてくれた」と答える。大野は「倅の差し料を打ってくれるよう頼んでくれないか」と言うと、岡島は「助直を呼ぶので、直々にお願いしてはどうか」と返す。
直助にとっては「10年間、忍耐したのはこのためだ。覚えておれよ、黒兵衛よ」。黒田が値段を訊くと、直助は「千両」と答える。黒田は「下から出ればつけあがって!天狗になるのもいいかげんにしろ!」。直助は黒田の自慢の長谷部長兵衛国重を指して、「戦場では役に立たぬ代物。小さな傷がある」と言うと、黒田は「折れるか、折れぬか、試してみよ」と強硬姿勢。直助は長谷部長兵衛国重に自分の稲荷丸を振り下ろそうとしたとき…。
「しばらく待たれよ」の声。大石内蔵助だ。内蔵助は「どこかで見たことのある…下郎の直助だ」と気づく。10年前に岡島と黒田が言い争いをしているときに、直助が仲に入って止めたのを見て覚えていたのだ。「岡島は良い家来を持ったのう。あのときの下郎が出世して、丸津田助直殿か」。内蔵助は万が一、直助の意趣返しが失敗したときのことを考え、代役として武林唯七を指名し、黒田の名刀を斬り落とすよう命じる。「さすが、城代家老」と周囲の者たちは思った。
果たして、黒田自慢の長谷部長兵衛国重は真っ二つに。見事、岡島八十右衛門と直助改め丸津田助直は無念晴らしを果たすことができたという…。雲月先生、渾身の高座だった。
YEBISU亭に行きました。
オープニング/「路地裏の伝説」柳家喬太郎/今夜踊ろう/中入り/「湯屋番」風間杜夫
喬太郎師匠がまとった昭和の空気が好きだ。オープニングで風間杜夫さんとデュエットで唄った♬3年目の浮気は昭和57年のヒット曲。ヒロシ&キーボー、懐かしいなあ。
「路地裏の伝説」も昭和感満載の新作落語だ。主人公の父親の三回忌に同級生が集まり、献杯して「発泡酒は発泡酒」と思わず漏らすところ。おつまみのチーズ鱈を食べながら、「真ん中は確かにチーズだけど、両脇は明らかに和紙だよな」と突っ込むところ。昭和の香りがする笑いがたまらない。
そして、次々と飛び出す小学生の間で流行ったモノたち。ネッシー、ツチノコ、ヒバゴン、なんちゃっておじさん、口裂け女…赤軍派はちょっと違うけど、これもまた昭和だ。日常生活にあった鳩サブレ、ドクターペッパーや少し大人になった気になって読んだ平凡パンチやGORO…。この落語が平成、令和、そして次の時代と語り継がれ、「古典落語」として吉原遊郭や棒手振り商人、長屋の大家と店子、旦那と奉公人といった言葉や文化風俗と同じ並びになる日が来るかもしれないと思うと、ちょっとワクワクするなあ。