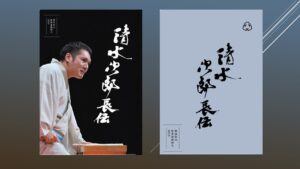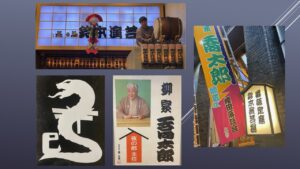神田伯山新春連続読み 清水次郎長伝(下)

「神田伯山新春連続読み 清水次郎長伝」に行きました。
四日目。第十一話「お民の度胸」は神田愛山先生の持ちネタにはない。ただ、伯山先生が、「浪曲ではよく掛かる部分だし、森の石松の最期を描きたい」と考えて、宝井琴調先生から教わったそうだ。「お民の度胸」と演題にはあるが、石松ってバカが褒め言葉になるほど、バカ真面目だなあ、それゆえに死んじゃったと思う話だ。
石松は人が好いから、預かっていたお蝶の香典の百両を簡単に都鳥の吉兵衛に貸しちゃう(というか、あげちゃう)し、保下田久六の子分3人と都鳥一家が結託、石松は命を狙われるが一旦は小松村の七五郎とお民の夫婦に匿ってもらったのに、またのこのこと閻魔堂まで出向いてしまう。その上、久六子分&都鳥一荷が「石松ほどバカはいない」と言って挑発すると、あっさりと彼らの前に現れて、もはや戦える身体ではない、ボロボロなのにもかかわらず、敵に向かって行くという…。まさにバカは死ななきゃ治らない、なのである。愛すべきキャラクター、森の石松だ。
許せないのは、百両を貰っておいて殺してしまおうと考える都鳥の吉兵衛だ。久六の子分、布橋の兼吉、尾島の松五郎、鹿島の久松の三人と「次郎長一家は大嫌いだ」と徒党を組む厭らしさが許せない。一方で石松のことを思い、吉兵衛たちがやって来ても一歩も退かなかった七五郎、そして妻のお民の度胸に感心する。石松が殺されたと聞き、現場に駆け付け、石松の髷と小指を斬り落として、「必ず仇を討つ」と誓った七五郎に共感する。
第十二話「蛤茶屋の間違い」は、恋の鞘当てが大事となり、荒神山の賭場争いへと発展するところに妙味を感じる。富田の町の料理屋「みすじ」の十八歳になる看板娘、お琴に安濃徳次郎の子分、上州無宿の熊五郎が入れ込んだ。だが、お琴には神戸の長吉の子分、加納屋利三郎という“いい人”がいた…。
熊五郎は利三郎を負かすことを考える。賭場にいた利三郎を目の敵にして、腕自慢の博奕で一泡吹かせる。だが、利三郎の懐は温かく、負かしても、負かしてもビクともしない。ようやく、利三郎が熊五郎に少し融通してほしいと頼んだところで啖呵の切り合いとなり、あわや大喧嘩となるが、周囲が止めて、利三郎は去って行った。いつか、決着をつけてやる…と熊五郎は思ったのだろう。
熊五郎は帰り道、安濃徳次郎の用心棒をしている信州松本浪人の角井門之助と出会い、利三郎との諍いのことを話す。門之助はきっとこれは“荒神山の件”だろうと推測し、熊五郎を褒める。一日で千両もの儲けが出る荒神山の賭場は親の代から神戸の長吉の縄張りだが、その利権を安濃徳次郎に奪わせようと喧嘩をしたのだと勘違いした。熊五郎もあえて、これを否定しない。ましてや料理屋の看板娘を巡る喧嘩なんて小さなことを言ったら恥だ。このことが、後の荒神山の喧嘩への導火線となるのだから面白い。
中入り後の第十三話「三本椎の木お峯の茶屋」。大変な修羅場でありながら、婆さんと子どもがキーパーソンになるところが面白い。門之助と熊五郎が仲間30人ほど集めて神戸の長吉の家に殴り込みをかけるところ、家には長吉どころか子分も一人もいなかったが、長吉の母親だけいた。婆さんは少しも怯まず、啖呵に対して啖呵で返すという…。ここの部分、コミカルである。仕方なく、熊五郎たちは「三本椎の木お峯の茶屋へ来い」と伝言を残し去る。
長吉が帰り、またそこに利三郎が飛び込んで来て、「喧嘩の種は自分にある」と、お琴や賭場での熊五郎との諍いについて話す。そして、一行はお峯の茶屋へと向かうが、そのときに通りすがりの子どもに声を掛けられる。「松蔵だよ」。利三郎が堅気として質屋の若旦那をしていた頃に母親が助けられ、以来助太刀をするように言いつけられて育ったという。だが、そんな子どものことなど構っていられない。いざ、喧嘩がはじまる。
利三郎に斬りかかる熊五郎…だが、その熊五郎をあの松蔵が一突きした。お蔭で、利三郎は熊五郎に止めを刺すことができた。だが、利三郎も門之助に斬り殺されてしまう。そこに「御用だ!」の声。一同は退散したが、喧嘩の発端である熊五郎と利三郎は命を落とした。ああ、それにしても松蔵。不思議な存在だ。
第十四話「飯田の焼き打ち」。子分たちは血気盛んなのはいいけれど、どうして親分である次郎長の「黒駒の居場所だけ尋ねろ。答えなくても、喧嘩をしないで帰って来い」という命令を守れないのだろうと思ってしまう。
黒駒勝蔵は信州飯田に流れ、畑中の鉄五郎と鯛屋の鶴吉が世話をしている。二人にとって目の上のたん瘤は次郎長の子分の滑栗の初五郎。次郎長を憎む黒駒に殴り込みを促し、黒駒は沢山の子分を連れて初五郎宅を襲うが、初五郎は不在。だが、妻や子どもを斬り殺した。
この話を聞いた次郎長は黒駒の行方を探す。大政、大瀬半五郎、増川仙右衛門、法印大五郎、小松村の七五郎の五人を筆頭に子分十七人を畑中と鯛屋の許へ遣わす。そのとき、次郎長は「相手が答えなくても、決して喧嘩はするな」と釘を刺したのだが…。
飯田に着いた十七人。大野の鶴吉を先鋒として行かせると、負けず嫌いの桶屋の鬼吉が我慢できずに追っかける。喧嘩早い鬼吉の動きに慌てた一行は全員が畑中と鯛屋の許へ。しかし、時すでに遅く、喧嘩は始まっており、やむなく他の面々も喧嘩に加わると、畑中と鯛屋を斬り殺してしまう。さらに鬼吉は家に火を放った…何ということをしてくれたんだ!と思う。
次郎長の命の背いてしまった十七人は面目が立たなくて、清水に戻ることができない。間に吉良の仁吉に入ってもらおうと考え、仁吉を訪ね、仁吉もこれを引き受けることにする。桶屋の鬼吉…こういう軽はずみな男が、どの時代にもいるものだと思った。
千穐楽。第十五話「仁吉の離縁場」。親族よりも義理を大事にする任侠の世界とは言うが、仁吉はそれを地でいった男だ。神戸の長吉の縄張りだった荒神山の賭場を、利三郎と熊五郎の一件によって、安濃徳次郎が自分の手に渡ったと廻状を廻す。二千もの身内がいる安濃徳にどう対抗するか。長吉は吉良の仁吉に仲裁を頼むことにした。
だが、仁吉は三か月前に安濃徳の妹お菊と結婚していたことを思い出す。長吉が荒神山の賭場の件を切り出すと、仁吉はすべてを飲み込んで、お菊を呼び、「お前といると義理が立たない」と離縁状を渡すのだ。申し訳ないお願いをしてしまったと長吉が詫びを入れても、仁吉は後に退かない。お菊は泣く泣く家を出て行った。任侠の世界というのはこういうものなのか。
仁吉はやって来た次郎長に長吉のことを話し、仁吉の義侠心に免じて子分を許し、荒神山への帯同を命じる。「逆らう者は片っ端から叩き斬れ」。次郎長子分二十七人が、仁吉と長吉の後ろ盾となって荒神山へ向かう…。
第十六話「仁吉の最期」。さあ、ここはチャンチャンバラバラ。喧嘩場である。荒神山で待ち受ける安濃徳と角井門之助に対し、次郎長勢二十九人が闘う。仁吉は門之助と斬り合ったが、何と卑怯なことに安濃徳が雇った猟師に足を撃たれ、よろけた隙に止めを刺されてしまった。
駆け付けた大政が門之助を槍で突き、小政が斬り倒す。「角井門之助は小政が討ち取った!」と叫ぶと、安濃徳の身内は蜘蛛の子を散らしたように去って行った。「喧嘩は勝った。あとは任せろ」と瀕死の仁吉に伝える大政と子分たち。畳を置いた戸板に仁吉を載せて、山を下り、三州吉良へと戻った。吉良の仁吉、享年二十六。
中入り後は第十七話「仁吉の焼香場」。神戸の長吉は喧嘩の間、逃げて隠れていたことが判ってしまう。次郎長の目は誤魔化せない凄さと同時に、所詮長吉は侠客の玉ではない、気弱な可哀想な奴だった…。これが切ない。
仁吉の葬儀は次郎長が仕切った。人望ある仁吉のこと、大勢の列席者が集まる。次郎長が指名した大瀬半五郎が荒神山の一部始終を物語るところ、皆が咽び泣くようだ。焼香は仁吉の妹おひさ、大政、小政、神戸の長吉と続いたが…。
次郎長は長吉に自分の長脇差を持ってこさせる。それを抜くと、畳に突き差し、隣に仁吉の長脇差を突き差した。綺麗な長吉の長脇差に対し、仁吉のものは柄糸まで血に染まって刃もぼろぼろである。仁吉が命を投げ出し、斬り合う中、長吉は逃げていたのだ。
そのことが明らかになると、仁吉の親分である寺津間之助は次郎長の許しを得て、長吉を斬ろうとした…そのときに、御油の玉屋の玉吉が飛び出してきた。玉吉は仁吉、長吉と兄弟盃を交わした仲。「長吉は気弱な男。その弱さに仁吉も気づいていたはずだ」と言って、命だけは助けてほしいと願い出る。次郎長が了承すると、玉吉は長吉を追い出した。以来、長吉は渡世人の世界に姿を見せることはなかったという。情けない結末。これもまた任侠の世界か。
第十八話「その後の次郎長」。時代は江戸から明治に変わり、次郎長は苗字帯刀を許され、今の警察署長のような役に就いたという。これまでの罪滅ぼし、恩返しとして、世の為人の為に働いた。幕府の脱走兵が官軍に倒された咸臨丸事件が起きたとき、謀反人の死骸を弔うなという官軍の命令に背き、次郎長は「仏に敵も味方もない」と丁重に埋葬した。このことが、山岡鉄舟の耳に入り、痛く感服して、墓の揮毫を申し出たという逸話も残る。
その後も次郎長と鉄舟の交流が続き、次郎長は「精神満腹という度胸免状を貰った」と自慢していたという。富士の裾野の開墾や船宿末廣の開業など、その後も地域に尽くしていく。そして、明治26年に七十四歳で大往生を遂げたという。
三代目神田伯山が創り上げた「清水次郎長伝」を、今こうして六代目の伯山先生が連続読みで観客に届けてくれる。伝承芸の素晴らしさを改めて感じた。