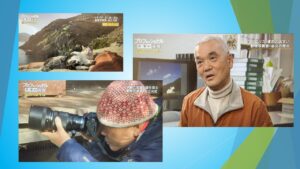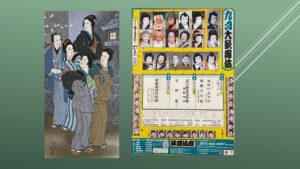【猫じゃ猫じゃの会】「猫定」の熱演に、名手・柳家さん喬の真骨頂を見た

江戸東京博物館小ホールで「猫じゃ猫じゃの会」を開きました。(2021・09・25)
♬猫じゃ猫じゃとおっしゃいますが 猫が下駄履いて 絞りの浴衣で来るものか おっちょこちょいのちょい~♪
おっちょこちょい節は文政年間に流行し、その後俗曲に残って幕末から明治初期に再び流行したという。
辞書を引くと、おっちょこちょいとは、落ち着いて考えないで軽々しく行動すること、とある。語源は不明だが、猫が下駄を履いたり、浴衣を着たりすると思い込んでしまうなんて、相当おっちょこちょいなのは確かですね。
今回は猫にまつわる演目や演者でプログラムを構成しました。
昔昔亭昇「猫の皿」
去年二ツ目に昇進したばかりのフレッシュな若手の昇さんは、アグレッシブな高座が身上。尊敬している桃太郎師匠にまつわるエピソードで客席を大いに沸かせて、スピーディーに本題を展開した。開口一番に相応しい、元気いっぱいな高座。
江戸家小猫
小猫先生、この会の意図を汲んで下さり、出囃子に乗って、ニャーオォと猫の鳴き声とともに登場。イリオモテヤマネコとツシマヤマネコの鳴き方の違い(?)に爆笑。信じる心が大切なんですよね。ネコ科のトラとライオンの鳴き方の違いは説得力があった。アーとウーを逆転するというテクニック、違いがよくわかった。
立花家橘之助
お約束で「おっちょこちょい節」を演奏。そして、寄席では時間の制約があってできない「たぬき」のフルバージョンをたっぷりと披露!前座の左ん坊さんが一生懸命勉強した甲斐があって、太鼓をタイミングよく入れて楽しい演奏に。途中、木魚も入るのは、いかにも狸らしい。左ん坊さん、グッドジョブです。
柳家さん喬「猫定」
50分を超える熱演!定吉が可愛がっている猫のクマを懐に入れて、博奕にいく様子は、猫の鳴き声と腕の使い方によって、実によく描かれている。そして、定吉の女房のおたきと源太郎の不義密通を伝えようとするクマの忠義心が何とも愛おしい。定吉殺人の仇討を見事に果たすクマの行動は因縁噺の真骨頂で、噛み付いた喉仏が二つ並んでいるところなど、情景が浮かび、その恐ろしさで体にゾクッとしたものが走った。