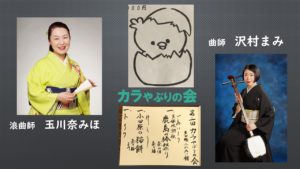柳家喬太郎「拾い犬」 謙虚を忘れず、真っ正直に生きろ。切なくて、やがてほっこりする。

日本橋三井ホールで「COREDO落語会」を観ました。(2020・09・23)
柳家喬太郎師匠の新作落語「拾い犬」を久しぶりに聴いた。この噺の初演は2014年11月の横浜にぎわい座、「わんにゃん寄席」という百栄師匠との二人会で、百栄師匠が猫担当で「バイオレンススコ」と「ロシアンブルー」を演じ、喬太郎師匠は犬担当で「バイオレンス・チワワ」とネタおろしの「拾い犬」を演じたのだった。
喬太郎師匠は「棄て犬」という二ツ目時代に作った、とても居たたまれない(そこがまた師匠の魅力なのだが)、後味の悪い作品があるのだが、さすがにこの企画にはそぐわないと思ったのか、古典風味に新作をこしらえて掛けた。ちなみに、「棄て犬」は13年4月の「ザ・きょんスズ」、去年の「ザ・きょんスズ30」でしか聴いたことがない。「拾い犬」はその後、その去年の「ザ・きょんスズ30」に同じ日に「棄て犬」と組み合わせて掛けている。それ以来だ。
ほっこりとさせてくれる噺である。ある長屋に白犬が捨ててあったのを六ちゃんと善ちゃんが見つけて、可哀想だから長屋で飼おうと提案するが、大家は貧乏長屋にはそんな余裕はないし、どこか裕福な家庭に引き取ってもらった方が犬にとっても幸せだといい、ある呉服屋に預けられた。
善吉はシロと名付けて心に思っていたが、どうしても諦めきれず、その呉服屋の天水桶の陰に隠れて遠巻きから覗く。不審に思った番頭は善吉から訳を訊くと、納得。お嬢様が5歳、善吉が7歳、よい遊び相手にもなるだろうし、人手も足りないところだったから、旦那に話して、善吉を奉公人として雇うことに。
10年後。旦那が善吉を呼びつけ、話をする。飼い犬のシロが最近、姿を見せない。犬は利口で自分の寿命がわかっている、死ぬ時期を悟ったのかもしれない、迷惑をかけるといけないからと姿を見せなくなったのかもしれないと。と同時に、娘に縁談が来て、婿取りの話が進んでいる、あるお店の次男坊なのだが、お前はどう思うか?と。善吉はただ「おめでとうございます。結構な話です」。
だが、旦那が繰り返す。主従の間柄で一緒になるのは世間様では「身分違い」と言う。だが、私は関係ないと思う。人間同士好きあっていれば、良いことだと思う。むしろ、一緒になれないのは可哀想だ。それを踏まえて、娘が婿を取っていいかい?
善吉はただただ真っ正直に「私が口出しすることではないです」。それに対し、旦那は浮かない顔で、また同じこと言って「婿を取っていいかい?」。旦那は善吉を娘の婿にしたいのだという気持ちがありありと見て取れる。だが、あくまで善吉は「お婿様を取れば、お店は益々ご繁栄です」と、暖簾に腕押し、糠に釘だ。そのまま店先に戻ってしまった。
「この庭にシロはもう戻ってこないのか」。善吉の脳裏に思い出がよみがえる。シロと出会わなければ、こんな切ない思いはしないですんだのかもしれない。これが生きていくということか。そんなことを考えていると、「善吉!」と呼ぶ声がどこかからする。声の方角を見ると、六ちゃんがいる。「久しぶりだな」。「お前もうまいことやりやがったな。旦那には可愛がられ、娘とも仲良くしているらしいじゃないか」。すっかりと悪の道に染まってしまった六がそこにいた。
ここのお嬢様はいい女らしい。お前の言うことなら、疑わずに何でも言うことを聞くだろう。一緒に吉原に売り飛ばし、山分けしないか?とんでもない、できない相談である。断る善吉に匕首を突き付け、「これでもできないか?」と脅す六。「かどわかし」などできないと、拒否する善吉。そこに一匹の白犬が現れ、六に噛み付く。「シロ!」。どこか悲しい顔をしている。犬の攻撃で諦めた六は「わかったよ。なかった話にしてやらあ」。そして、そこには六もシロもいなくなった。
お嬢様が善吉のところにやってくる。一部始終を見ていたのだ。「ありがとう、助けてくれて。シロが縁で助かった。あたし、お婿さん取るの、やめます」「なんだって、そんな」「訳を言ったら野暮よ。お前さんと同じ気持ち」。
拾った犬が縁で恋仲になった身分違いの奉公人とお嬢様の恋は成就するのだろう。そこには真っ正直な善吉に惚れたお嬢様、旦那、そして結びの神であるシロを愛した人間の優しい気持ちが底辺に流れているのを感じた。擬古典という言葉が流行っているが、何十年後には古典落語に加わる名作だと思った。