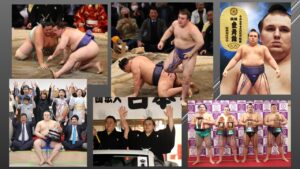春風亭一之輔のドッサりまわるぜ「らくだ」、そして柳家喬太郎独演会「粗忽の使者」
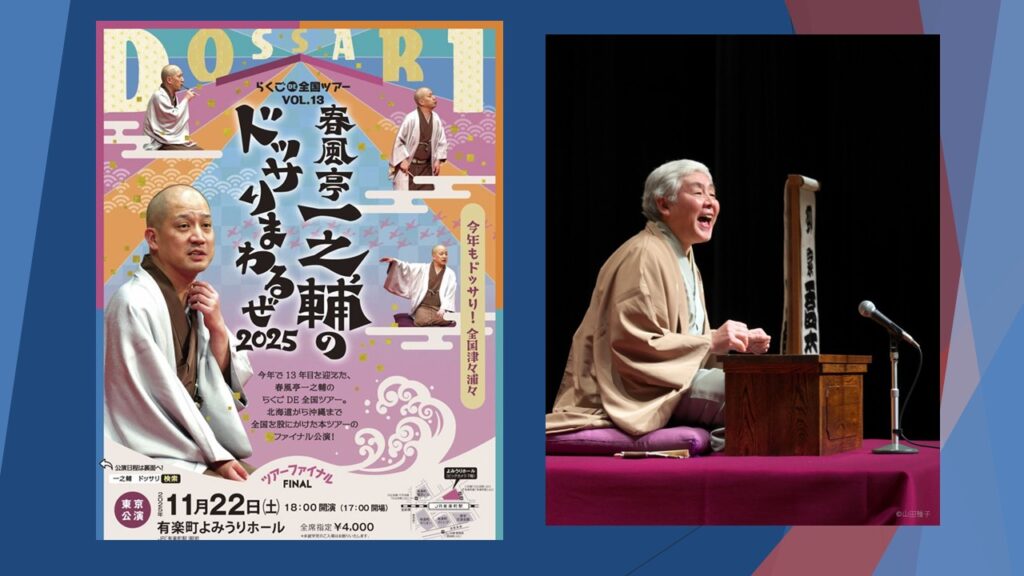
春風亭一之輔のドッサりまわるぜ2025ツアーファイナルに行きました。「青菜」と「らくだ」の二席。開口一番は春風亭一花さんで「洒落小町」だった。
「青菜」は植木屋の悪戯っ子っぽいキャラクターが光る。ガラスのコップを目に当てて、「旦那が大きくなったり、小さくなったりする」と喜んだり、鯉のあらい用の酢味噌を舐めて、「これだけで五合は飲める…おまんまにかけて食べたい。守っていきたい味だね…スミソニアン博物館」と洒落を言ったり、奥様が咄嗟の隠し言葉を繰り出したのに対して「ご懲役がある…ご教育か。懲役だったら、番号で呼ばれて、湯も10分、箪笥を拵えなきゃいけない」と冗談を言ったり。
「鞍馬から牛若丸…」の夫婦のやりとりを家路につく途中で何回も繰り返しているうちに、「金持ちは嫌だなあ。やることが大仰だ。菜はあるか?ねえよ!で良い。ちゃんちゃらおかしい」と言っていたのが、「やってみたい!ずるい!金持ち!無駄を楽しむんだね。貧乏人もやりたい!」と変わる過程が何とも可笑しい。
タガメの女房に「感心バカ」と言われながらも、「華族様の出じゃないかと言われたい」とやる気満々の植木屋は、小町は十二単じゃなきゃいけないと無理やりに襦袢の上に綿入れを三枚着せて、髪もほどいてザンバラにして、次の間の代わりに押し入れに押し込む。建具屋の半公に対して柳影の代わりに二級酒、鯉のあらいの代わりに鰯の塩焼きを勧めて、菜は嫌いだと言うのに無理やり、「コレヨ!奥ヤ!」と手を叩くと、半公まで面白がって合いの手を入れる漫画世界が実に愉しかった。
「らくだ」通し。丁の目の半次が屑屋の久六を脅して、らくだの弔いの準備のために遣いに行かせるところ。屑屋が「十四を頭に五人の子供を養わないといけない」と断ろうとするが、「今日中によく顔見とけよ。生きて二、三日だな」とか、「お耳をお貸しいただけますか。自分で自分のハラワタを見たことはありますか。意外と綺麗ですよ」とか、強面で迫られたら、言うことを聞かざるを得ないだろう。
らくだの死を屑屋から知らされた大家の表現も興味深い。誰のお陰でお前はこの長屋に出入りできていると思っているんだ。恩を忘れやがって。だるまさんが転んだ?…らくだが死んだ…屑屋の符牒か?死なないかなあ。世界中の長屋に漏れなくらくだが付いているなら諦めがつく。何で、うちだけ?セコヨイショは通じないよ。あいつは死なないよ…本当に死んだ?ヤッター!石で頭潰しておけ。河豚塚を建てて、河豚祭りだ。
酒や煮しめや握り飯をお願いすると、「三年間店賃一度も払っていないんだ。それを棒引きするだけで十分だろう」と言うのは理に適っている。だが、屑屋が“死人のカンカンノウ”を半次に言われた通りに持ち出すと、「朝から退屈していたんだ。見てい、見てい、是非見てい」と、塩を撒いて追い払う…。そこで実際に屑屋がカンカンノウを歌って、半次が腕をボキボキ鳴らしながららくだを抱えて踊らせるところは迫力満点。「酒、出せ!酒が飲みたーい。煮しめ、出せ!煮しめが食べたーい。ついでだから、もっと躍らせろ」。驚いて腰を抜かす大家夫婦の様子が目に見えるようだ。
大家から届いた酒を半次が「お前は死人を担いだから汚れている。清めに飲め」と屑屋に勧めるところ。「十四を頭に…」と屑屋は固辞するが、「優しく言っているうちに飲めよ」と迫り、結局三杯飲む。その間に屑屋がどんどん酔っていく。親方、偉いや。兄弟分のために金がないのに、これだけやっちゃう。私も人のために働くのは嫌いじゃない。頼まれるとやっちゃう。元は古道具屋だったけど、酒でしくじった。目も利かなくてね。親父は自分の頭の蠅も追えないのに人の世話を焼くと小言を言っていた。あなたと気が合うんじゃないか。
長屋は皆貧乏だ。だけど、心根が優しい人が多い。下駄の歯入れ屋の辰さんは「死ねば仏だ」と言ってくれた。そこへいくと、大家さんは…好きじゃない。「是非見たい」と言っていたのが「勘弁してください」。あんなに驚いているところは初めて見た。よっぽど怖かったんですね。だったら、ハナから出せって言うんですよ。そう思いません?「誰のお陰で」とか「恩を忘れて」とか、良くない。かけた情けは水に流す、受けた恩は岩に刻むくらいのことは心得ているんだ。男らしくない。何が家主だ!馬鹿野郎!
「もう一杯」と要求する屑屋に、半次が「大丈夫か?」と訊くと「大丈夫だよ」。死ねば仏…何が仏だ!とここから、らくだに対する恨み節が始まる。地べたに丸を描いて、50文で買わされた。丼が四つ揃いであったので200文で買うと、「蓋もある」、そこには長寿庵と名入れがあった。その上、蕎麦屋に返して、代金まで支払わされた。そこまで言って、「お前が笑うなよ!」。
甚五郎の蛙。一分を払うと、蛙がピョーン!と跳んだ。甚五郎が彫ったから生きているんだと言われ、柱に頭をゴツンゴツンと叩きつけられ、おでこから血が出た。口の中に蛙を入れられ、泣きながら家に帰った。死んだ女房の代わりをしてくれている十四の娘が四人の弟を遊びに出し、手拭いでぬぐってくれた。「私も働くから、体だけは気をつけて」。らくだの耳を食いちぎって、目ん玉くり抜いてやろうと思った。でも、一家が路頭に迷う。堪忍した。堪忍してやったんだ!
これを聞いて泣く丁の目の半次。「偉いぞ、兄弟!」これに対して、屑屋は「俺は一匹狼だ。屑屋の久さんと言えば、泣く子も黙るんだ。言ってみろ、お前に名前教えたろ!」「屑屋の久さんじゃないの?」「そうだよ。屑屋の久さんです、よろしく!」。
「やめた方がいいよ、兄貴。商売に行かなきゃ」という半次に、「赤の他人に財政に立ち入るな!娘を吉原に売ってでも何とかするんだ。俺が優しく言っているうちに注げ!」。屑屋はもう商売に行かないと決め、「三日三晩、飲み明かす!」。屑屋の久六と丁の目の半次の立場逆転を鮮やかに描いて、落合の焼き場へ。焼き場の吉さんを交えてベロベロに酔っ払った三人が、「弔いだ!弔いだ!らくだの弔いだ」とご機嫌になって、「俺は隠亡、死人を焼くのが仕事」「俺は屑屋、屑を買うのが仕事」「俺はヤクザ、人を脅すのが仕事」と歌って盛り上がるところも面白かった。願人坊主を火の中に放り込み、「火屋でもいいから、もう一杯」。一之輔師匠、渾身の「らくだ」完演だった。
柳家喬太郎独演会に行きました。「首ったけ」と「粗忽の使者」の二席。開口一番は隅田川わたしさんで「元犬」、ゲストは柳家圭花さんで「ふぐ鍋」だった。
「粗忽の使者」は、これぞ落語!という遊び心が愉しい。主人公の名前が地武太治部右衛門というのからして可笑しいが、面白き人物が杉平柾目正という殿様の家来にいるという噂を聞いて、赤井御門守様が是非会いたいので使者によこしてほしいという発想が面白い。
馬廻り役の別当を弁当と呼んだり、使者を将棋の駒…飛車ではない!と言ったり、口上を忘れて切腹してお詫びをすると言うところを「一服する」と言ったり…。この病的粗忽症の男に重役の田中三太夫が「尻をつねると思い出す」と言われて、「いかがでござる?地武太氏!」と大真面目に尻をつねるが…。痛みどころか、蚊が止まったほどにも感じない治部右衛門。柔の達人である三太夫さんが手を焼く情景が目に見えて面白い。
この窮地に名乗りを挙げる大工の留ッ公の登場がこの噺をさらに面白くする。閻魔という釘抜きで治部右衛門の尻をつねるという算段。三太夫さんは藁をも掴む思いで、この際は身分など度外視してこの「指先に力量がある」と自慢の留ッ公を取り立てる。侍の装束を着せ、「中田留太夫」に仕立て、治部右衛門に口上を思い出してもらうことにする…。
子どもの頃からの粗忽ゆえ、尻はタコが出来るくらいに堅くなっていて、これじゃあ指でつねっても効かないはず。閻魔を使っても「まだまだ…もそっと…」と強い刺激を求める治部右衛門に対し、留ッ公は袋の裏あたりの柔らかい部分をつねる…「そこは初めて!これは効く!」。そして、治部右衛門は思い出したのだが…。落語的世界を実に落語らしく表現するところに喬太郎師匠の手腕を見た。