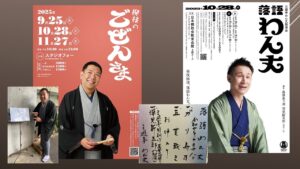通し狂言「義経千本桜」

錦秋十月大歌舞伎の第一部・第二部・第三部を観ました。義経千本桜の通し狂言である。
第一部(Bプロ)鳥居前/渡海屋/大物浦
第二部(Bプロ)木の実/小金吾討死/すし屋
第三部(Aプロ)吉野山/川連法眼館
大物浦の渡海屋銀平実は新中納言知盛を演じたのは坂東巳之助。船問屋の渡海屋の主人、銀平は女房お柳と娘お安と暮らしている。だが、銀平は世を忍ぶ仮の姿であり、実は平知盛が一門の仇である義経に恨みを晴らす機会を窺っていた。お安は安徳帝で、お柳は帝の乳母である典侍の局であった。だが、このことを義経は見破っていて、知盛勢は義経勢に返り討ちされ、敗れてしまう。
満身創痍の知盛は安徳帝の行方を追って大物浦へ。知盛に対し義経家臣たちが打ち掛かると、安徳帝と典侍の局を伴った義経が現れる。義経は安徳帝を必ず守護するので安心するよう諭すが、知盛はそれを信じず、義経を討って平家一門の恨みを晴らそうとする。
そのときの安徳帝の幼少ながらも思慮深い言葉が心を打つ。知盛のこれまでの忠義に感謝し、義経の情けを仇に思うなという…。典侍の局は義経に守護を頼み、自害。それを目の当たりにした知盛も、亡き父の清盛が横暴の限りを尽くした報いだと観念し、覚悟を決めて碇綱を身に巻き付けて大碇を担ぎあげて海へと身を投げる。知盛の壮絶な最期を見届けて、義経一行は安徳帝を供奉して立ち去る…。平家と源氏、対立する者同士ではあっても、どこかで通じ合うものがあったということだろう。
すし屋のいがみの権太を演じたのは片岡仁左衛門。梶原平三景時が平維盛の首を差し出すように命じたときに戻ってきた権太は維盛の首と縛り上げた若葉の内侍と六代君の身柄を差し出し、褒美に頼朝着用の陣羽織をもらう。これを見た権太の父である弥左衛門が怒り心頭し、権太を斬り付け詰め寄る。そのときの意外な告白…。
きょうこそ改心して弥左衛門の許しを得ようと考えた権太は、取り違えた鮓桶の中にあった小金吾の首から父の意図を察し、その首を維盛のものに仕立てた上で、さらに女房の小せんを若葉の内侍、息子の善太郎を六代君の身代りに仕立てたのだという…。笛の合図で、維盛が若葉の内侍と六代君を伴い、無事な姿を見せる。なぜ、権太はもう少し早くに改心してくれなかったのか。弥左衛門は嘆き悲しむ。悲劇である。
そして、褒美の陣羽織に縫いこまれていた袈裟と数珠に頼朝のメッセージがこめられていたというのが興味深い。かつて維盛の父である重盛に命を救われたことのある頼朝が、その恩に報いるべく維盛に出家を勧め、命を救うという暗示だったのだ。つまり、梶原景時も偽首であることは承知の上で首実検をおこなっていたのか。このことを知り、弥左衛門は勿論、権太も悔やまれてならないだろう。父を喜ばせたいと思っていた権太の揺れ動く感情を仁左衛門が巧みに表現していたように思う。
川連法眼館。佐藤四郎兵衛忠信実は源九郎狐を市川團子が演じた。同道してきた忠信の正体を怪しんだ静御前は義経から預かった脇差を抜いて、迫る。観念した忠信は自分は狐であり、初音の鼓の皮は自分の両親だと明かす。桓武天皇の御世に雨乞いの儀式のために作られた初音の鼓が義経の手に渡ったとき、自分は忠信に姿を変え、静御前を守護しながら、親にも等しい鼓に付き従っていたのだ。
義経や静御前を欺いていたことを詫びながら、親を慕う心情を察してほしいと願う源九郎狐。義経が鼓を打って、姿を消した源九郎狐を呼ぶように静御前に命じるも、親子の別れを悲しんでか、鼓が音を出さない。その様子に義経は、人ならぬ身の狐でさえこれ程までに親子の情があることに感じ入る。また、源九郎という自らの名を与えた子狐の身の上と、肉親の情に恵まれずに育った我が身を重ね、こうした悲哀を味わうのも前世からの因縁であろうと嘆く。
再び姿を現した源九郎狐に義経は初音の鼓を与える。源九郎狐は喜びの内に、両親に等しい鼓と戯れるところ。そして、義経を夜討ちにしようと企てている吉野の悪僧たちを通力によって散々に翻弄し、退散させるところ。最後に義経と静御前に礼を述べて。初音の鼓を携えて古巣へ旅立っていくところ。團子が見事な運動神経で魅せるパフォーマンス、そして宙乗りで去って行く演出に拍手喝采の舞台であった。