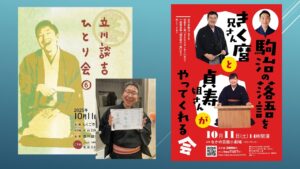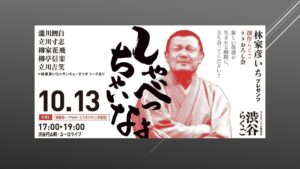百栄てきぃーら 春風亭百栄「姫と三太夫」

「百栄てきぃーら~春風亭百栄独演会」に行きました。「生徒の作文」「お血ミャクミャク」「寿司屋水滸伝」「姫と三太夫」の四席。開口一番は桂枝平さんで「つる」だった。
「姫と三太夫」は9年ほど前に落語協会二階での勉強会で「ハロウィン」「帯留め」「スケベニンゲン」の三つのお題で創作したものだが、それ以降ほとんど掛けていなかったこともあり、かなり手直しをしての蔵出しで、ネタおろしに近い形となった。
このところ柳亭こみち師匠の「あくび指南」を改作した「チャンネル違い」、林家きく麿師匠の「不幸家族」を改作した「わなわな」と、最近ほとんど掛けていなかった過去の噺を掘り起こして練り直す機会が続いた。その2回とも完璧な状態で高座に掛けられずに、カンペを取り出して、ようやくサゲまで辿り着いていた。そして今回もそれに近い高座になってしまったのは残念だ。おそらく忙しくて時間が足りなかったのだと思う。
オランダのハーグ郊外にスケベニンゲン(正確にはスヘフェニンゲン、斜面の村)という地名があって、日本ではこれを面白がって銀座に「スケベニンゲン」という名前のレストランがあるそうだ。それを起点に考えた新作である。
姫のところに沢山の高価な貢物が贈られるが、それは姫を奥方として迎え入れたいという男たちがいるからだ。だが、姫は「男というのはすべからくエッチな人間で、自分のことを手籠めにしたいと考えているからだ。そんな下品な男の貢物など受け取れない」と拒む。
長崎出島の紅毛人から帯留めが贈られた。唐茄子が腐って穴が空いたような帯留め。それはヨハンという飾り職人が作ったもので、キリシタンのお祭り、ハロウィンを表したものであることが判る。この貢物に添えられた手紙を翻訳すると、出島で行われるハロウィンパーティーへの招待で、参加する姫君を募集しているという内容。中央公民館に二朱を払うとワンドリンク付きで入場できる。だが、この誘いを断ると幕府に伝えるという。首絞めか?帯締めか?トリックorトリート…。
その貢物の差出人はオランダの「スケベ」ニンゲン出身の者だという…。ああ、やっぱり、男の考えることは同じだ…そんな噺だ。
百栄師匠の新作落語の魅力は師匠らしい独自の細かいギャグを緻密に計算して散りばめて構成するところにある。是非、この噺も十分時間を使って練って頂き、万全の状態で聴きたいと切に願う。