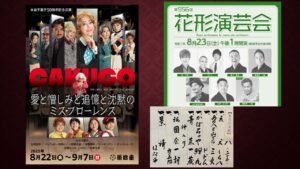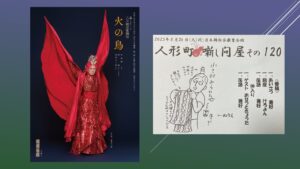音楽劇「くるみ割り人形外伝」、そして歌舞伎「野田版 研辰の討たれ」

音楽劇「くるみ割り人形外伝」を観ました。作・演出:根本宗子。
思春期の人間の感情は複雑だ。僕もかなりひねくれた子どもだった。だから、この劇の主人公のクララの気持ちがよくわかる。演じているのは中学2年生の澤田杏菜さんだったが、実に表現力が豊かな役者さんで、クララを等身大に描いてくれていて、観ていて胸がキュンキュンした。
歌うことも踊ることも大好きで、感情豊かな少女だったクララ。ある出来事がきっかけで、自分の感情をぜんぶ心の奥底にしまい込むようになってしまう。人前では、楽しいことにも、好きなことにも、何にも興味がないみたいなふりで、膨れっ面を続けながら、大好きなうさぎの人形だけに本当の気持ちを話す日々を過ごしていた。
そんな中で迎えたクリスマス。クララが自分の気持ちを隠して、「クリスマスなんかいらない」と嘘をついてしまったせいで、世の中からクリスマスがなくなってしまった!クララはうさぎの人形の手を取り、一晩の大冒険へと向かう…。
クララの奮闘で世の中にクリスマスは戻って来て、ハッピーエンドになるのだけれど、クララはどうしてあんな嘘をついてしまったんだろうと考える。それが思春期というものなのだろう。素直になることは素晴らしいことなのに、わざと反抗してしまっていた。
僕は今でも幼かった頃の夢をよく見る。どうしてあのとき、素直に行動できなかったのか。どうして自分の気持ちに正直になって生きることができなかったのか。いまさら思い返しても仕方のないことを還暦を過ぎても考えてしまう自分がいる。だから、子ども時代の夢を見るのだと思う。
人生は一度きりだ。10代、20代の若い子たちには「自分の気持ちに素直になること」「自分の思い描いている夢は持ち続けること」を大切にしてほしいと声を大にして言いたい。61歳のおじさんは今、「素直」の素晴らしさを噛みしめている。
八月納涼歌舞伎第三部を観ました。「越後獅子」と「野田版 研辰の討たれ」の二演目。
「野田版 研辰の討たれ」。研屋から武士になった守山辰次は素直で人間味の溢れている男だと僕は思う。赤穂浪士の討ち入りが大評判となっても、浅野内匠頭の愚行を非難し、それに対し忠義心をもって仇討して潔く死んだ武士の生き方を否定している。それはひねくれものと片付けてしまってよい問題ではないと思う。寧ろ、研辰の考えの方が賢明ではないかと思う。
仇討礼賛とでも言うべき世の中の風潮を諷刺しているのも良い。確かに研辰は剣術でコテンパンにやられて恥をかいた腹いせに家老・平井市郎右衛門に仕返しをしようとしたことはよくないことだ。でも、まさか死んでしまうとは思わなかった。高齢ゆえに心不全で死んでしまったのか。
それを息子の九市郎と才次郎は「武士の面子を保つため」に、研辰に斬り殺されたことにして、仇討ちの旅に出る。そこがまずおかしいだろう!と僕は思う。二人は道後温泉で研辰を見つけるのだが、逗留先にいたおよし・おみね姉妹の態度の変化も皮肉で面白い。研辰が「父を殺害した九市郎・才次郎兄弟を追っている」と言っていたときには、研辰の妻になりたい!と姉妹は言い寄る。英雄の女房になりたい。仇討ち効果抜群である。
ところが、平井兄弟が研辰こそ自分たちの父を討った仇だと話すと、野次馬たちは急に平井兄弟を応援しはじめ、およし・おみね姉妹も今度は平井兄弟の妻にしてほしいと迫るという…。
最後の大師堂百万遍の場。研辰の「勝負を嫌がっている自分を殺すのは、仇討ちではなく、人殺しだ」と叫び、平井兄弟がひるむ。良観和尚が現れ、「生きたい」と繰り返す研辰を見て、「できることなら助けてやりなさい」と言い残して去ると、雰囲気が一変するのが可笑しい。野次馬たちは別の場所で仇討ちが始まった!と言って、その場を去ってしまう。表面的な仇討礼賛の野次馬たちに対する批判的な眼がこの芝居の眼目に思う。