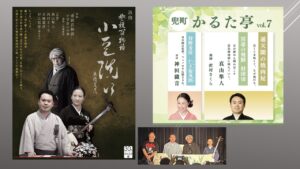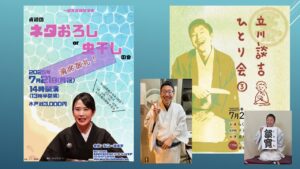奈々福、独演。語り、騙って30周年

「奈々福、独演。語り、騙って30周年」に行きました。
初日 「風流烏」三門綾・沢村まみ/「茶碗屋敷」玉川奈々福・広沢美舟/対談 安田登・玉川奈々福/中入り/「シン・忠臣蔵」玉川奈々福・広沢美舟
二日目 「甚五郎 京都の巻」東家志乃ぶ・沢村まみ/「英国密航」玉川奈々福・広沢美舟/対談 いとうせいこう・玉川奈々福/中入り/「桜の森の満開の下」玉川奈々福・広沢美舟
初日のゲストは能楽師で下掛流ワキ方の安田登先生。観世能楽堂で浪曲の独演会を開いて、ゲストに能楽師をお呼びするという奈々福さんの発想が面白い。奈々福さんは安田先生から、もう10年も謡を習っているのだそうだ。
二人の出会いは奈々福さんが編集者だった時代に遡るそうだが、安田先生の担当編集者は他にいたので、お目にかかりたくても出会いがなかった。それが、新書の担当になったときに、安田先生に書き下ろしをしてもらおうとお会いしたのが最初だったとか。
そのときの安田先生の「奈々福さんの第一印象」が面白い。場所は広尾。別れ際に奈々福さんが「私、浪曲をやっているんです」と告白した。安田先生はちょっと驚いた。というのは、安田先生は銚子出身で、iPhoneに天保水滸伝を入れて聴いているという…。1970年代、ラジオで「早起き浪曲劇場」という番組があって、耳でコピーをしていたとか。
それで、安田先生は思った。そういえば、この女性の目は「普通の目」じゃない、「非社会人の目」だ。獲物を狙うような目。安田先生は「芸人玉川奈々福」を見抜いていたのだ。その後、奈々福さんは筑摩書房を退職し、本格的に浪曲師となり、こうして「芸歴30周年」の独演会を開いている。すごいことだ。
能という芸能は、この能楽堂の舞台で「祝祭」をやって、お客はそれを覗き見するものなのだという。観客は舞台に対し、「意識を飛ばす」ことで能を味わうものなのだそうだ。主役のシテは精霊のような役廻りで、安田先生はワキなので、それを脇で「全身全霊をかけて」何もしない、「座る」ことが役割なのだとおっしゃっていた。これを「煙草盆でもほしくなる」と表現されていたのが面白かった。
また、浪曲は能に近い芸能だとも。能のことを僕はよく判っていないので、僕なりに解釈したのだが、「語るうちに歌ってしまう」芸能という点において共通項があるという。また、弱者の芸能、敗者の物語であるというところも、なるほどと素人なりに合点がいった。
声の出し方は「大きな声というのではなく、残る声という意識で」。実際に、高砂や~のあの有名な謡をやってくださって、「残る声」とおっしゃるニュアンスが少し判ったような気がした。
二日目のゲストは作家でラッパーのいとうせいこうさん。前日の安田登先生から謡を習っている仲間だそうだ。開口一番、浪曲は三味線との伸縮自在なセッションだね、と。古典芸能というと、毎日同じことをしているようなイメージで捉えられてしまうけれど、それは違っていて、例えば能でも流派が沢山あって、各流派が集まって「じゃあ、こうやりましょうか」と毎回演出が異なってくる。そのセッション性を核として捉えなければいけないとおっしゃった。
せいこうさんは義太夫も習っていて、師匠と一対一で稽古するのだが、それは厳しいものだそうだ。今、語った部分はどういうつもりで語ったのか。情景が浮かばない。あなたの頭の中に何が浮かんでいるのか。それを解釈して語りなさいと言われる。だから、お客さんに伝えることができる。念を送る。感情は自ずと付いてくる。詳細は聴き手に委ねる。
小説の世界でも、「描写しすぎるとしくじる」と言われる。それが演劇と語りの違いであり、余白を残すことが大切。奈々福さんが「私は演じすぎるとよく言われる」と。文学も「文芸」というくらいで、芸能。自己表現をしては駄目で、「どう読まれるか」は読者に委ねる潔さが大切という論は大いに肯いた。