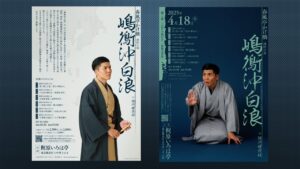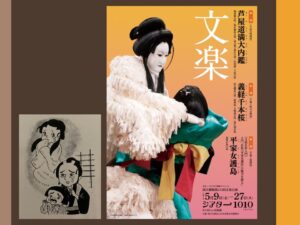貞鏡傳 一龍斎貞鏡「四谷怪談 お岩誕生」、そして落語教育委員会 柳家喬太郎「ぺたりこん」

「貞鏡傳~一龍斎貞鏡ひとり会」に行きました。「仙台の鬼夫婦」「四谷怪談 お岩誕生」「南部坂雪の別れ」の三席。
貞鏡先生の「お岩誕生」は初めて聴いた。祖父の「おばけの貞山」と呼ばれた七代目一龍斎貞山が得意としていた演題だ。田宮又左衛門の娘お綱は七歳のときに酷い病に罹り、醜い顔になってしまった。だが、飯炊きの伝助と深い仲になり、身籠る。形の上では勘当、貧乏長屋に伝助とお綱は住まう。
伝助は高田大八郎の飯炊きとして雇われた。端午の節句。高田の着物の肩に血がついているので、拭いてあげて訊くと、「二階で猫が鼠を食らい、その血が付いた」という。高田が湯に行くが、「二階には決して上がるな」と言い付けた。伝助が飯を炊いて、お鉢によそってると、天井から血が垂れてきて、白い飯が赤く染まった。猫がまた鼠を食っているのか…と主人の言い付けを忘れて二階に上がると、合羽笊の蓋が小刻みに震え、中から人魂のようなものが飛び出した。中を覗くと、首と胴体が切り離されている死骸があった。
高田が湯から戻ってくると、伝助がいない。二階に昇ると伝助がいた。「見たな!」その死骸は霊雁島の金貸し、伊勢屋重助という男だという。5両借りたが、利息が嵩み、15両になってしまった。「返せ」と催促がしつこいので、斬ったのだという。「てめえの命も…」と言われ、伝助は「勘弁してください。何でも言うことを聞きます」と言うので、一両をやる代わりに死骸を棄てて来いと命じられた。
伝助は麻の風呂敷に死骸を包み、背負って屋敷を出た。どこに棄てようか迷っているうちに、自分の住む長屋まで来てしまった。「布団の洗濯」とお綱には言って、押し入れの中にしまう。伝助はこのことを伊勢屋重助の女房に伝えようと家を出る。だが、女房おふみはなかなか帰ってこない亭主が心配になり、高田大八郎のところを訪ね、「悪事が露見してはいけない」と斬り殺されていたのであった…。
お綱がいつ産まれるかわからない身重ゆえ、伝助が傍にいてくれたらいいのに…と帰りを待っていると、足音がする。「ごめんくださいまし…霊雁島川口町伊勢屋重助の女房おふみでございます…ここでお世話になっているそうで…押し入れの中で麻の風呂敷に包まれている…会わせていただきたい」。そして、おふみは勝手に上がり込み、奥の押し入れを開け、中から重助の血の滴る生首を取り出し、抱えた。「主人がここにおりました」と言って、へへへと笑う。
お綱は余りの恐ろしさに産気付き、女の子を産み落として、息絶えてしまった。隣のおきん婆さんがやって来ると、そこには生首と赤ん坊が並んで置いてある。お綱の父、田宮又左衛門はこの赤ん坊を引き取り、お岩と名付けた。このお岩が成長し、榊原数馬という男を婿に迎え、田宮伊右衛門と改名するが、この伊右衛門こそ高田大八郎の倅だという因縁がこの後に展開していく…。
「四谷怪談」の序開きだが、おふみが高田大八郎の屋敷を訪ね、「自分の亭主はいますか」としつこく訊ね、挙句に斬り殺される場面の描写がなく、単に一言伝聞調で「このとき、おふみは高田大八郎に斬り殺されていた」とあっさり済ませていた。そのためか、その亡霊がお綱のところに現れる「この読み物の最大のクライマックス」を折角鳴り物入りで雰囲気を盛り上げていたのに、やや「怖さ」が弱い印象だったのが残念だった。
「南部坂雪の別れ」。殿中刃傷から内匠頭切腹までをダイジェストで語った後、本題に入った。瑤泉院の許を久しぶりに訪れた大石内蔵助が仇討本懐をぬかりなく成功させるために本心を明かさないところがこの読み物の肝だろう。「いよいよ本望を遂げるときがきたな。日は決まったか。教えてくれ」と言う瑤泉院に対し、ここで手筈は整ったと言えば喜ぶだろうが、見知らぬ腰元も同席している、間者でもいて秘密が露見しては…と警戒する大石は流石である。
「本望とは何のことでしょうか。無念を晴らし、仇討ちをすると?私は山科に永住し、百姓をするため、暇乞いに来たのです。時が経つにつれ、仇討の同士は減ってしまいました。事の起こりは殿の短慮。仇討などというお上に歯向かうようなことはできません」。
瑤泉院がそれは本心か?と訊くと、「武士は嘘偽りは申しませぬ」。田村邸で殿が片岡源五右衛門に「余は無念じゃ」と大石に伝えてくれと頼んだことを引き合いに出し、なおも問い質す瑤泉院。「この位牌に対し、申し訳ないと思わぬのか?」。大石は「身に覚えのないこと」と心を鬼にして答える。ついに、瑤泉院は「二度とそなたと会うことはありません。さらばじゃ」と立ち去る。
戸田局がさらに大石に念を押すが、「思いもよらぬこと」と一蹴する。そして、東下りのときに詠んだ歌だと言って、巻物を袱紗に包んで渡す。だが、それが大石のメッセージだったというのがドラマチックだ。
最近に召し抱えた紅梅という腰元が実は間者で、その巻物を戸田局の寝間から盗み出そうとしたことがきっかけで、四十七士の仇討血判状であることが顕われる。慌てて、戸田局は瑤泉院の部屋へ行き、その血判状を見せる。「やはり、大石は別れを告げに来たのか…そして、心無きことを並べたのか」。瑤泉院が巻物に書かれた四十七士の名前を読み上げる。この読み物の最大のクライマックスは感動的だ。今年3月の有楽町朝日ホールで「南部坂雪の別れ」をネタおろししたときには、この四十七士読み上げがなかったが、きょうこうして仕上げてきた貞鏡先生に拍手喝采を贈りたくなった。
「落語教育委員会」に行きました。三遊亭兼好師匠が「兵庫船」、三遊亭歌武蔵師匠が「家見舞」、柳家喬太郎師匠が「ぺたりこん」だった。開口一番は三遊亭萬都さんで「熊の皮」、オープニングコントは「夢グループ編」だった。
兼好師匠の「兵庫船」。江戸っ子二人組が地元の人と謎かけで遊ぶ風景が楽しい。鮫がガリガリ、プクプク、パクパクという擬態語表現も面白い。鮫に見こまれた講釈師、二流斎停船が繰り出す五目講釈のクオリティが高いのは、流石兼好師匠である。武蔵坊弁慶、お富与三郎、平知盛…と四十七士が出てこない赤穂義士伝というのが可笑しかった。
喬太郎師匠の「ぺたりこん」は三遊亭わん丈作品。仕事ができなくて、どんどん出世が遅れて、会社のお荷物になっているタカハシさんも血が流れている人間である。笑ってはいられない、切なくて悲しい不条理落語だと思うし、喬太郎師匠が演じることで身に詰まされるものがある。感動的とすら思うのは、僕がタカハシさんに共感を覚えるからだろうか。
タカハシさんの左掌が机に引っ付いて剥がれなくなってしまった。ワタナベ課長はそれをいいことに、常務と結託して、“かねてからの懸案”を解決することを思い付く。就業規則第8条、社員は犬に尻を噛まれてはいけない。就業規則第26条、社員は掌を机にくっ付けてはいけない。この二つに抵触するから、解雇になるところだが、温情案としてタカハシさんを「こういう形をした机」とみなし、月々の備品使用料を払うという。
あなたは素直に会社をやめますか、それとも備品として会社に残りますか。タカハシさんは「俺はモノか?汗も出れば、涙も出る。俺は人間だ」と高らかに叫ぶが、住宅ローンも残っているし、子どもの受験も控えている。「机になります。備品としてよろしくお願いします」。折れた。切ない。
最も哀しいのは自宅への電話だ。「しばらく帰れないかもしれない。私、机なんだよ。デスク?そういう意味じゃない」。息子のケンイチは高校をやめて働くと言い出す。サユリは楽しみにしていた西武園に一緒に行けなくなり、「どうしてパパは机になっちゃったの?」。「大人になればわかる」と言って、電話を切りたいタカハシさんだが、「サユリの方から切ってくれないと…パパからは切れないから」。涙が出そうだ。
タカハシさんは憔悴し、一カ月半後に息を引き取った。会社は遺族に億という額の慰謝料を払った。そして、ワタナベ課長は解雇となった。就業規則に違反したからだ。就業規則第3条、社員は机に座ってはいけない。
僕は退職する前の一年間、自分の机を奪われてしまった。職場に外部パワーの人たちが溢れたために、ある一定の地位以下の職員は外部パワーの人たちと一緒に大きな共用机を使いなさいという決定だった。番組の企画を考え、取材し、構成する仕事をする人間が職場から自分の机を奪われた屈辱は耐え難いものだった。僕は職員としてのアイデンティティを失い、それが退職の一因になったことは否めない。この噺を久しぶりに聴いて、タカハシさんに自分を重ね合わせた。