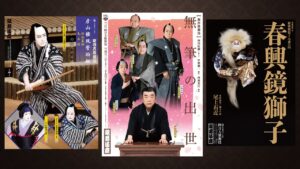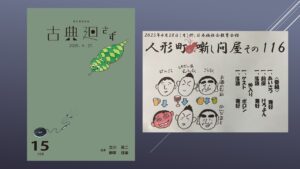べらばう~雲助廓乃御伽噺~ 五街道雲助「お直し」「五人廻し」

上野鈴本演芸場四月下席六日目夜の部に行きました。今席は五街道雲助師匠が主任を勤め、「べらばう~雲助廓乃御伽噺~」と題したネタ出し興行。①お見立て②干物箱③明烏④幾代餅⑤居残り佐平次⑥お直し⑦五人廻し⑧品川心中⑨付き馬⑩木乃伊取り。きょうは「お直し」だった。
「寿限無」翁家丸果/「猫と金魚」桃月庵白浪/太神楽曲芸 翁家勝丸/「魚男」古今亭志ん五/「道灌」蜃気楼龍玉/民謡 立花家あまね/「ミステリーな午後」柳家小ゑん/「天狗裁き」むかし家今松/中入り/奇術 アサダ二世/「短命」古今亭菊之丞/紙切り 林家二楽/「お直し」五街道雲助
雲助師匠の「お直し」。お茶を挽いて辛い思いをしている女郎に、若い衆が温かい声を掛けてあげているうちに深い仲になってしまうのはよくわかる。だが、廓で働く男女が出来てしまうのはご法度。それを目ざとく見つけた主人の温情が良い。証文を巻いてやり、夫婦として引き続き自分の店で働きなさいというのだから。
遣り手として再起した女の方は感謝の心を忘れずに仕事に精を出す。だが、男というのはどうして駄目なんだろう。千住で遊び、居続けをし、さらには博奕に手を染める。無断欠勤だ。女房も言い訳が続かず、店は首になってしまい、元の木阿弥。食うに困る貧乏暮らしだ。
男が「目が覚めた。やり直そう」と、女房に持ってきた話は蹴転(けころ)、羅生門河岸だ。若い衆は俺がやる。お前は女郎をやれ。背に腹は代えられない。女房は腹を括る。そして、「お前さんも覚悟が必要だ」と言う。すなわち、焼き餅を妬いていては仕事にならない。お線香の本数で代金が決まる。客を繋ぎ止めるために甘い言葉で引っ張る。そこでいちいち焼き餅を妬いていたら商売にならない。男も承知した。
職人風情の男の着物の袖の中に手を入れて引っ張り込む。「相方の面が化け物みたいに酷いから抜け出して来た」という客は、どうせ蹴転の女郎だろうと疑い深かったが、女を見てすっかり気に入る。「あれかい?驚いた。いい女だ。掃き溜めに鶴だ。本物?看板じゃないの?」。女はここぞとばかりに誘う。「寄ってらっしゃいよ。あら、冷たい手をして…どこで浮気してきたんだい。様子がいい…女がほっておかないよ」。
客が訊く。「お前みたいないい女がなぜこんなところにいるんだ?…金だよな…いくらだ?」「30両なんだよ」「俺が30両持ってきたら、女房になってくれるか?」「こんな嬉しいことはないよ。願ったり、叶ったりだよ」「今、請け負っている蔵の仕事が終わると、30両入る。親許身請けということにして、夫婦仲良くしようじゃないか」「ようやく甲斐性がある人に巡り会えたよ。これで私も浮かび上がれるよ」。
「近いうちに金を持ってくるから待っていてくれ」「嬉しいよ。夫婦になったら、たまには喧嘩もしたいね。いくら打たれても、半殺しにされてもいいよ」「俺が仕事から帰ったら、湯に行って、膳には酒と肴。差し向かいで、やったりとったりしたいな」「夢のようだよ」「俺とお前は夫婦だよ」「きっとだよ」。
ようやく客が帰るまで、男は「直してもらいなよ」を6回言った。そして、「馬鹿馬鹿しい!よすよ!本当に夫婦になるのか!いくら打たれても、半殺しにされても?…あいつの手を握ったときの目付きが只事じゃない!」と怒り出す。すると、女は「それじゃ、私もよすよ!何もやりたくて、やっているんじゃない!お前がやらせているんじゃないか!それを、よしやがれ!とは何だい!」。
女が「お前さんの親切が忘れられないから一緒になったんじゃないか。この人と離れたくないと思ったから、一緒にいるんじゃないか。それを、つまらない焼き餅を妬いて…酷すぎる!」。男は謝る。「俺が悪かった。お前に惚れているから、つい焼き餅を妬いてしまったんだ」「昔、一つの鍋焼きうどんを二人で食べた。こんな温かい気持ちになったのは初めてだった。生涯、忘れないよ」「勘弁してくれ。よりを戻すもなにも、お前と一緒にいたいんだ」。
蹴転という最下層まで堕ちた男女だが、そこに本当の夫婦愛があることを確認できたことが素晴らしいと思った雲助師匠の高座だった。
上野鈴本演芸場四月下席七日目夜の部に行きました。五街道雲助師匠が主任を勤める「べらばう~雲助廓乃御伽噺~」と題したネタ出し興行。きょうは「五人廻し」だった。
「長屋の算術」桃月庵白浪/太神楽曲芸 翁家勝丸/「駐車券」古今亭駒治/「もぐら泥」蜃気楼龍玉/民謡 立花家あまね/「弟子の強飯」春風亭百栄/「てれすこ」むかし家今松/中入り/奇術 アサダ二世/「猫と金魚」古今亭文菊/ものまね 江戸家猫八/「五人廻し」五街道雲助
雲助師匠の「五人廻し」。一人目の職人風の男。壁の落書き、「女郎屋の二階と梅雨時の空 ふられふられて嫌になる」。勘定書きの金3円50銭を見て、「襟巻でも買っておけば良かった」。「かみさんは有難い。廻しを取らないし、銭もかからない。大事にしよう」も、けだし名言。喜瀬川への伝言、「客を振るような面か!ケツでも振ってろ!」。若い衆に「人間らしいのをよこせ」と言うと、「私が寝ずの番でして。私が二階を廻る。これが吉原の法、これすなわち廓法で」と返され、「すなわち?擂り鉢みたいな顔をして」。そして、オギャーと生まれて三歳から婆さんに連れられて吉原に通っていると言って、「そもそも吉原は…」と故事来歴を早口で並べて、「頭に味噌付けて食っちまうぞ!」。江戸っ子口調も素晴らしい。
二人目は通人。「拙宅にもお立ち寄り願いたいね」と若い衆を呼び込み、「もちりん。角が取れて丸い。貰いものの角砂糖」と変な持ち上げ方をした後、「尊君などはさぞ御婦人を泣かせたんでありんしょう。その罪滅ぼしでここで働いている。のろけを聞きたいね。ありあしょう?」。そして、嫌味が飛び出す。「傍に姫がいた方が愉快か、誰もいない方が愉快か、そのへんのところを伺いやしょう」。吉田兼好の「傾城傾国に罪なし、通う客人に罪あり」。そして、「柔らかそうな手を握らせたまえ…」。
三人目は軍人風。「給仕!前へ進め!」。若い衆の年齢を問い、「四十二」と答えると、「そのような歳をして、夜具布団の運搬をして、どこが面白い?このような職業をするために両親は君を教育したわけではなかろう」と問い詰める。空々寂々という言葉のセレクトも良い。陰鬱な部屋を「見るが如くの惨状」と言い、「枕がここに二つある。一つは私が使うとして、いま一つは何人が使用する枕か?…あの娘(こ)さん?面を一度も見せない」。そして軍人調に「男子が女郎部屋に登楼する目的は何か?女郎買いの本分とは何か?」と叫んだ後、領収書を差し出し、「娼妓揚げ代金とあること、甚だ理解に苦しむ。もはや有名無実である!」。もっともだ。
四人目は田舎のお大尽。「チョックラ、コケッコ!」。「客を振るなら、田舎者を振れ。おらは日本橋の在、江戸っ子の中の江戸っ子だ」。愚痴を言いながら手鼻をかむ。可笑しい。
最後は関取。喜瀬川が来ないので、四股を踏んでいる。で、若い衆が「廻しを取って、振られています」で、サゲ。五人五様の人物造型もさることながら、その人物の台詞が細部にわたって精巧かつ正確で、後輩たちが手本として見習ってほしいと思える、「人間国宝の高座」であった。