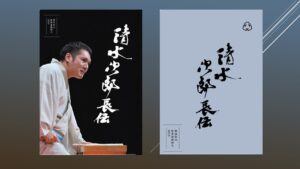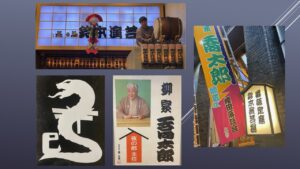鈴本演芸場正月二之席 柳家喬太郎「按摩の炬燵」

上野鈴本演芸場正月二之席初日夜の部に行きました。主任は柳家喬太郎師匠、今席の興行は昼の部(主任:春風亭一之輔)も夜の部も土日祝の5日間は前売り指定券が販売された。満員御礼の盛況だった。
「転失気」柳家やなぎ/奇術 ダーク広和/「一目上がり」入船亭扇遊/「おもち」林家きく麿/漫才 風藤松原/「徂徠豆腐」宝井琴調/「旅行日記」柳家三三/中入り/紙切り 林家八楽/「馬のす」橘家文蔵/ものまね 江戸家猫八/「按摩の炬燵」柳家喬太郎
喬太郎師匠の「按摩の炬燵」。奉公は修行、暑いだとか寒いだとか不平を言ってはいけない。それは生意気であり、贅沢である。番頭さんが小僧たちに諭す言葉に説得力がある。現代では通用しない理屈だろうが、それで辛抱して、商人は出世していくものだったろう。
番頭さんが偉いのは、どんなに上の立場に立っても、炬燵も行火も入れないことだ。私がやれば若い者が真似をする、若い者がやれば小僧が真似をする、それで万が一火事でも出したらご主人様に申し訳が立たない。実るほど頭を垂れる稲穂かな。
こういう了見の番頭さんの頼みだから、按摩の米市さんは“自分が炬燵になること”を怒らずに承諾してくれた。番頭さんが小僧たちに厳しいことを言った後で「寒いなあ」と言葉を掛け、「私が米市さんに怒られてあげる」と昔からの友達である米市さんに“炬燵になってくれないか”と頭を下げた。米市さんも番頭さんの心意気に打たれ、「なりましょう!」と答えた。
酒を飲む米市さんが素敵だ。「良い酒で良い燗、文どんが付けたのかい?いける口だね」と美味しそうに飲む。ハゼの佃煮を肴に、実に美味しそうだ。「良い炬燵になれそうだ」というのも洒落が利いている。嫁さんを貰わないかと言われるが、私は独りが楽でいい、これ(酒)がかみさんだよ。愚痴も聞いてくれるし、心も身体も温めてくれる。こんな良いかみさんはいないよ。
子どもの頃の思い出話も良い。番頭さんには昔から仲良くしてもらった。ガキの頃は柿を盗んだりして悪かったんだよ。十二のときまで寝小便もしていた。子ども時分は遠慮がない。「やーい、めくら!」と囃したてる。庇ってくれたのは、いつも番頭さんだった。そう、いつも番頭さん。ありがとうね。
五合の酒を飲み干し、身体が温まった米市さんは番頭さんの部屋で炬燵の形になる。番頭さんだけ当たるのかと思ったら、小僧が皆やって来て、手なり足なりを当てて寝転がる。「皆、寝ちまった。疲れているんだね。綿の如くという奴だ。皆、一生懸命に昼間働いているんだ。こうやって、皆、偉くなるんだな」。米市さんの小僧たちへ向けた優しい眼差しがとても素敵な高座だった。