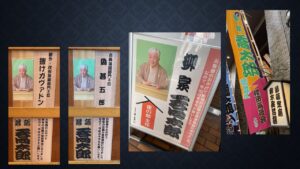浪曲定席木馬亭 澤雪絵「お富与三郎 稲荷堀」天中軒雲月「佐倉宗吾郎 妻子別れ」

木馬亭の日本浪曲協会七月定席初日に行きました。
「梅花の誉れ」玉川き太・玉川鈴/「双葉山」東家三可子・馬越ノリ子/「大前田英五郎 島抜け」天中軒景友・佐藤一貴/「クラシカ浪曲 歓喜の歌」港家小ゆき・沢村道世/中入り/「安兵衛婿入り」国本はる乃・沢村道世/「ピクサーを創った男」神田桜子/「鰍沢」鳳舞衣子・沢村道世/「お富与三郎 稲荷堀」澤雪絵・玉川鈴
小ゆきさんの「歓喜の歌」。ベートーヴェンが新しい交響曲を作ろうとする情熱と、小ゆきさんが創作浪曲に懸ける情熱がオーバーラップしているように感じた。それほどにパッションを感じる高座だった。
交響曲に合唱を組み込むというベートーヴェンの斬新な発想に、カロリーネは魂が震え、狂喜乱舞した。だが、再び会ったときにはベートーヴェンは激しく落ち込み、頭を抱えて「わからなくなった」と悩んでいた。この様子を見たカロリーネはベートーヴェンに檄を飛ばす。あなたの音楽でこれまでどれほどの人たちが救われてきたか。そして、あなたの新しい音楽をどれほどの人たちが待ち望んでいるのか。ベートーヴェンは迷いを振り切り、強い心をもって作曲に臨み、12年ぶりの交響曲、第九「合唱付き」は誕生し、今も多くの人々に勇気を与えているという…。客席と演者が一体となり、歓喜の歌を歌うという見事な高座だった。
舞衣子先生の「鰍沢」。呉服商の新助が月の輪お熊に痺れ薬を入れた玉子酒を飲まされ、逃げるところを鉄砲を持って追いかけられたが、九死に一生を得た。その3年後を描いているのが良い。
新助は越前屋という立派な店を構え、商売も繁盛していた。そこへ乞食となったお熊が物貰いに来るのだ。「あれから二カ月後に亭主の伝三郎は死んだ。これも悪事の報い」と懺悔する。すると、新助は自分の命が助かったのは身延のお陰と言って、お熊を越後屋の下女として働かせる。慈悲深い。お熊はこの情けに感謝し、越後屋に尽くして生涯を終えたという筋書き。なかなか興味深かった。
雪絵先生の「お富与三郎」。一度は死んだとお互いに思っていたお富と与三郎が江戸で再会し、悪党として生きていく過程として描かれているのが面白い。
多左衛門の旦那の妾として囲われているお富。だが、坊主の富が多左衛門に「お富は与三郎と通じていて、旦那に毒を盛って殺そうとしている」と告げ口をする。その様子を押し入れに隠れて聞いていた与三郎は、坊主の富の後を追い、稲荷堀で鯵切り庖丁で殺害した。このことを聞いたお富は「止めは刺したのかい?」と訊く。与三郎は元伊豆屋の若旦那。詰めが甘い。「鯵切り庖丁は刺したまま…忘れてきた」。
お富と与三郎は二人で稲荷堀へ。坊主の富がいない。「きっとそこらに隠れているよ」。いた。「与三さん、自分で蒔いた種だ。やっておしまい!」。瀕死の坊主の富の息の音を止め、死骸は川の底に沈める。その前に、「旦那から褒美に貰った3両があるはず」と、坊主の富の懐から3両を抜き取ることも忘れない。「大層、役者があがったね」。所詮二人は悪縁、汚れた体だ。生きて良かったと夜をしっかり抱いて抱かれて確かめて、もう夜が明ける東雲の、消えて儚い横櫛はお富与三郎、流す浮名の玄冶店。「お富与三郎」、落語も講談も良いが、浪曲も良い。
木馬亭の日本浪曲協会七月定席五日目に行きました。国本晴美先生の一周忌企画ということで、トリに2016年5月木馬亭での収録映像が流れた。
「琴櫻」天中軒かおり・沢村博喜/「悲母大蛇」富士実子・伊丹秀勇/「源太しぐれ」国本はる乃・沢村道世/「亀甲組 加太山」港家小柳丸・沢村道世/中入り/「真柄のお秀」玉川福助・玉川みね子/「出世証文」神田こなぎ/「佐倉宗吾郎 妻子別れ」天中軒雲月・沢村博喜/「仲乗り新三」国本晴美・伊丹秀敏(映像)
はる乃さんの「源太しぐれ」。女義太夫語りの竹本小芳ことお芳が源太郎に10両で頼まれて打った祝言をぶち壊す芝居。だが、お芳は本当に源太郎のことが好きなってしまう…。切ない恋心が良い。
甲州上野原の一膳飯屋で暑さしのぎに冷や酒を5、6本呷ったお芳だが、いざ勘定となると持ち合わせがなくて、「義太夫で払う」と言い出す。困った店主に対し、「俺がその勘定を払う」と進言する男。博奕打ちの信楽屋徳兵衛親分の子分の源太郎だ。ただし、源太郎はお芳に一芝居打ってほしいと頼む。
徳兵衛は相撲上がりの久右衛門に喧嘩を売られ、これを片づけてくれれば一人娘のお藤の婿に源太郎を迎えてやって、跡目を譲るという。だが、お藤には喜助という惚れた男がいた。それを慮って、源太郎とお藤の祝言の席にお芳が「源太郎と言い交わした女房だ」と言って乗り込み、婚礼をぶち壊してほしいという筋書きだ。
お芳はこれを引き受け、「源太郎が6年前に剣術の修行で江戸へ行ったときの女房。本所で所帯を持ったが、急に姿をくらまし、なしのつぶて。思うはあなたのことばかり」と、目に涙をいっぱいに浮かべ、徳兵衛を納得させた。源太郎は「お嬢様の幸せを祈っている。喜助、幸せにしてやってくれよ」と言って、お芳と一緒にその場を去る。
お芳は「この芝居が本当だったら…いっそ本当にして、私を連れていってくれ」と源太郎に言う。だが、源太郎は「俺は旅烏」と意に介さない。「待っておくれ…」と追うお芳。はる乃さんの感情のこもった高座に胸がキュンとなった。
雲月先生の「佐倉宗吾郎妻子別れ」。宗吾郎が380ヶ村、5万人の人々を救うために、磔獄門を覚悟で上野東叡山寛永寺に墓参する将軍に直訴する決意をするが、残された妻と4人の子どもへの情愛を棄てなければいけない。その葛藤が良く描かれていて、雲月先生のネタの中でも大好きなネタだ。
雪降る中、甚兵衛に無理を言って渡し船を出してもらい、家族の許を訪ねた宗吾郎は妻のおさんに離縁状と子どもたちへの勘当状を袱紗包みに入れて渡す。残る子どもに罪はないが、夫婦とはそのようなものではない。真の夫婦は共にあるべきではないか。生きながらえるつもりはない。4人の子どもは水戸様の領地にいる伯母に預け、あなたと一緒に私は死ぬ…そういう妻おさんの気持ちに胸が熱くなる。
「お前が泣けば、わしの心も鈍る」と宗吾郎は言って、「名残は尽きぬ。さらば」と強引に帰ろうとする宗吾郎に対し、おさんは「この世の別れ。せめて一目でも子どもの顔を見てやってくれ」と懇願する。一番幼い赤子を抱いた宗吾郎は、自分の顔を擦りつけて、思わず落とす一滴。赤子が泣き出すと他の子どもも気づいて、「お父ちゃま、待って。おいたはしないから、一緒にいて」と叫ぶ。
宗吾郎の心は揺れる。いっそ、このまま留まろうか。いや、しかし、そうじゃない。もしもこの身が留まれば、5万人の人々が救えない。親子の愛も何のその。ここが我慢のしどころだ。「お父ちゃま、待って!」という声が遠ざかる。これがこの世の別れかと、男泣きする宗吾郎の心中いかばかりか。
たとえ、その名は朽ちるとも。残るその名はいつまでも。佐倉の村民たちを救うという使命のために自らを犠牲にする漢気に酔う。