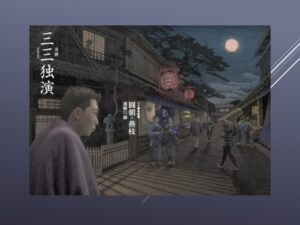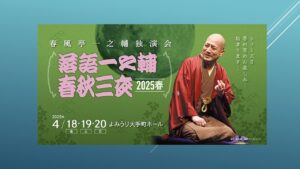落語一之輔春秋三夜 第一夜 春風亭一之輔「たちきり」
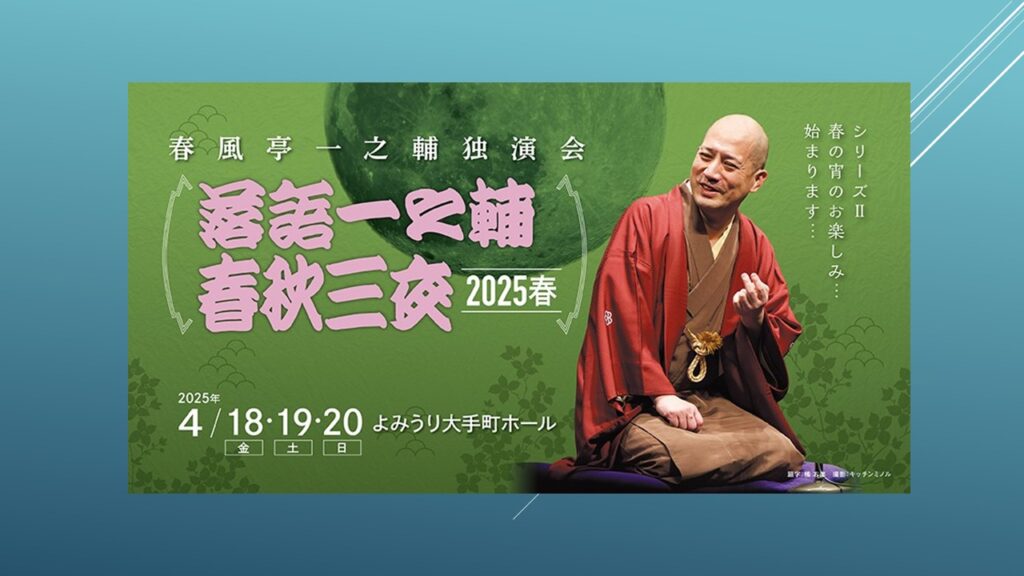
「落語一之輔春秋三夜 2025春」第一夜に行きました。「ちりとてちん」「ぜんざい公社」(ネタおろし)「たちきり」の三席。開口一番は春風亭貫いちさんで「真田小僧」だった。
一之輔師匠は一席目の出囃子が♬MajiでKoiする5秒前、二席目の出囃子が♬大スキ!マクラで広末涼子は自分の三歳年下、「高3のときに彼女は中3ですよ…70代、80代のお客様にとっての吉永小百合みたいなもの」と言って、落語協会の新弟子年齢制限を今の30歳から45歳に引き上げて、ヒロスエが自分の弟子になったら…と妄想するのがとても愉しかった。
「ちりとてちん」。お世辞を並べる金さんが、まず好きだ。酒が喉を通るとき、「私、灘の生一本です…通ってもよろしいですか…失礼いたします」と言いながら通ったとか。鯛の刺身を食べたとき、「僕は鯛ですよ…」と口の中で言い残して自分の意思を伝えるのは大したものとか。腹の中で灘の生一本と鯛の刺身が「ようやく会えたね!」と喜び合っているとか。
隠居が腐った豆腐に唐辛子を混ぜるとき、「3分キューピークッキング」のテーマ音楽を鼻唄で歌っているのも可笑しいが、この異物を瓶に詰めたところで、女中のお清は全て了解していて、これを「ちりとてちん」と名付け、すぐに知ったかぶりの六さんを呼びに行くのも面白い。六さんがそのちりとてちんを相手に悪戦苦闘している様子を見て、キャッキャッ!と笑いながら喜んでいるのはお清だ。
六さんの強がりも面白い。ちりとてちん?あれが日本に来たんですか?あれは朝に良し、晩に良し。匂いが身上、匂いで食うもの。台湾では冠婚葬祭に必ず出る。懐かしいなあ。カカアと知り合ったのも、これがきっかけ。ちりとてちんを求める行列に並んでいて、俺のところで売り切れになった。その後ろにいたのが今のカカアで、「おひとつ、いかがですか?」と声を掛けたのが馴れ初め。ちりとて婚。酒にも合うし、おまんまにも合う。パンに塗る、うどんにからめる。何でも美味しい。
隠居が「私の前で食べておくれよ」と真剣な目付きで言うと、「勿体ない」とか言ってはぐらかす六さん。隠居は「本当は食べたことないのか?」と迫ると、「ありますよ!」。箸も匙も要らないと言って、瓶ごと口に流しこもうとする。「ちりとてちんは喉ごし!」と言って、踊りながら食う。ちりとての舞い。お清は団扇で仰ぎ、手拍子を叩いて、大喜び。最後は六さん、鼻をつまんで、口の中に入れ、悶絶。ようやく飲み込んで、「最高!」。実に愉しかった。
「たちきり」。柳橋の久野屋の芸者・小久と深い仲になった若旦那は店の金を使い込む。これでは店を食い潰してしまう。金の有難みを知ってもらうためを考え、大旦那承知の上で番頭は「百日に蔵住まい」を若旦那に命じる。芝居見物の約束をしていた若旦那が何日も来ないので、小久は手紙を書いて届けていたが、番頭が引き出しに仕舞ってしまったので、若旦那の目に触れることはなかった。百日経った後に、番頭が「柳橋より」という手紙が八十日届いていたが、「やはり花柳界、馬を牛に乗り換えたのでしょう」と言って、若旦那に最後に届いた手紙を読み上げる。若旦那は居ても立っても居られず、浅草の観音様に願掛けしていたので御礼参りに行くと言って、真っ直ぐ柳橋に向かう。ここのところ、僕は個人的には番頭のおこなったことの是非に少々首を傾げる。「百日ずっと手紙が届いていたら、若旦那とその芸者を添わせてもらえるように大旦那に進言しようと思っていた」と言うのだが、それならもっと早くに小久の誠意を汲むこともできたのではないか、と思う。
若旦那は「かあさん、小久はいるかい?お稽古?それとも、お座敷?…これまで都合があって来られなかったんだ。ごめんなさい」。かあさんはこちらに上がるように言って、白木の位牌を見せる。「嫌なことをするね。意趣返し?」と言う若旦那に対し、かあさんは「あの子、こんな姿になっちまいました」。「死んだ?何で?」と激しく迫る若旦那に、「何で死んだと言われたら、あなたが殺した言いたくなるじゃないですか」。すごく強い台詞である。
お芝居見物の約束の日。寝坊の小久が珍しく早くに起きて、化粧をしていた。だが、待てども、待てども若旦那は来ない。泣き腫らし、真っ赤な目をして、「お手紙書いてもいい?」と訊く小久を拒むことはできなかった。何通書いても返事がない。「私、捨てられたのかもしれない」。手紙を書く本数は増えても、一向に若旦那からの連絡はない。痩せ衰えて、寝込んでしまった。「私、生きていてもしょうがない。捨てられたんだ」。
亡くなる日の昼、若旦那が誂えた三味線が届いた。若旦那と小久の比翼の紋が付いている。小久は初めてニコッと笑い、「弾きたい」と言った。おなかが身体を抱えて、たった一撥弾いて、それっきり。小久は息を引き取った。
「知らなかった。わかっていたら、蔵を蹴破ってでも出てきたのに」。百日の蔵住まいのことをかあさんは知り、「それじゃあ、手紙を読んでもらう気遣いもないですねえ」と悲しむ。「皆、私が悪いんだ。ごめんなさい」と謝る若旦那に、三七日だから供養してくださいと言うかあさん。「ご縁がなかったんですね」。
若旦那は大きな茶碗に酒を注いでもらい、一気に呷り、咽ぶ。そのタイミングで三味線が鳴り出す。「あの子、若旦那の好きだった黒髪を弾いていますよ」。「小久!ごめんよ。勘弁してくれ。お前のことをわかっていたら、飛んできたのに。俺、決めた。生涯、女房と名の付く者は持たない。必ず、そっちへ逝く。そして、一緒になろう。許してくれ」。
三味線が鳴り終わる。かあさんの「今の言葉を胸にしまって、綺麗なところへお参りしてね」。悲恋である。もう少し、何とかならなかったものか。とてもやるせない気持ちになった。