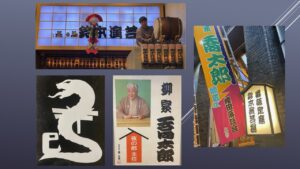通し狂言「彦山権現誓助剣」四幕七場

国立劇場初春歌舞伎公演 通し狂言「彦山権現誓助剣」四幕七場を観ました。
六助がヒロインお園と出会う「六助住家」、いわゆる毛谷村の場面のみが演じられることが多いが、今回はその前の発端「豊前国彦山権現山中の場」、序幕「周防国太守郡家城外の場」「長門国吉岡一味斎屋敷の場」、二幕目「山城国小栗栖瓢箪棚の場」が上演され、三幕目の“毛谷村”へと続く形の通し狂言だったので、人物関係が明確になって楽しめた。
吉岡一味斎は周防・長門を治める郡家の剣術師範であり、毛谷村六助の技量と心底を見込んで自身の跡継ぎにしようと、八重垣流の奥義の一巻を授ける。だが、一味斎は浪人上がりの京極内匠が闇討ちにして、殺されてしまう。一味斎の下の娘・お菊を妻に望んだが認められない上に、御前試合で打ち負かされたことを根に持って、恥辱を雪いだのである。
このとき、一味斎の上の娘・お園が父を迎えに来ていて、逃げようとする内匠の片袖を奪った。倒れているのが父であることに気づき、あの男が父を殺したのだと知る。このことを母・お幸に知らせなければいけないが、余りに悲しく無念であるために、お園は酒に酔ったふりをして伝えるのが切ない。駕籠に亡くなった父を載せて座敷に運ばせ、中に変わり果てた一味斎の姿があるのを確かめさせてから、取り乱す母と妹に父の最期を語る…。
二幕目でお園は今度は妹のお菊の死を知る。お園と別れて敵の行方を追っていたお菊とその息子・弥三松だったが、摂津国須磨浦でお菊は何者かに殺されたと供をしていた友平から聞く。弥三松が難を逃れたのは不幸中の幸いだったが、と同時に現場に守り袋が落ちていたのが手掛かりとなる。その守り袋には臍の緒書が入っていて、「永禄九年五月十日の誕生」と記されていた。瓢箪棚の場で突然、京極内匠が現れ、お園は近づいて、臍の緒書の生年月日が内匠と一致することが判り、お菊を殺害した下手人だと確信する…。
ここまでの吉岡一味斎、その妻お幸、長女お園、次女お菊、次女の息子弥三松の関係、そして京極内匠を仇討しなければならない経緯が判ると、三幕目の毛谷村六助住家の場が良く理解できる。旅姿のお幸が六助に対し、素性を隠して自分を母にしてくれと切り出したこと。彦山杉坂墓所の場で内匠側の山賊に追い立てられ深手を負った佐五平が連れていた弥三松を六助が助けてやり、自分の子どものように世話をしていたこと。そして、虚無僧に身をやつしたお園が弥三松の着物が干してあるのを見つけ、六助が「家来の敵」だと勘違いしたが、実は命の恩人だったこと。これらが繋がるのが芝居の面白さだ。
六助は彦山で一巻を授けてくれた吉岡一味斎の娘がお園だと知り、お園も父が「お前の夫に」と望んでいた人物こそ六助だったことを喜んだ。さらに、お園は父が京極内匠に殺され、仇討の途上であること、お園の妹お菊は内匠の返り討ちで命を落としたこと、その子どもが弥三松であることを明かし、仇討ストーリーが収束に向かっていくのが面白い。そこへお幸が実は一味斎の妻だと言って、部屋から出て来るのだから。引き出物で夫の形見の刀を差し出して、六助とお園の祝言をあげるという…。
さらに微塵弾正実は京極内匠が彦山杉坂墓所の場で、「親孝行」と言って六助を騙し、勝ちを譲ってほしいと頼んで六助との試合に勝利したばかりでなく、「親孝行」芝居に利用した斧右衛門の母を亡き者にしたことが判り、六助は怒りに震える。
お幸が持つ人相書、お園の持つ臍の緒書も証拠となり、「京極内匠、許すまじ」とお幸、お園、弥三松、そして六助が一致団結する。大詰の「豊前国小倉真柴大領久吉本陣」へと乗り込み、見事に本懐を遂げる大団円。お正月興行に相応しい、めでたい芝居であった。