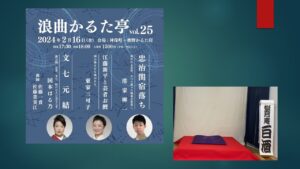春風亭朝枝「七段目」、そして高円寺演芸まつり おしくら饅頭、四派でドカン

「朝枝の会~音曲噺の世界」に行きました。春風亭朝枝さんが「七段目」をネタ卸し、しかも鳴り物入りで挑戦するというので伺った。ほかに「普段の袴」「甲府ぃ」の三席。開口一番は三遊亭まんとさんで「狸の鯉」、ゲストは三遊亭好二郎さんで「元犬」だった。鳴り物は三味線が田村かよ師匠、太鼓はまんとさん、附けは好二郎さん。
「七段目」。若旦那の芝居気違いぶりを愉しく描く。外科のお医者先生を乗せた同じく芝居好きの鉄っつぁんが曳く人力車を強引に止めてしまったり、巡礼の親子が訪ねてきたときに出身は「越後の新潟」だと言うのに「阿波の徳島」じゃないと許さなかったり。大旦那が「帰りが遅い。芝居でも観ていたのだろう」と小言を言うと、「晦日に月の出る里も闇があるから気をつけろ」と芝居台詞で返し、二階への階段を「八百屋お七」に見立てて、トッチンチンと昇るのも面白い。
そして、定吉と若旦那の芝居ごっこ。妹の長襦袢を定吉に着せ、手拭いを姐さん被りにさせて、お軽の役に仕立て、自分は本身の刀を腰に差して平右衛門を気取る。「お前は兄さん、恥ずかしいわいな」…「勘平の女房とご存じあってのことか」「知らぬぞえ」…「その文残らず読んだその後で、互いに見交わす顔と顔」「ジャラ、ジャラ、ジャラつきだして身請けの相談」…「読めた!その頼みというわなあ」…。かよ師匠の三味線に乗って、流暢な芝居台詞が見事に決まる。ネタ卸しとは思えない出来栄えであった。
「甲府ぃ」。正直で働き者の善吉、なるほど豆腐屋主人が気に入るはずだと合点のいく高座。自分の娘のお花の婿にしたいと考えた主人、独りで盛り上がっちゃって、まだ善吉に話もしていないのに、「うちのお花のどこが気に入らないんだ!」と怒鳴っちゃうところが可愛い。また、休むことなく働く善吉を呼び「たまには休め」と言うとき、「さぞ、気の利かない馬鹿親父と思ったろ?」と三遍繰り返すところ、義理の父親としての照れみたいのが感じられてとても良かった。
あと、この店独特の売り声「豆腐ぃ、胡麻入り、がんもどき」を主人が善吉に仕込むところ、朝枝さんの良い喉に聴き惚れた。それを真似する善吉が音程を上手くとれないで頓珍漢な売り声を出すが、それが3年も経つと様になっているのが、サゲの「甲府ぃ、お参り、願ほどき」の良い喉でわかる。単純に良い喉を聴かせるのが目的ではなく、善吉の成長を示す意味で効果的に演出されているのが良いと思った。
夜は高円寺演芸まつり「おしくら饅頭、四派でドカン」に行きました。落語協会の林家彦いち師匠、落語芸術協会の瀧川鯉八師匠、圓楽一門会の三遊亭萬橘師匠、落語立川流の立川談笑師匠という顔付けだ。4人の個性がぶつかりあい、とても良い会だった。
立川談笑「金明竹」
与太郎に仕事や受け答えを教えるが、ことごとく失敗する「骨皮」の部分から丁寧に演じ、その上で上方言葉の言伝のところは津軽弁に改作した談笑オリジナルを披露。たっぷりと楽しませてくれた。それにしても、ネイティブでもないのに、あれだけ津軽弁を駆使できるのは、本当にすごい。
三遊亭萬橘「二階ぞめき」
古典の芯はしっかり保持しながら、独自の切り口で構成を組み立て直す手法は萬橘師匠の面目躍如たるところ。自分は素見(ひやかし)が好きなんだ、二階に吉原でもあれば外に出掛けることもないと若旦那が洒落で言ったことを、番頭は真面目に捉えて、本当に棟梁に頼んで二階に吉原を再現してしまうという…。
最初はこんなことで喜んでたまるかと思っていた若旦那が、あまりに良い出来栄えに感心し、ついにはその気になって、一人何役も演じて喜々として素見を楽しんでいる姿、特に若い衆と若旦那の喧嘩の場面は高座に寝転んでの大熱演で、客席は大爆笑だ。
瀧川鯉八「厚化粧」
唯一無二の鯉八ワールドである。不思議な世界に連れて行ってくれる。スナックのママとホステスの会話、半分以上解読不能なのだけれど、なぜかそこに妙な可笑しみがあるのが魅力だろうか。二つ目時代の作品は、内容をほぼ理解できたのだが、真打昇進後の最近の作品はシュールすぎて、僕には意味不明になることが多々あるのは、僕の脳の老朽化が進んでしまったということだろうか。
林家彦いち「私と僕」
SF作品だ。林家彦いちが26年前、1998年の下北沢に迷い込んだという設定が面白い。街の風景、流れる音楽、テレビの中のタレントやニュース…すべてが26年前。そして、行きつけだったバーに入店すると、カウンターの奥には「26年前の林家彦いち」が座っているという…。2024年の彦いちに対し、1998年の彦いちはタイムトラベルでは禁断とされている“未来がどうなっているか”という質問をしてしまう…。そして、その2024年の彦いちの前に、さらに26年後の彦いちが現れ…。自分という存在は、一体何者なのか?人間にとって永遠の課題を突き付けられたような、とても魅力的な作品である。