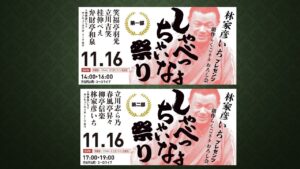【アナザーストーリーズ 】モナ・リザ来日狂騒曲 世界の至宝はそれでもほほ笑み続けた
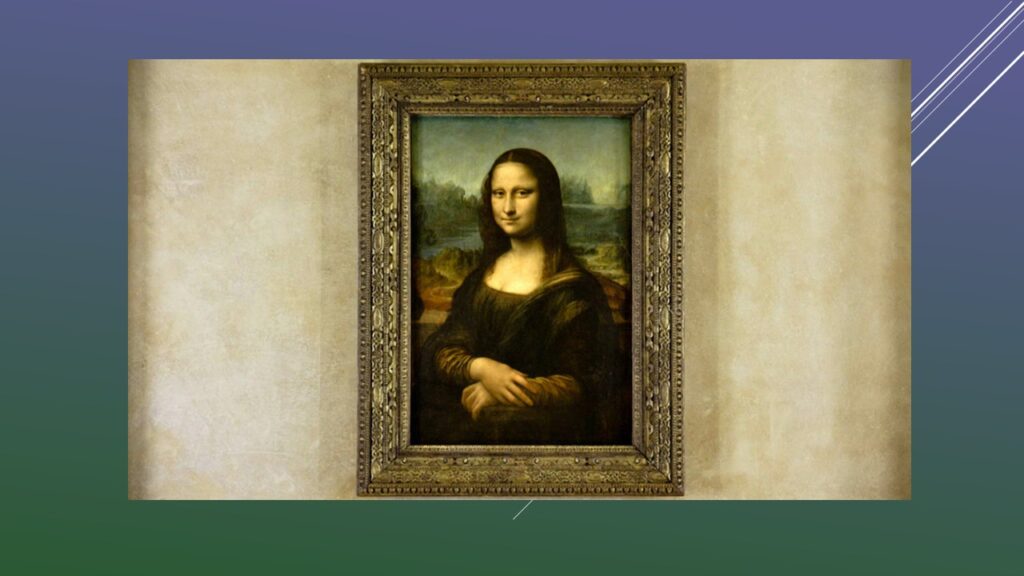
NHK―BSで「アナザーストーリーズ モナ・リザ来日狂騒曲 世界の至宝はそれでもほほ笑み続けた」を観ました。
1974年4月20日から東京国立博物館で「モナ・リザ展」が開かれ、50日間で150万人を動員した。当時小学生だった僕も両親に連れられて観に行ったのを覚えている。このモナ・リザ展を三つの視点から描いた非常に素晴らしいドキュメンタリーであった。
まず、フランスのルーヴル美術館から日本にモナ・リザを運搬して展示するために、日本の技術力が大いに寄与したことである。ポプラの板に描かれたモナ・リザは湿度や温度に非常に敏感で、厳重な管理が必須とされた。ルーヴル美術館の学芸員たちは貸出しに不安を持ち、万が一のことがあってはならないと考えた。そのために東京国立文化財研究所の研究員だった三浦定俊、日本硝子の伊藤宏、宮城敬雄らが結集して万全の体制が整られたのだ。
モナ・リザ来日の前年、ルーヴル美術館館長のピエール・コニアムとフランス美術館局科学研究所所長のマドレーヌ・ウールが来日し、東京国立博物館を視察し、特別5室の展示することが決まった。条件は湿度は50%前後、温度は18~21℃の間を保つこと。国立博物館は天井が高く、空間が広い。また、入り口から外気が入る恐れがある。この難題をどうするか。
モナ・リザをガラスケースの中に収め、湿度と温度を一定に保つことにした。当時、美術展示においてガラスはタブー視されていた。反射すること、割れると危険ということ。そこで工夫を凝らす。防犯のためにハンマーで叩いても割れない強化ガラスを観客側に使用。さらにモナ・リザ側には自動車に使われている合わせガラスを使用するという、複層ガラスの設計にしたのだ。建築技術と自動車製造技術の合わせ技で、美術品用密閉展示ケースが誕生した。
モナ・リザは来日以前に一度だけ海を渡ったことがある。1963年にアメリカのワシントン・ナショナル・ギャラリーで展示された。そのときは輸送用コンテナに入れて船で運んだ。今回は飛行機で輸送する。離着陸時の風圧や振動に耐えられるのか、負担が予想された。輸送用コンテナを包む特大ケースを作成し、耐火性のある青い塗料を塗った。同乗した在フランス日本大使館の一等書記官であった内田弘保は「梱包の際に大きな音がして心配したが、18時間後に日本に到着して梱包を解いたとき、コニアム館長が確認して『パルフェ!』つまり、完全であると言ったときには胸を撫でおろした」と語る。
4月20日公開スタート。大型連休に入り、観客の熱気で湿度が1~2%微妙に上昇し、このままにしておくと大変なことになると判断した。そのときに役立ったのが、展示ケースの下の小さな空間だった。そこには調湿剤のゼオライトが入っていて、その量を増加させることで、湿度は安定し、一定に保たれたという。管理責任者である三浦は「無我夢中だった」と振り返ったのが印象的だった。
二つ目の視点のキーマンは田中角栄である。1972年7月、内閣総理大臣に就任。田中は「日本列島改造論」を謳い、日本経済の発展を前面に打ち出した。だが、密かに文化庁が交渉を進めていた「モナ・リザ来日計画」を知ると、田中は経済だけではなく、文化・芸術も判る男だとイメージを変えることができると乗り気になったという。
在フランス日本大使館の内田は「そう簡単なものではない」と思ったし、ルーヴル美術館も「あり得ない」と否定的だったという。田中は1973年にヨーロッパを歴訪するが、その一番目の訪問国がフランスだった。当時、日本との経済摩擦が懸念されていた。ピエール・メスメル首相はある提案をする。フランス領アフリカにおけるウランの開発プロジェクトに日本も投資しないかというものだ。時代は石油依存から脱し、原子力発電が注目されていた。その原子力に欠かせないウラン鉱石の開発を誘ってきたのだった。
日本の資源外交はアメリカ中心だった。フランスが作る濃縮ウランを買うということは、アメリカを刺激することになる。1960年代、アメリカとソ連の二つの大国を中心に世界が回っていた。その一方でフランスのシャルル・ドゴール大統領が核兵器を持ちたいと考えた。そこでドゴールはモナ・リザをアメリカに貸し出すことで米仏関係を好転させる手に出る。そして、モナ・リザ展開催中に核保有宣言をしたのだ。アメリカの歴史作家、マーガレット・レスリー・デイビスが語る。「芸術が米仏両国の親善と友好の証しになった。二つの国が結びついた」。
田中角栄は決断する。ジョルジュ・ポンピドー大統領との首脳会談後の記者会見で「フランスの提案を受け入れ、濃縮ウランを日本が引き受ける意思がある」と述べた。その裏では「日本にモナ・リザを貸し出しましょう」という取引があった。これによって日仏関係は経済協力だけでなく、文化交流においても強化に弾みがついたのだ。ルーヴル美術館を訪れた田中はモナ・リザの前で立ち止まって言ったという。「これは日仏関係の歴史的1ページだ」。
第三の視点は目から鱗だった。モナ・リザ展初日におこったスプレー事件のことである。展示ケースに赤い塗料のスプレーを噴射した女性の名は米津知子。時代はウーマンリブ、女性解放運動が盛んな頃だった。だが、それは単に女性差別というのではなく、障害者差別も含めた抗議であった。
米津はポリオの後遺症で右脚麻痺という障害を持っていた。当時、優生保護法の改正がなされ、妊娠した女性が障害にある子を産む可能性がある場合は中絶を認めるという内容だった。それに加え、文化庁がこのモナ・リザ展では観客の移動をスムーズにするために、「身体不自由者はお断り」と発表したのだ。
米津は「このモナ・リザ展こそ、優生保護法そのものだ」と考え、障害者を排除するモナ・リザ展に反対するという趣旨で行動に出たのだった。決してモナ・リザを傷つけようとしたものではない。米津は軽犯罪法違反で起訴され、三千円の罰金が課せられた。2022年に創立150年を迎えた東京国立博物館の記念誌にモナ・リザ展のことが記されている。
本展によって当時社会問題となっていた「人権」の問題が大きく浮き彫りされた。あらゆる来場者が作品の前で立ち止まり、作品との対話を楽しむことを望む学芸員にとって、本展は特別展のあり方そのものにも思考を促すよい機会となった。
日本におけるモナ・リザのガラスケースを使った展示方法は、その後にルーヴル美術館でも採用された。だが、「日本のような最高の技術を再現することはうまくできなかった」という。
日本の科学技術の粋を集めた展示。外交の手段として使われた芸術。そして、障害者差別への反省。今から50年前のモナ・リザ展を三つの視点から切り取った、この番組の取材力、構成力に唸った。