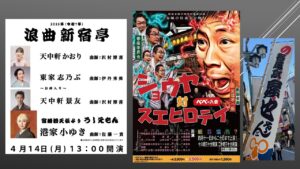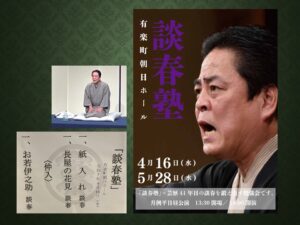わん丈、東へ西へ、昔へ今へ 三遊亭わん丈「鰍沢」「付き馬」

上野鈴本演芸場四月中席四日目夜の部に行きました。今席は三遊亭わん丈師匠が主任を勤め、「わん丈、東へ西へ、昔へ今へ」と題したネタ出し興行だ。①厩火事②五貫裁き~花魁の野望~③矢橋船④鰍沢⑤孫の営業⑥付き馬⑦休演⑧双蝶々 権九郎殺し⑨牡丹燈籠 お露新三郎⑩滋賀のらくだ。きょうは「鰍沢」だった。
「転失気」三遊亭東村山/「ローカルバス」三遊亭ごはんつぶ/太神楽曲芸 鏡味仙志郎・仙成/「有名人の家」三遊亭天どん/「代脈」柳家小平太/粋曲 柳家小菊/「歯ンデレラ」林家きく麿/「浮世床~夢」入船亭扇遊/中入り/漫才 風藤松原/「手水廻し」柳家㐂三郎/紙切り 林家楽一/「鰍沢」三遊亭わん丈
わん丈師匠の「鰍沢」。激しい雪の中、道に迷った大川屋新助が灯りの点いた民家を見つけて、一晩の宿泊を許されたときの安堵。そして、焚火にあたりなさいと言われ、凍えた手足を温めることができ、「火は何よりのご馳走」と人心地ついたときの幸せな気持ち。まず、その心理描写がこの噺では大切だ。
その上で、焚火の向こうのこの家のおかみさんを見る。歳は二十六、七。継ぎ接ぎだらけの着物を着ているが、抜けるような肌の白さ、すっきりとした目、きりりと締まった口元…こんな田舎には珍しい美貌。だが、喉から顎にかけて刃物の傷跡があり、それが一層その美貌を引き立てる。新助がそれだけ精神的に余裕が出てきたことが判る。
「江戸の方ではとお見受けしますが…」と問うと、実は昔吉原にいたと言う。新助は三年前の二の酉の晩を思い出す。「熊造丸屋の月之兎花魁では?」。女の方はハッとするが、新助は懐かしむような口ぶりで三年前の思い出を話し、「裏を返そうと思ったが、なかなか行けなかった。ようやく行くことが叶って、指名をしたら花魁は心中をしたと聞かされた…」。屈託のない素直な物言いで、女は新助に対する警戒心を緩めるのが伝わってくる。
女は「心中はしたんですよ」。ただ、し損なって、品川に売り飛ばされ、やっとの思いで今の亭主とこの山里に逃げてきた。そのし損ないが、この首の傷跡だと説明する。名前はお熊なので、この里では月の輪お熊と呼ばれている、亭主の伝三郎は生薬屋のしくじりなので、今はここで熊の膏薬売りをして生計を立てていると洗いざらい話すのは、新助は敵ではないと判断したからだろう。新助もそれを感じたのか、お熊のことを「昔は極彩色の煌びやさがあったが、今は墨絵の美しさがある」と褒めそやす。また、「この話を狂言役者が聞いたら、乙な二番が書けそうですね」とも言う。
だが、新助が命拾いをしてくれた御礼の気持ちだと言って、胴巻きから切り餅を取り出し、幾ばくかの金をお熊に渡すところから、お熊の気持ちに変化があったのだろう。「この男は金になる…」。玉子酒を作ってあげようと言って、実は毒を仕込み、それを新助に飲ませた。だが、新助は下戸なので少量しか飲まなかった。後から帰って来た亭主の伝三郎が何も知らずに、その玉子酒の残りをそっくり飲み干してしまった。新助の胴巻きを見て、「百両はある」と踏んでいたお熊の計略は意外なところで狂ってしまったわけだ。
苦しむ亭主を脇に見ながら、危険を察知して外に逃げた新助をお熊が鉄砲を持って追いかける。雪道を倒つ転びつ、泳ぐように逃げる新助は鰍沢の急流が見える断崖に追い込まれる。後ろは鉄砲、前は崖。足を滑らせて崖を落ちた新助は川にあった筏に掴まり、命を託す。だが、筏を繋いであった藤蔓が切れ、急流に飲まれる。材木はバラバラになり、一本の材木に必死にしがみつく新助。その様子を見たお熊は狙いを定め、鉄砲を撃つが…。弾は運良く新助の髷をかすめ、岩に当たった…。スリルとサスペンスに溢れた最後の情景描写も良かった。
上野鈴本演芸場四月中席六日目夜の部に行きました。三遊亭わん丈師匠が主任の「わん丈、東へ西へ、昔へ今へ」と題したネタ出し興行だ。きょうは「付き馬」だった。
太神楽曲芸 鏡味仙志郎・仙成/「のめる」柳家小平太/「不良クラブ」三遊亭天どん/粋曲 柳家小菊/「下町せんべい」柳家小ゑん/「人形買い」入船亭扇遊/中入り/漫才 風藤松原/「権助提灯」柳家勧之助/奇術 マギー隆司/「付き馬」三遊亭わん丈
わん丈師匠の「付き馬」。無銭飲食無銭遊興をする男の口八丁手八丁が気持ち良くて、嫌な気持ちにならないのがポイントだ。店に上がるところから、若い衆を自分のペースに乗せている。「お前さんのあがってもらいたいという気持ちと俺のあがりたいという気持ちがピタリと合った。ここは一つ、歩み寄らないかい?」。歩み寄るのは若い衆だけなのに、なぜか煙に巻かれて、「おあがりになるよー」。テンポ良く事が運ぶ。
翌朝もそうだ。勘定書きを見て、「安すぎる」とおだてておいて、「ごめん。うっかりしていた。印形を忘れた。君が書付を持って行っても、おばさんが信じないだろう。二人で行こう」。だけど、“おばさんの家”なるものを遠くから指差して、「まだ寝ているよ。寝込みを襲うのはいけない」と言って、大門を出て、この辺りをぶらぶらしようと提案。疑う若い衆に、「俺の目ごらんなさい。騙すような目をしているかい?」と自分のペースに巻き込むテクニックがすごい。
湯屋で汗を流して綺麗さっぱり、湯豆腐を食べてお銚子を15本空けて、その代金は「君、立て替えておいて」。「ない」と言うと、「あるよ!さっき紙入れに細かく畳んだ一円札があったよ!」。抜け目がない。浅草演芸ホールは芸協の芝居なので通過し、花やしきの前を通って、鳩の餌を売るおばさんへの皮肉を言って、仁王様に紙屑を投げてぶつかったところが力が湧くという蘊蓄を並べ、亀屋と木村屋と並んだ人形焼きの店頭の玉子の殻の嘘を暴いているうちに、雷門に出ちゃった。流石の若い衆も黙っていられずに「仲見世じゃないか!」。男は慌てず騒がず、「この目をご覧なさい!逃げる男の目をしているかい?そんな怖い顔しないの」。
ここまで来たら、田原町の早桶屋のおじさんに用立ててもらう方がいいと男はさも思い付いたように提案し、「御礼に帯源の鬼献もあげるよ」と甘い言葉で自分の筋書き通りに若い衆を騙す方向へもっていくテクニックに舌を巻く。「笑って!この目を見て!」。
あの男の兄貴が腫れの病で亡くなって、図抜け大一番小判型という早桶を拵えなければならずに途方に暮れていると小声で言うが、あとは若い衆に聞こえる大きな声で「おはようございます、おじさん!」「拵えてもらえませんでしょうか、おじさん!」「拵えてくれる?ありがとうございます、おじさん!」。これで話を付けて、男は逃げるように去って行く。残されたのは、若い衆と早桶屋のおじさんだ。二人の頓珍漢なやりとりが実に可笑しい。
「朝から変なことを頼んですみません」「いや、これも商売だから…この度はとんだことでございます」「いえ、よくあることですから」「長かったんですか」「昨夜、一晩」「それは驚いたでしょう」「いや、来るなと思っていました」「虫の知らせというやつですか。通夜の具合は?」「芸者幇間あげて、どんちゃん騒ぎ」「その方がかえって仏さんも喜ぶかもしれませんね」「仏さん、裸で阿波踊りを踊っていました」。通じているような、通じていないようなやりとりが楽しい。
「どうやってお持ち帰りに?」「懐に入れて…、大きな早桶ですね。どういう方」がお誂えに?」「お前さんが…兄貴が亡くなったんだろう?」「兄なんていませんよ」「気持ちはわかるが、落ち着いて」「さっきの人、あなたの甥御さんですよね?」「知らない奴だよ」「だって、叔父さんって…」「俺はおじさんだから返事をした。おばさんと呼ばれたら、返事をしない」。まさに“おじさん”マジック!
すっかり男に騙された若い衆と早桶屋のおじさん。「ここはお互い、歩み寄ろう。木口の代だけでいいよ」。「歩み寄る」というワードが再びここに登場するところ、わん丈師匠のセンスを感じた高座だった。